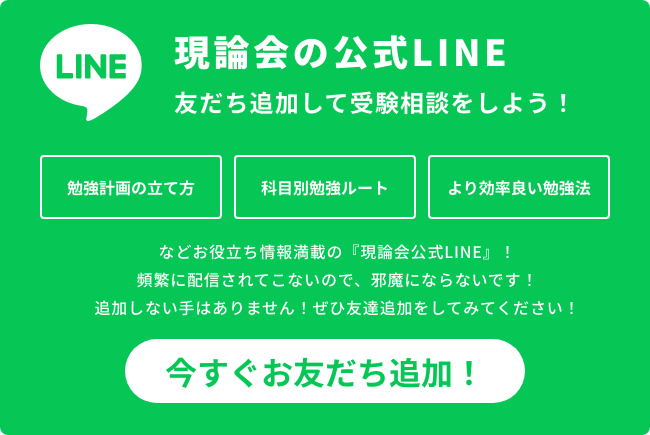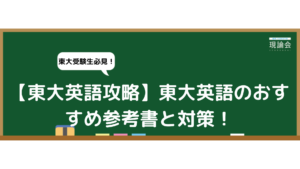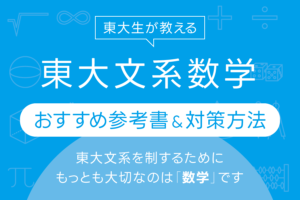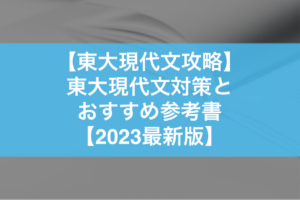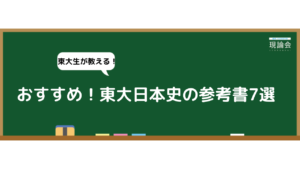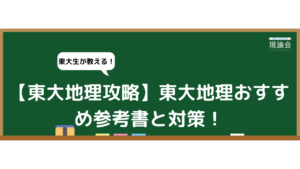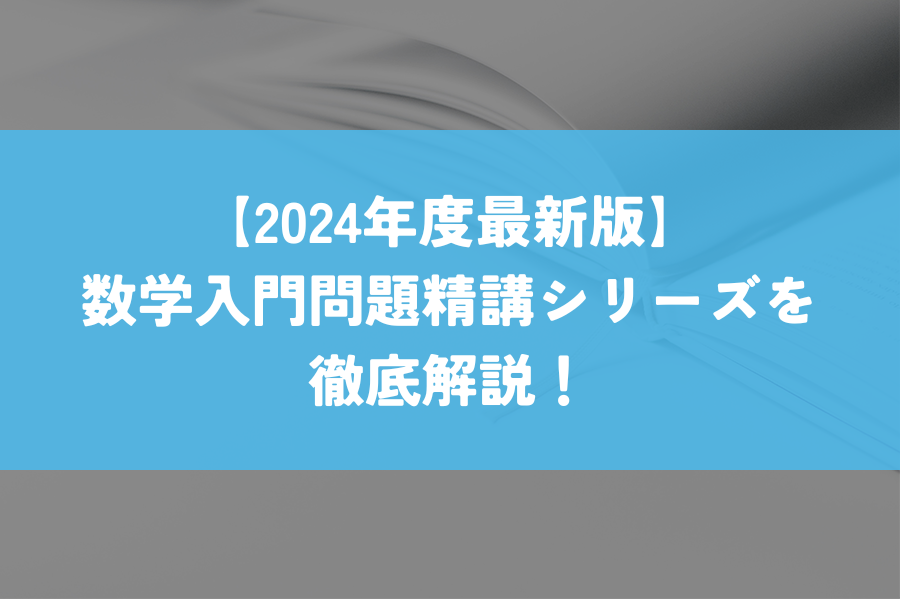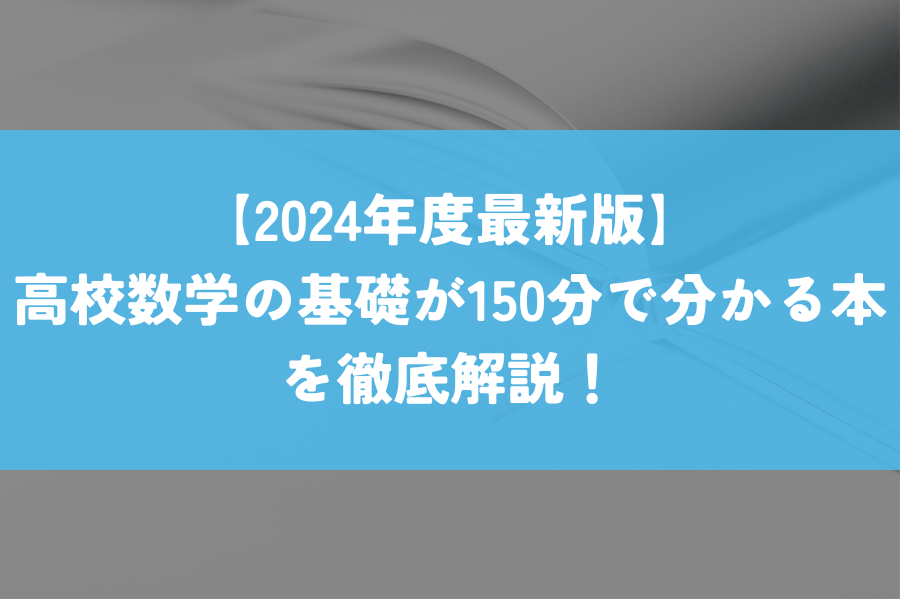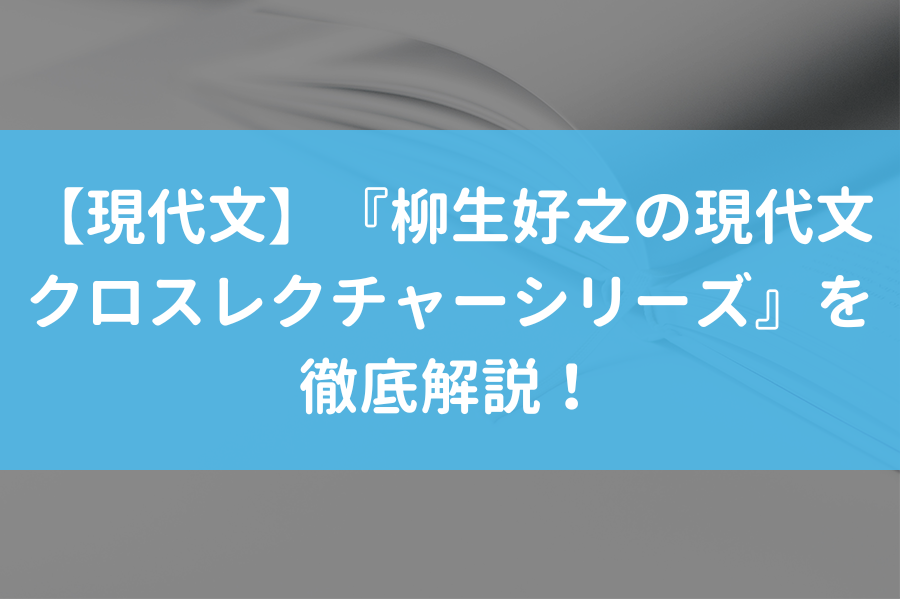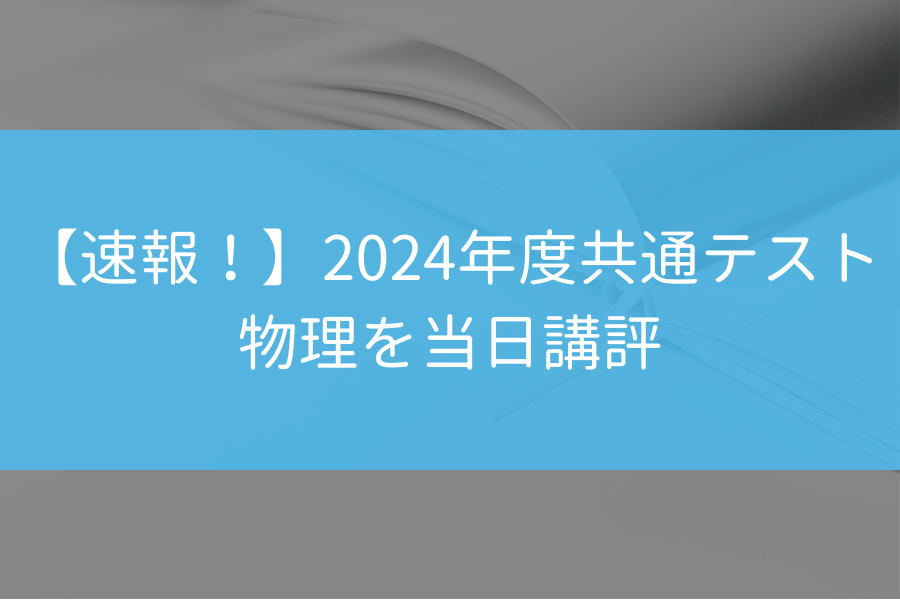【東大文系数学対策】文系数学満点の東大生が教える合格できる勉強法!

日本最難関の入試難易度を誇る大学、東京大学。
そんな東京大学では、文系といえども非常にレベルの高い数学力が求められます。
東大文系数学に対してどのような対策をしていくべきか。
東大文系数学で満点をとった筆者が、その勉強法をお教えします!
東大文系数学の概要

まずは東大文系数学の概要から見ていきましょう!
文系数学の傾向は非常にわかりやすいので要チェックです!
東大文系数学の合計得点は80点。
大問が4つになっており、それぞれに小問が2,3個ついています。
それぞれの配点は20点になっていて、部分点が非常に大きい=途中過程の採点が行われている傾向が見られています。
したがって、小問が有る無しに関わらず、その問題をどこまで解くことができたか。それが真正面から確かめられるテストになっています。
実際、筆者は満点と言いましたが、ラスト一問、答えを導出する式まで書き残したところでタイムアップとなってしまっていたのですが、それでも80点が帰ってきました。
東大文系数学において、その問題をきちんと理解できているんだよ、という証を残すことの重要性がわかるエピソードだと思っています。
そしてこの試験の合格点は例年40点程度。
つまり半分は完答する力を求められています。
近年は簡単になっている傾向があるため、これよりも高い合格点を求められることも多く、文系とはいえ気が抜けない試験となっています。
4問出題され、半分を解答する力が求められている
東大文系数学の対策

東大文系数学の大まかな概要を掴んだところで、対策にうつりましょう!
たとえ数学が苦手でもあることを意識するだけで変わってきます!
東大文系数学では、過程の採点が重視され、4問中2問を解ききれる力を求められていることはよくわかったと思います。
さて、そんな東大文系数学に対応するための勉強で意識すべき点は二つ。
解法暗記と、分野集中戦略です。
解法暗記
こちらの記事でも紹介していますが、解法暗記とは、例題で使われている「解法」を仕組みから理解した上で、類題にも使えるように暗記していくことです。
もちろんただ解答を暗記することとは全く違います。
この問題を解く際に有用なツールは何なのか。どういう手順でさばいていけば良いのか。
これを原理から理解してしまうことを「解法暗記」と読んでいます。
そして、東大文系数学では、この解法暗記が明暗を分けます。
東大文系数学の特徴として、比較的簡単な問題が2問と応用的な問題が2問の構成が多いというものがあります。
きちんと解法暗記ができていれば、この簡単な問題を取りこぼす確率がかなり下がります。
また、応用問題というのも、こうした解法を組み合わせて解いていくものです。
部分点の多い東大文系数学において、この解法までは思いついたけどこの先はわからなかったということを示すことで、完答はできなくても部分点を得ることができます。
こうした意味で、典型的な解法を完璧に自分のものにしておくことが東大受験生には必須の作業と言えるのです!
そして。これをできるようになるためには、徹底した標準問題の演習と理解が必要です。
一対一対応の演習や青チャートのような、良問を揃えた実践的な問題集を使って、徹底した解法暗記に努めましょう!
東大入試はまずは「解法暗記」から
1対1対応の演習や青チャートをやりこもう!
分野集中戦略

傾向がはっきりしている東大文系数学だからこそ使える戦略。
それこそが「分野集中戦略」です!
上記の解法暗記に加えて、東大文系数学対策で有効な戦略をご紹介します!
それは分野を絞って勉強すること!
まず、東大文系数学ではよく出る分野が明確に決まっています。
それは、
- 微積
- 図形と方程式
- 整数
- 確率
の4つ。
ここまで明確に分野が決まっているならば、ここに絞った対策を行っていけば良いのです!
そのためには、当然過去問25カ年を解いていく必要があります。
25ヵ年をやることによって東大で必要とされる考える力はどの程度なのか、どの分野が弱いのかを把握することができます!
ですが、それだけでは不十分。
分野を絞ってさらに深く勉強を進めることをお勧めします!
例えば確率などは確率漸化式の立式に繋げて答えを導出する問題が非常に多く出題されるため、こうした分野を集中的に勉強しておくことで一完を確保できます。
さらに他の難関大学で出題される、微積や方程式・整数の問題を解きまくる事により、こうした分野で出題される型をあらかた勉強し終えることができるようになるのです!
このように他大学の問題を解くには「問題演習」の問題集が非常に有効になります。
「問題演習」では「解法暗記」で培った知識を本番でどう使ったらいいかを取捨選択しながら解くことにより、実践力、思考力を伸ばすことができます!
おススメの参考書は以下のリンクの「問題演習」の項を確認してみてください!
【最新版】数学の参考書・問題集おすすめランキング!【これだけやれば大丈夫!?】
話を戻します!こうした分野で出題されないことがわかる「ベクトル」などの勉強は時間が無ければ手薄にするという戦略もあり得ます。
実際、筆者は、一対一対応より先、ベクトルの分野は一切勉強することなく東大文系数学で満点を取りました。
このような取捨選択により、集中的な勉強を行うことで、より合格率をあげることができる。
それこそが東大文系数学の王道対策なのです!
よく出る分野は微積・図形と方程式・整数・確率
分野集中で仕上げる
東大数学の対策方法

最後にどう勉強すると効果的なのかをご紹介したいと思います!
やるべきことは2つありましたね!
①東大25ヵ年を解く
②問題演習の参考書で分野別対策する
それではこれらのやり方を1つずつ解説していきたいと思います。
東大25ヵ年を解く
これは赤本の科目別の問題集になります。
とにかく東大の25ヵ年すべての問題が入っているため東大の傾向を常に感じることができます。
この問題集を本番までに解いていくわけですが、本番までの期間に合わせて始め方を変えてほしいと思います。
まず1つ目が10月より前に始める人、2つ目が10月より後に始める人です。
10月より前から始める人は比較的、時間的余裕があるので昔の問題からさかのぼるように解いていきましょう!
こうすることで思考力を鍛えながら最後には東大文系数学が求めてくる問題たちに対してパワーアップした状態で挑むことができます!
一方10月以降に始める人は最近の問題から始めましょう!
10月は少し気を抜いているとすぐ共通テスト対策を行わなくなってしまいます。
つまり、先に最近の傾向をつかむことが必要となってくるのでスタートは東大文系数学の最近の問題からとなります。
1日の分量は多くて3問程度、時間がある時は1年分やるくらいにとどめることで復習をおろそかにすることなく学習することができるでしょう!
また問題の難易度は難しくてもC問題に押さえておきましょう。
問題演習の参考書で分野別対策する
続いて問題演習の参考書による分野別対策です。
問題集の問題は分野別で分けられているため、まずは微積・図形と方程式・整数・確率に絞って勉強しましょう。
こちらも1日3問程度に抑えることで1問当たりの考える時間を20分以上確保し、復習をきちんと行えるようにしましょう。
ただ問題集をこの4つの分野のためだけに使うのは少しもったいないですよね。
なので、東大文系数学25ヵ年でできなかった分野を問題集の問題を使って考える練習をするということも適宜行うと良いでしょう!
こうすることで東大文系数学に出るかもしれない設定の問題を解くことができます!
問題演習は①25ヵ年②問題集でおこなう
1日の量は3問程度にして1問についてじっくり考える
まとめ
東大文系数学の特徴をお教えしたのち、解法暗記と分野集中戦略に絞って東大文系数学の対策法を解説してきました!
東大文系数学は対策をきちんとすれば十分に満点を狙える試験です。
一つ一つ解法暗記を積み重ねて、合格を勝ち取っていってください!
この記事に関連したオススメ記事

関連する勉強法も全て頭に入れて、より効率的で自分に合った勉強法を見つけてください!
オススメ第1位:【数学勉強法】東大数学満点が教える絶対に成績が上がる数学勉強法
オススメ第2位:【東大英語対策】東大合格に必須な英語の勉強法と時間配分を知ろう!
オススメ第3位:【必須参考書】数学の各チャートの難易度とレベル別勉強法!
YouTubeチャンネル・Twitterのご紹介