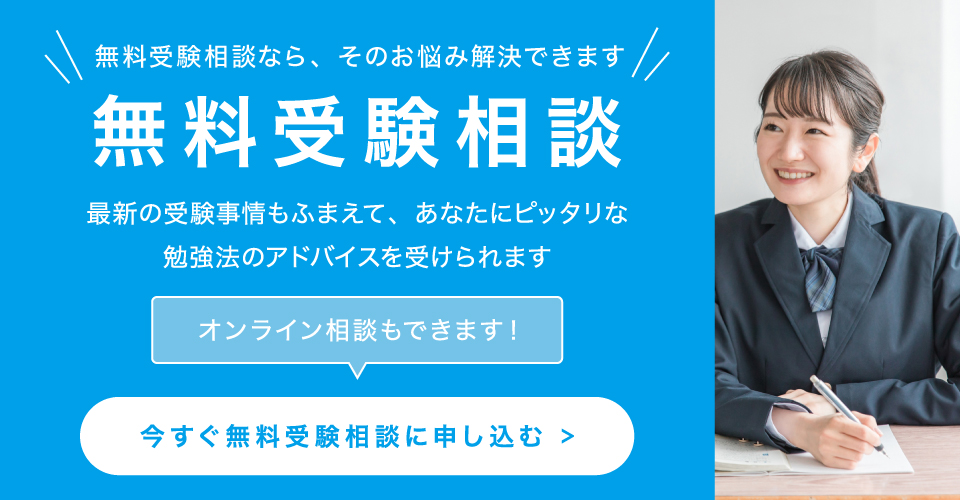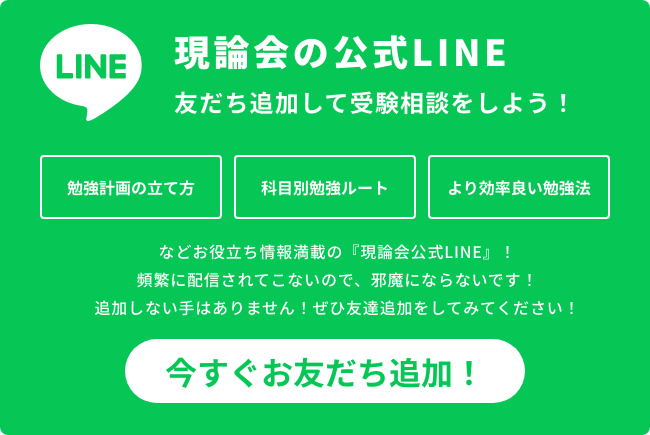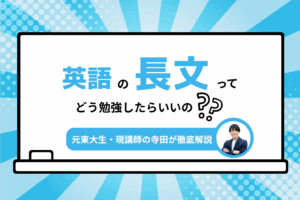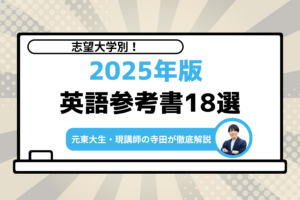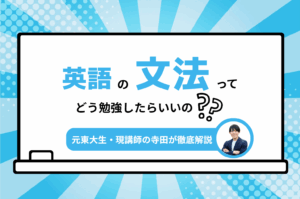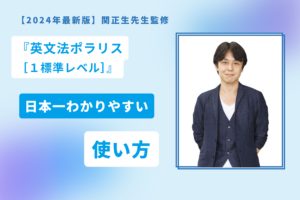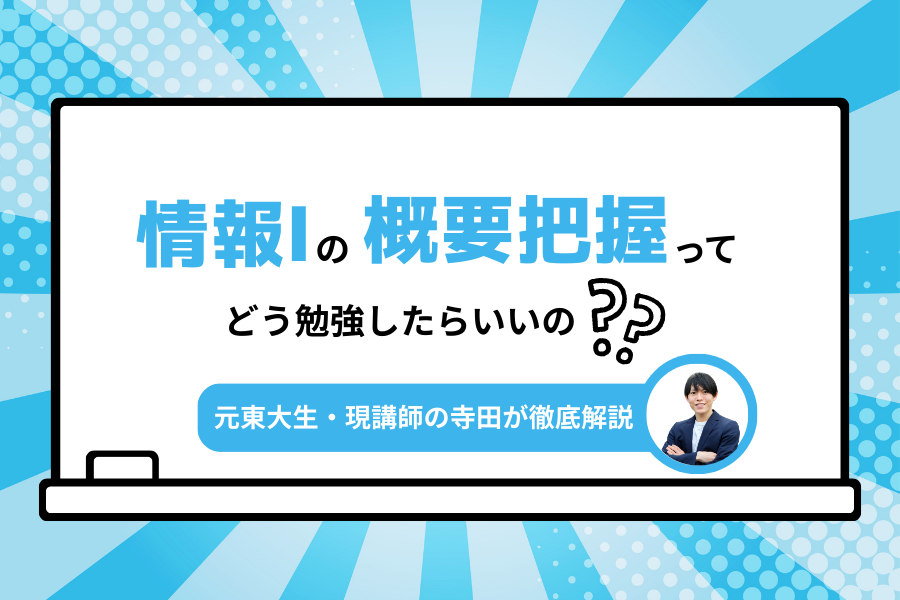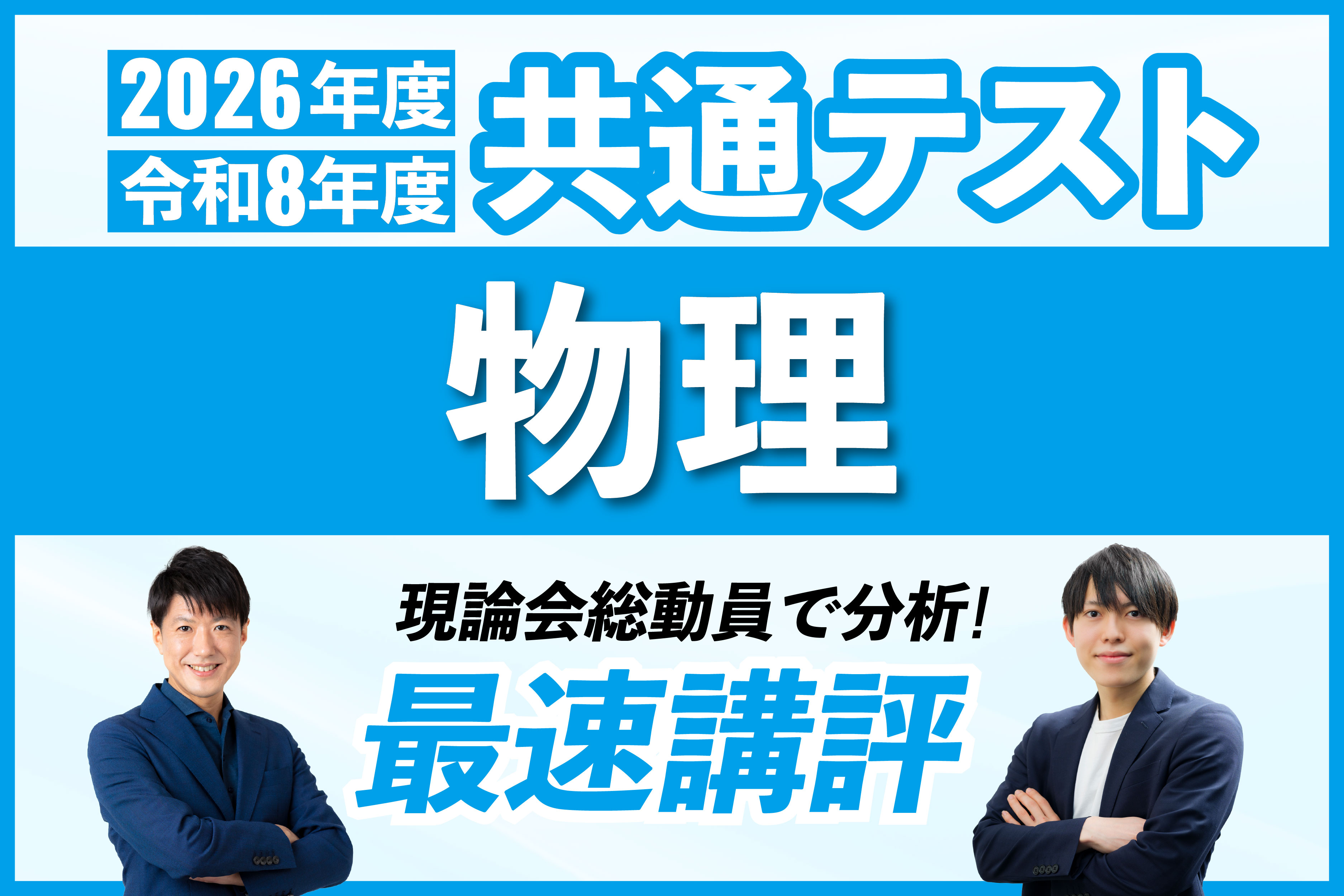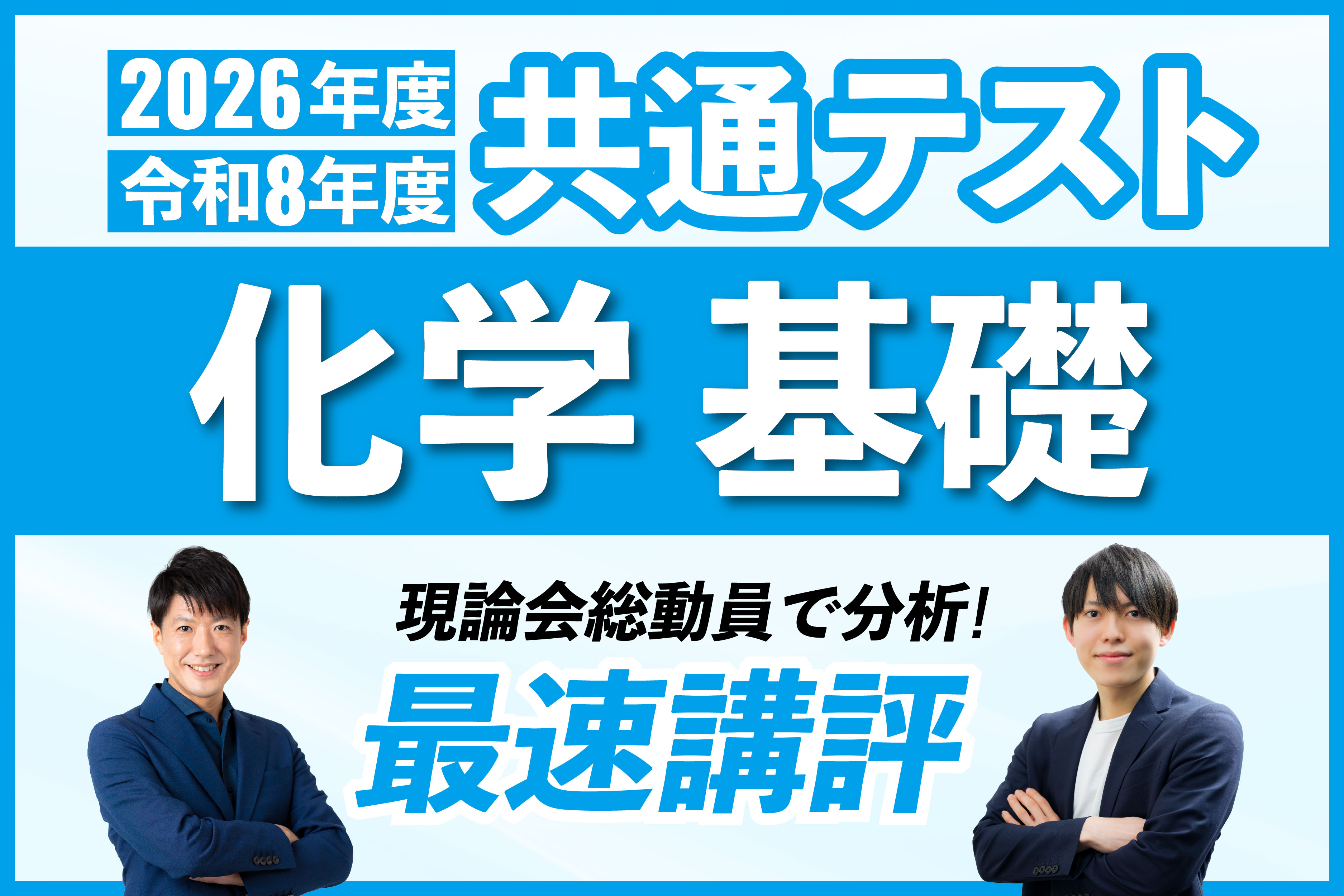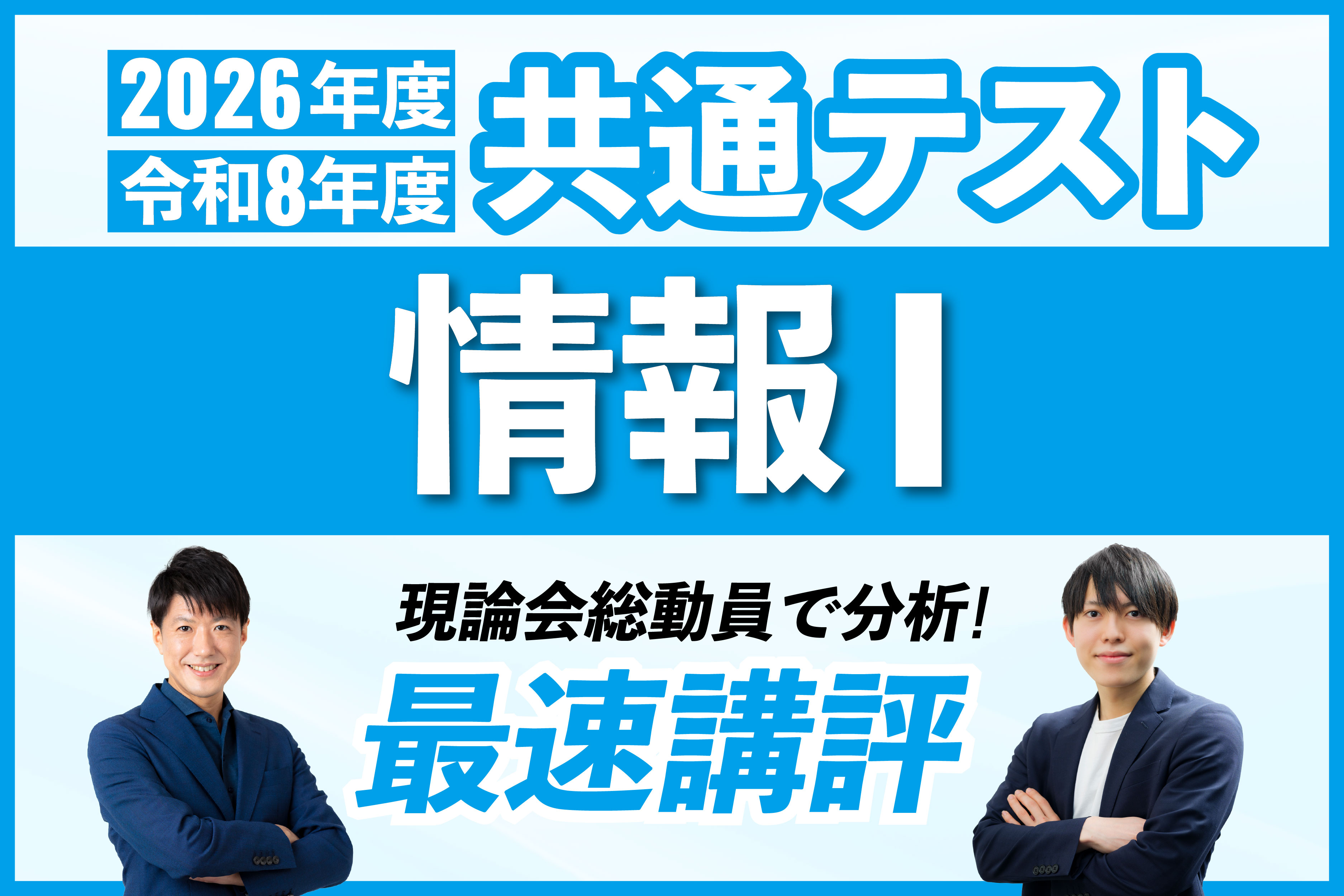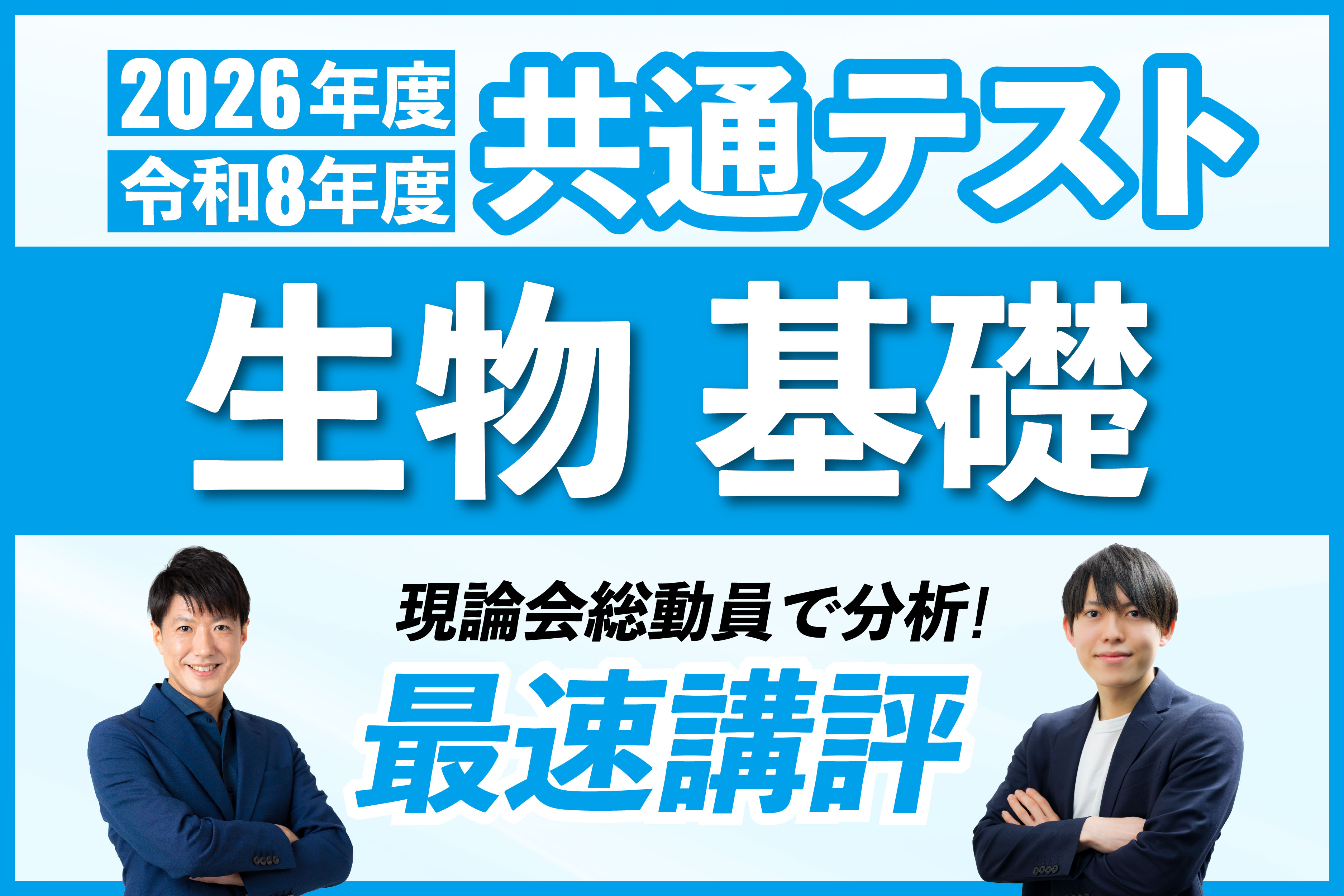【2025年最新版】英語長文の学習法を徹底解説!レベル別おすすめ参考書も紹介!
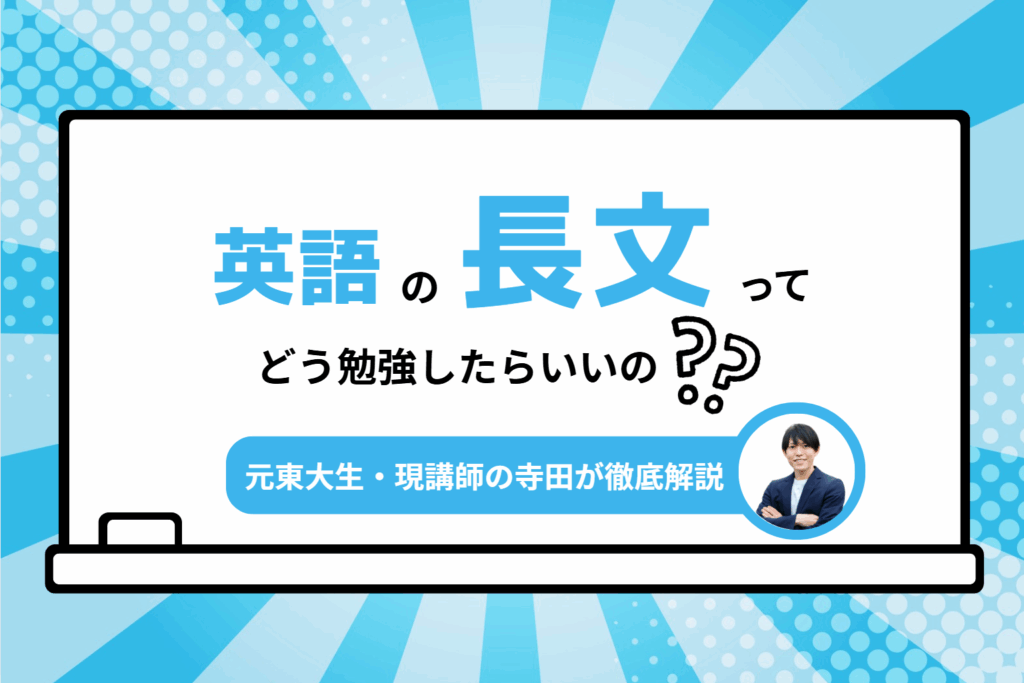
英語の勉強を進める中で、多くの受験生が壁にぶつかるのが「長文読解」です。
「長文読解になると、なぜかスコアが安定しない…」
「なんとなく訳せても、設問に正解できない…」
「単語・文法・解釈は固めたはずなのに、点数に繋がらない…」
このような悩みの原因は、単なる演習不足ではなく、長文読解の「正しい勉強法」を知らないことにあります。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、以下の内容を徹底的に解説します!
- 長文読解で確実に点を取るための学習の全体像
- レベル別・おすすめの参考書と、その効果的な使い方
- 偏差値70の壁を越えるための具体的な学習戦略
この記事を読み終える頃には、長文読解を得点源に変えるための道筋が、明確に見えているはずです。
また、長文読解を勉強する前に、英語の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!
英語の勉強法の詳しい情報についてはこちら
長文読解の攻略法
長文読解とは?
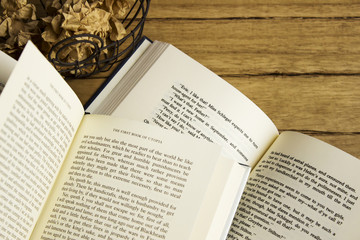

英語の勉強法は「単語」「文法」「英文解釈」「長文読解」という段階に分類できます。
単語
英語の4技能すべての基礎になる、英単語と英熟語を学習する段階です。 今後学習をしていく「文法」「解釈」「長文」「英作文」などの各段階においても、単語の習熟度が低いと勉強効率が落ちるため、英語学習において最も重要な段階です。
文法
英語のなかで最も触れる頻度も高く、重要度も高いのが文法です。4技能の基礎にあたります。 究極的には英文法が身についていれば、解釈や英作文も専用の対策をせずともできるようになりますが、現実的にはそうはなりません。 大切なことは、文法は完璧主義になりすぎずに軽く勉強をしておき、その後に各学習段階で特化して勉強していくことです。
英文解釈
解釈というのは、「読んだり聞いたりするのに必要な文法」を学ぶことです。言い換えると「英文の構造を掴む訓練」のことです。英語は配置の言語と呼ばれるほど文構造に敏感な言語です。逆にいうと文構造さえ掴んでしまえば、簡単に意味を掴むことができます。「解釈」の訓練をしっかり行えば、ゆっくりとですが確実に英文を読むことができます。
長文読解
長文はただ解くのではなく、再現性を持って点数を取ることが大切になります。そのためには長文の読み方と解き方を身につけたうえで、同じやり方で問題演習をしていくことが重要になります。
上から順に英語の基礎を積み上げていき、最終的に入試問題にも対応できる英語力を身につけていく必要があります。
長文読解は、英語学習の集大成です。単語や文法は、いわば戦うための「武器」や「防具」です。しかし、それらを身につけただけでは、ラスボスである長文問題に勝つことはできません。
なぜなら、長文読解には、文章全体の論理の流れを追い、対比や因果関係を捉えながら筆者の主張を見抜く戦略が必要不可欠だからです。この戦略がなければ、一文一文は訳せても、「結局、何が言いたいのか」が分からず、設問に正解することができません。
長文読解は、すべての英語学習のゴールであり、最も配点の高い得点源です。武器を磨くだけでなく、長文の読み方と説き方を身に付けたうえで問題演習を積みましょう。
長文読解を学ぶ3つのメリット

長文読解の学習は、英語学習全体の得点率を上げるための重要なステップです。以下のような大きなメリットが得られます。
1. 合否を分ける最大の得点源になる
大学受験の英語では、長文読解でいかに点数を稼げるかに合否が大きく左右されます。ほとんどの大学で配点が最も高く、長文読解の正答率が重要になります。問題演習を重ねて読解力が安定すれば、英語全体の成績も底上げできます。
ライバルに差をつけ、英語を得意科目にしたいなら、長文読解は絶対に落とせない最重要分野です。長文読解を制することが、志望校合格への近道です。
2. 単語や文法、英文解釈の穴を見つけることができる
単語や文法を一つひとつ学習するだけでは、知識はまだバラバラの状態です。長文読解は、それらの知識を同時に、かつ制限時間内に使いこなすための実践訓練です。
そのため、演習を通じて単語や文法、英文解釈における自分の弱点を客観的に発見することができます。
長文読解を学習することで、自分の知識の曖昧な部分や抜け漏れを明確ができ、より的確な復習を行うことができます。
3. 英語特有の論理展開に慣れることで、リスニングや英作文が得意になる
長文読解の演習を重ねることで、英語に特有の論理展開パターンが自然と身につきます。
例えば、英語の文章では「①主張 → ②具体例(For example,) → ③逆説(However,)」といった流れが頻繁に登場します。このパターンに慣れると、
- リスニングで 「However,」と聞こえた瞬間に「ここから反対意見が来る」と話の展開を先読みできるようになり、音声の理解度が上がります。
- 英作文で 「主張の後は具体例を入れよう」というように、英語の論理展開パターンを活用でき、説得力のある文章を組み立てることができます。
長文読解を通じて、英文を読むだけでなく、リスニングや英作文にも直結する論理展開力を鍛えることができます。
長文読解の勉強法

先ほど説明した通り、長文読解は単語や文法、英文解釈を基に成り立つ学習段階になります。
まだ、単語・文法・英文解釈の学習が進んでいない方は、まず以下の記事を参考に単語・文法・英文解釈の基盤を固めることをお勧めします。
単語・文法・英文解釈の学習に関する詳しい情報についてはこちら
【保存版】大学受験 英単語の王道勉強法!定着率が上がる覚え方&志望校別おすすめ参考書

次に具体的な「長文読解の勉強法」について紹介します。
STEP 1. 【インプット】講義系参考書で「読み方・解き方」のルールを学ぶ
目的: 感覚やフィーリングに頼らず、論理的な長文の読み方を身に付ける。
多くの受験生が、いきなり本文を読み始めてしまいますが、それでは行き当たりばったりの読解になり、点数は安定しません。まずは、長文の正しい読み方を学びましょう。
この段階では、『関正生のThe Rules英語長文問題集』シリーズなどの講義が詳しい参考書や『パラグラフリーディングのストラテジー』シリーズなどの参考書を使い、以下の知識をインプットします。
- 読む前の情報収集: 本文を読む前に「設問」や「注釈」に目を通し、文章のテーマや話の展開を予測する方法。
- パラグラフリーディング: 「1パラグラフ=1つの主張」という原則を理解し、段落ごとの要点を掴みながら読み進める技術。
- 設問へのアプローチ法: 内容一致問題、和訳問題など、問題形式ごとの最適な解き方。
これらのルールを学ぶことで、長文の論理的な読み方を身に付けることができます。
STEP 2.【アウトプット】問題演習で、時間内に得点する力を養う
目的: 学んだルールを使いこなし、制限時間内に合格点を取るための実践力を鍛える。
ルールを学んだら、次は実践です。『関正生の英語長文ポラリス』シリーズなどの問題集を使い、アウトプットの訓練を積みましょう。
- 時間を計って問題を解く:本番を意識し、必ず時間を計って取り組みましょう。事前に各大問の時間配分を決め、それを守る意識が重要です。
- 学んだルールを総動員する:「読む前に設問をチェック」「パラグラフごとにメモを取る」「内容一致問題は本文に根拠を探す」など、STEP1.で学んだ全てのルールを意識的に使いながら解き進めます。
- 根拠を持って解答する:特に内容一致問題では、「なんとなく」で選択肢を選ぶのをやめ、「本文のこの部分に○○と書いてあるから、これが正解だ」と、明確な根拠を持って解答する癖をつけましょう。
このような実践を積むことではじめて、STEP1.で学んだ知識が得点に直結する使えるスキルになります。
STEP 3. 【反復学習】徹底的な復習で、再現性を持った読み方ができるようにする
目的: 一度解いた問題を活用し、知識を完璧に定着させ、同じミスを繰り返さない力を身につける。
英語長文の成績は、問題を解いた時間ではなく、復習の質と量で決まります。本番で初見の長文を正しく読むための実力は、この反復学習によって養われます。
具体的には、以下の3つの復習を必ず行いましょう。
- 精読: まずは時間をかけ、分からなかった単語や構文を全て調べ、自力で全文の正確な和訳ができる状態にします。
- 問題の解き直し: 次に、なぜその答えになるのか、正解の根拠が本文のどこにあるのかを一つひとつ確認します。「なぜ自分は間違えたのか」「どう考えれば正解できたのか」を分析し、思考のプロセスを修正します。
- 音読: 最後に、仕上げとして最低10回を目安に音読を繰り返します。スラスラと意味を理解しながら読めるようになるまで繰り返すことで、速読力とリスニング力が同時に鍛えられ、英文が体に染み込んでいきます。
この徹底的な復習を行うことで、一つの長文から得られる学びが最大化でき、他の長文問題においても再現性を持って点数を取ることができます。
- 【インプット】講義系参考書で「読み方・解き方」のルールを学ぶ
- 【アウトプット】問題演習で、時間内に得点する力を養う
- 【反復学習】徹底的な復習で、再現性のある読み方ができるようにする
おすすめ参考書と効果的な学習戦略

現論会でも使用している、【2025最新版】志望校レベル別おすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します。
ここでは、長文読解の学習に特化した、おすすめの参考書とその効果的な使い方を、具体的な学習ステップに沿って解説します。
①日東駒専・産近甲龍合格レベル、共通テスト7割レベル(偏差値~55)
🔹 対象: 基礎に不安があり、共通テストで7割を目指したい人
🔹 目標: 共通テスト7割、日東駒専・産近甲龍の基本問題を解けるようにする
おすすめ参考書
①<インプット編>『関正生のThe Rules英語長文問題集1』
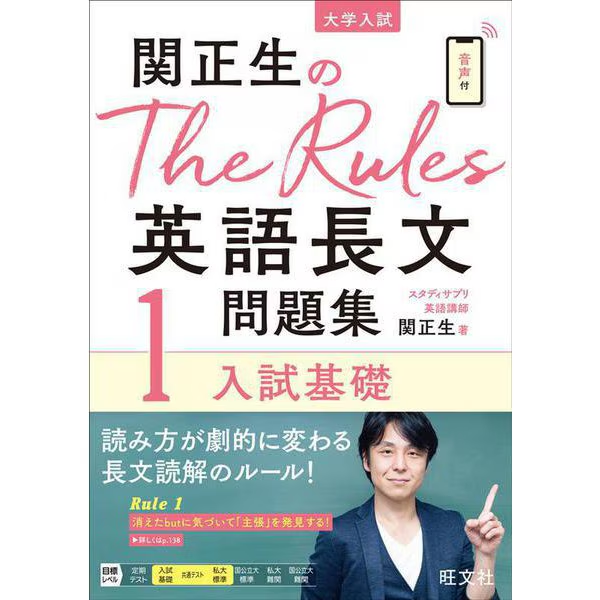
まず最初にご紹介するのは『関正生のThe Rules英語長文問題集1』です!
スタディサプリの実力派講師である関正生先生の書です。
このシリーズは、以下のようにレベルが分かれています。
『関正生のThe Rules英語長文問題集1』:入試基礎〜日東駒専・共通テスト
『関正生のThe Rules英語長文問題集2』:共通テスト〜成成明学獨国武、関関同立
『関正生のThe Rules英語長文問題集3』:GMARCH、地方国公立
『関正生のThe Rules英語長文問題集4』:早慶、旧帝大
自分の志望校のレベルに合った本を選ぶようにしましょう!
この本の最大の特徴は、試験本番にどのように長文問題を解いていくか、受験生視点で詳しく解説されている点です。
また、構文分析が詳しく載っているため、復習の際の音読が容易という特徴もあります。
解答のプロセスまで非常に詳しく解説されているため、長文問題で点数が取れていない方には絶対に取り組んでほしい一冊です。
②<アウトプット編>『関正生の英語長文ポラリス1』
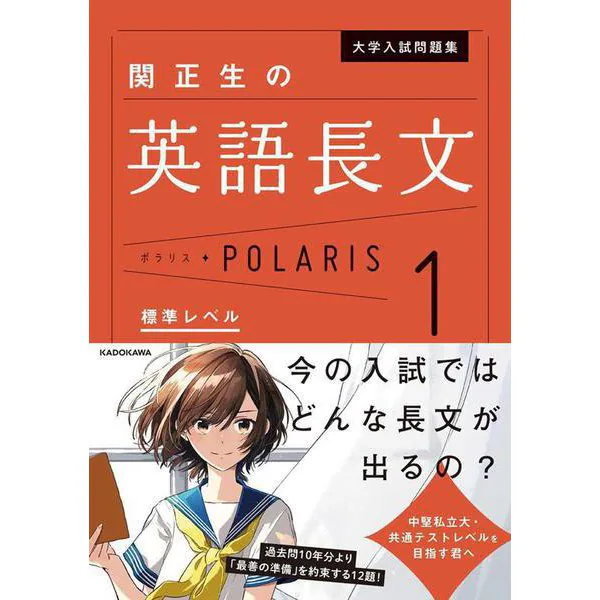
次にご紹介するのは『関正生の英語長文ポラリス1』です!
すべての長文に構文解析が付いているため、1文1文丁寧に確認できることが特徴です。また、出題テーマについても最新の傾向が反映されており、最新の入試問題の傾向を掴むことができる参考書になっています。
レベル別で分かれているので、自分に適したレベルを選ぶようにしましょう。
『関正生の英語長文ポラリス1(標準)』:日東駒専・産近甲龍レベル
『関正生の英語長文ポラリス2(応用)』:GMARCH・関関同立・難関国公立レベル
『関正生の英語長文ポラリス3(発展)』:旧帝・早慶・東京一科レベル
日東駒専・産近甲龍合格レベル、共通テスト7割レベル(偏差値~55)の場合は、まずは『関正生の英語長文ポラリス1』で基礎知識をつけるようにしましょう!
学習戦略
まず長文読解の「正しい読み方・解き方」の型を身につけることが最優先です。フィーリングに頼った読解から脱却し、安定して得点するための土台を築きましょう。
- 【STEP 1. <インプット>『関正生のThe Rules英語長文問題集1』で読み方のルールを学ぶ】
- まずは『関正生のThe Rules英語長文問題集1』を解き進め、「パラグラフの要点を掴む方法」「設問のパターン別解法」など、長文問題の正しい読み方を学びます。
- 問題を解くことはもちろん、解説を熟読し、「なぜそのように読むのか・解くのか」という思考プロセスを理解することに集中してください。
- 【STEP 2. <アウトプット>『関正生の英語長文ポラリス1』を解いて知識をアウトプットする】
- 次に『関正生の英語長文ポラリス1』を使い、時間を計って問題を解きます。
- STEP1.で学んだ「読む前に設問をチェックする」「パラグラフごとに要点をメモする」といったルールを意識的に実践しましょう。
- 最初は時間がかかっても構いません。一つひとつ丁寧に行うことで、徐々に型が身についていきます。
- 【STEP 3. <反復学習>徹底的な復習で「型」を定着させる】
- 問題を解き終えたら、答え合わせをして終わりではなく、精読・解き直し・音読の3ステップで徹底的に復習します。
- 特に、「なぜその答えになるのか」という設問の根拠を本文中から見つけ、自分の思考プロセスとどこが違ったのかを分析することが重要です。このサイクルを繰り返すことで、学んだ「型」が体に染み込みます。
②地方国公立、GMARCH理科大、関関同立、共通テスト8割レベル(偏差値~60)
🔹 対象: 基礎はある程度できていて、共通テストで8割を目指したい人
🔹 目標: 共通テスト8割、二次試験の基本問題を解けるようにする
おすすめ参考書
①<インプット編>『関正生のThe Rules英語長文問題集2』
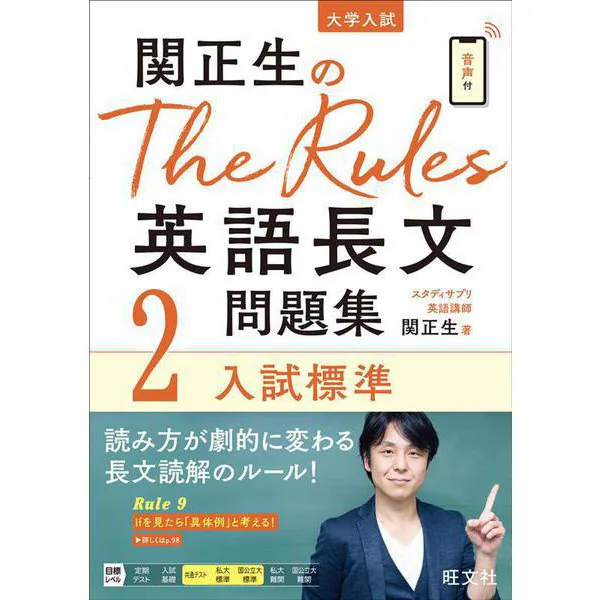
インプット編一冊目としてご紹介するのは、『関正生のThe Rules英語長文問題集2』です。
こちらはレベル別で分かれているので、自分に適したレベルを選ぶようにしましょう。
『関正生のThe Rules英語長文問題集1』:入試基礎〜日東駒専・共通テスト
『関正生のThe Rules英語長文問題集2』:共通テスト〜成成明学獨国武、関関同立
『関正生のThe Rules英語長文問題集3』:GMARCH、地方国公立
『関正生のThe Rules英語長文問題集4』:早慶、旧帝大
地方国公立、GMARCH理科大、関関同立、共通テスト8割レベル(偏差値~60)の場合は、まずは『関正生のThe Rules英語長文問題集2』に取り組み、知識を確かなものにしましょう!
②<インプット編>『パラグラフリーディングのストラテジー①』
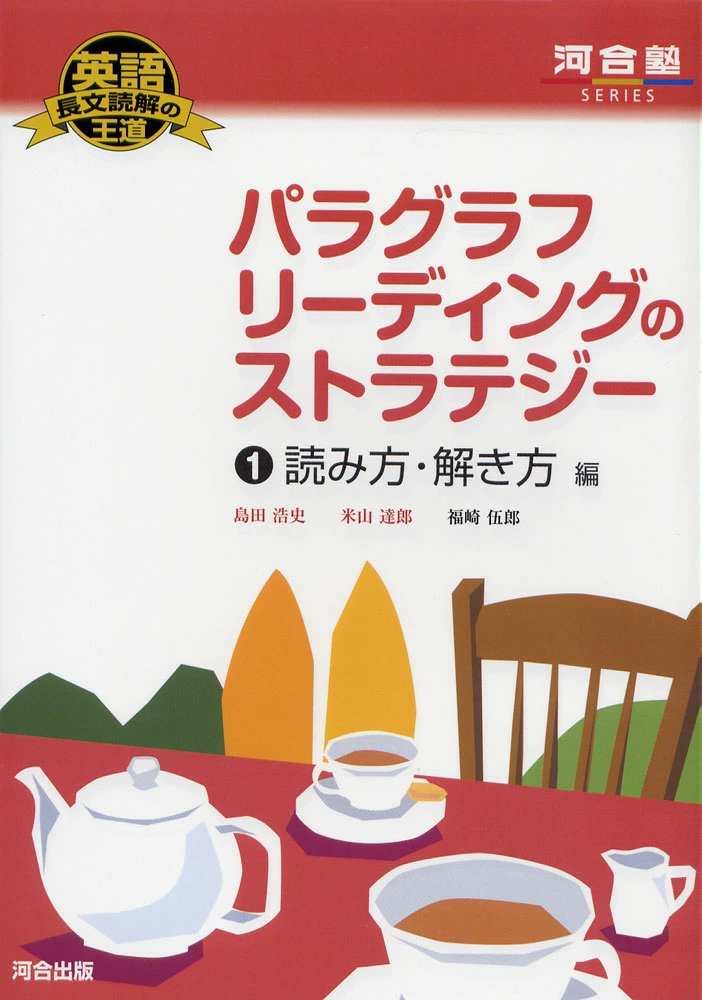
次に紹介するのは、『パラグラフリーディングのストラテジー①』です。
このシリーズは、志望校によって以下のように分かれています。
①読み方・解き方編
②実践編:私立大対策
③実践編:国公立大対策
①読み方・解き方編は、私立大・国公立大共通の長文の読み方を学ぶことができるため、どの大学を志望する方も読んでほしい一冊です。
こちらのシリーズは、文章の論理的展開がどのようになっているのかや、難単語の類推の仕方など、入試問題を解く上で必要な方法論が載っています。
例えば、第1パラグラフの次の第2パラグラフの先頭にHoweverがついている場合、第1パラグラフの内容とは反対のものがくるという事が分かります。
その後、英文解釈のアウトプットを兼ねて英語長文問題集に入っていくことができます。
英語長文は、難易度が上がれば上がるほど構文が複雑になります。
構文が取れなかった場合、必ず英文解釈の参考書に戻って復習し、再度構文を取り直してみましょう!
『関正生のThe Rules英語長文問題集』シリーズが、全文構文解説がついており、早く正確に長文を読み解く訓練をする問題集であるのに対し、『パラグラフリーディングのストラテジー』シリーズは、部分的に未知な箇所があったとしても、主張を捉え論理的に正解を導けることを伝える参考書となっています。
③<アウトプット編>『関正生の英語長文ポラリス2』
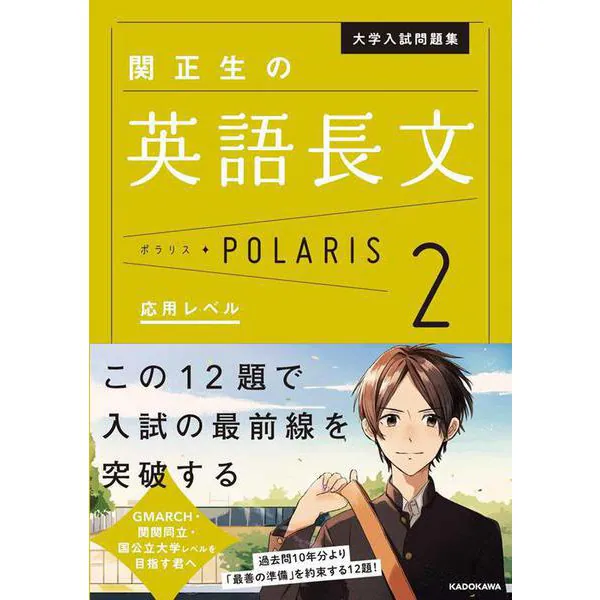
アウトプットの教材としてご紹介するのは、『関正生の英語長文ポラリス2』です。
こちらのシリーズはレベル別で分かれているので、自分に適したレベルを選ぶようにしましょう。
『関正生の英語長文ポラリス1(標準)』:日東駒専・産近甲龍レベル
『関正生の英語長文ポラリス2(応用)』:GMARCH・関関同立・難関国公立レベル
『関正生の英語長文ポラリス3(発展)』:旧帝・早慶・東京一科レベル
地方国公立、GMARCH理科大、関関同立、共通テスト8割レベル(偏差値~60)の場合は、『関正生の英語長文ポラリス2』で問題演習を重ねましょう!
学習戦略
基礎的な読み方を土台に、より複雑な文章でも論理的に内容を追い、安定して高得点を取るための「読解の精度」を高めることが目標です。
- 【STEP 1. <インプット>『関正生のThe Rules英語長文問題集2』と『パラグラフリーディングのストラテジー①』を読んでルールをインプットする】
- 『パラグラフリーディングのストラテジー①』で「トピックセンテンスの見つけ方」「論理マーカーへの注目」といった基本原則を学びます。
- 『関正生のThe Rules英語長文問題集2』の少し難解な文章を素材に、『パラグラフリーディングのストラテジー①』の基本原則を、いかにして応用するかを学びます。
- 【STEP 2. <アウトプット>『関正生の英語長文ポラリス2』で実践演習を行う
- 『関正生の英語長文ポラリス2』を使い、時間配分を意識しながら問題を解きます。
- 「なんとなく」で選択肢を切ることをやめ、全ての選択肢の正誤の根拠を『パラグラフリーディングのストラテジー①』で学んだ原則に基づいて本文中に求めることを徹底してください。
- 【STEP 3. <知識の定着>基本原則に立ち返り復習する】
- 復習の際、なぜ間違えたのかを分析する時に、必ず『パラグラフリーディングのストラテジー①』の基本原則に立ち返りましょう。
- 「ディスコースマーカーを見落としていた」「具体例を主張と勘違いしていた」など、自分のミスの原因を基本ルールと結びつけることで、読解の精度が向上します。
③旧帝大、早慶レベル(偏差値~65)
🔹 最難関大レベルを目指し、共通テスト8割5分以上を狙いたい人
🔹 難関大二次試験で合格点を取れるようにする
おすすめ参考書
①<インプット編>『関正生のThe Rules英語長文問題集3』
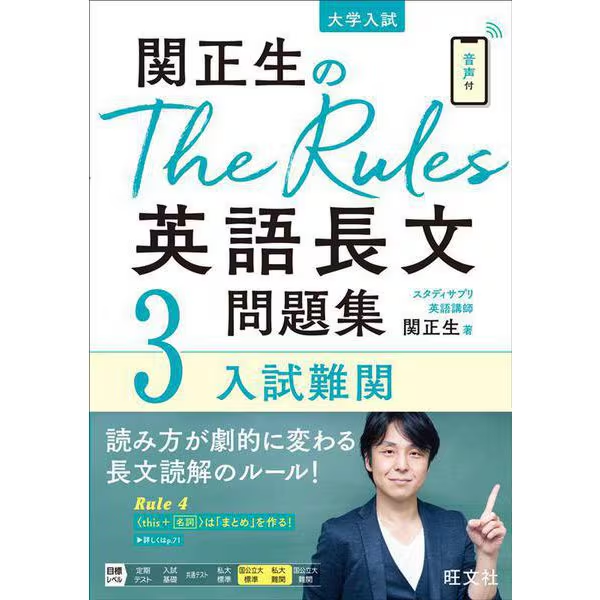
まずご紹介するのは『関正生のThe Rules英語長文問題集3です。こちらはレベル別で4冊に分かれており、旧帝大、早慶レベル(偏差値~65)では、『関正生のThe Rules英語長文問題集3』に取り組むことをお勧めします。
②<インプット編>『パラグラフリーディングのストラテジー①』
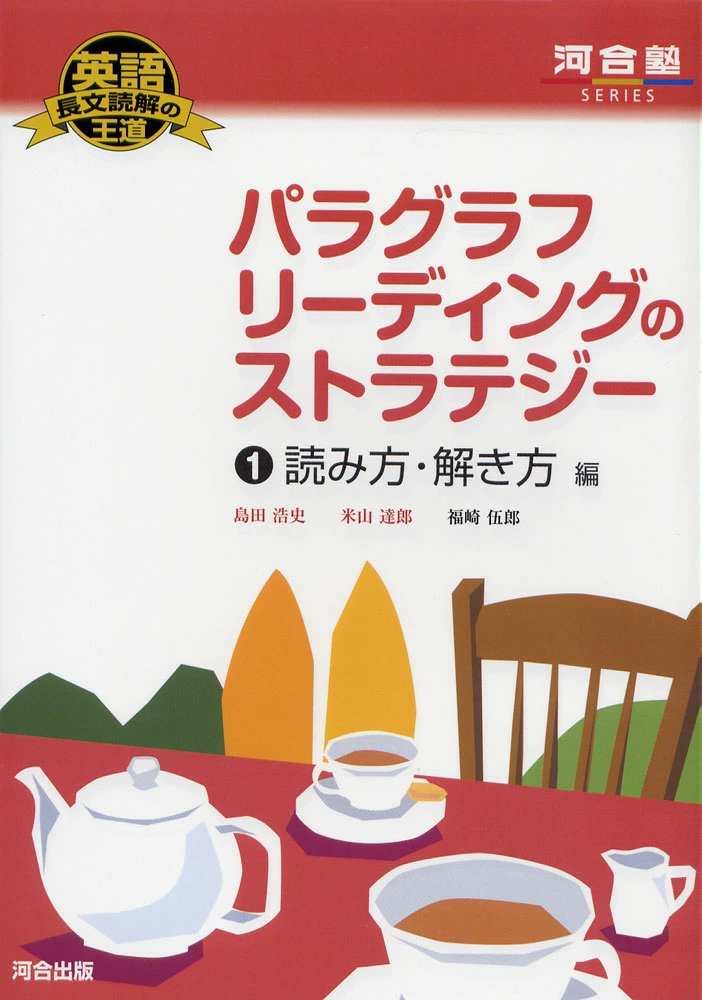
次に紹介するのは、『パラグラフリーディングのストラテジー①』です。
このシリーズは、志望校によって以下のように分かれています。
①読み方・解き方編
②実践編:私立大対策
③実践編:国公立大対策
①読み方・解き方編は、私立大・国公立大共通の長文の読み方を学ぶことができるため、どの大学を志望する方も読んでほしい一冊です。
こちらのシリーズは、文章の論理的展開がどのようになっているのかや、難単語の類推の仕方など、入試問題を解く上で必要な方法論が載っています。
例えば、第1パラグラフの次の第2パラグラフの先頭にHoweverがついている場合、第1パラグラフの内容とは反対のものがくるという事が分かります。
その後、英文解釈のアウトプットを兼ねて英語長文問題集に入っていくことができます。
英語長文は、難易度が上がれば上がるほど構文が複雑になります。
構文が取れなかった場合、必ず英文解釈の参考書に戻って復習し、再度構文を取り直してみましょう!
『関正生のThe Rules英語長文問題集』シリーズが、全文構文解説がついており、早く正確に長文を読み解く訓練をする問題集であるのに対し、『パラグラフリーディングのストラテジー』シリーズは、部分的に未知な箇所があったとしても、主張を捉え論理的に正解を導けることを伝える参考書となっています。
③<アウトプット編>『パラグラフリーディングのストラテジー②』
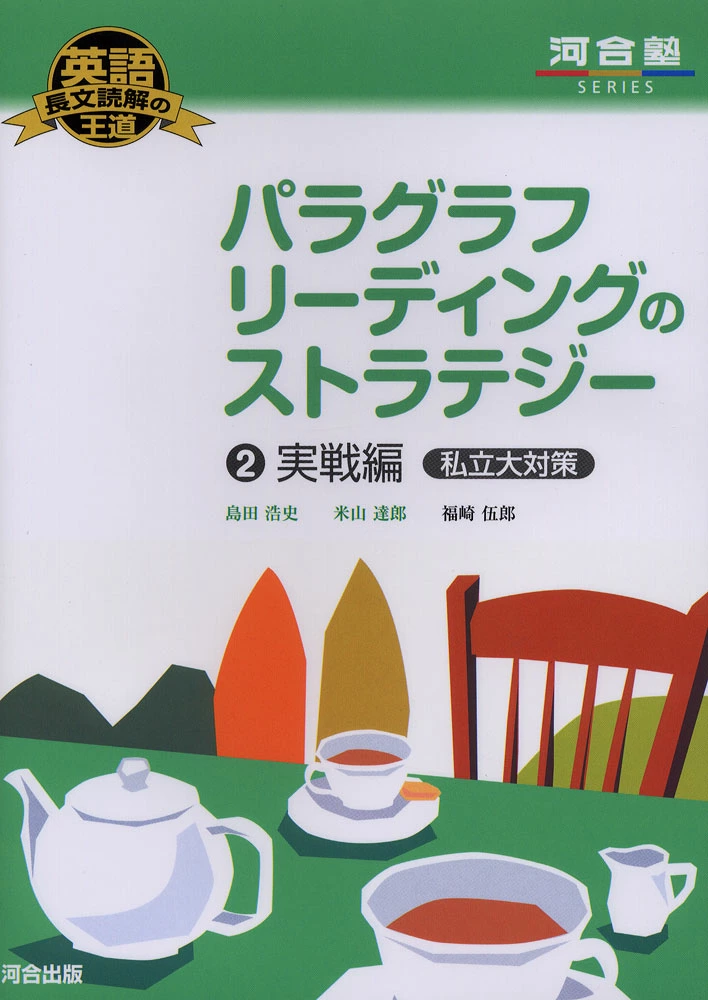
次にご紹介するのは、『パラグラフリーディングのストラテジー②』です。
こちらは、参考書として珍しいことに、『パラグラフリーディングのストラテジー①』の読み方と解き方と並行して問題演習をこなせる参考書となっています。
問題演習では『パラグラフリーディングのストラテジー①』で学んだ読み方と解き方が最後まで忠実に再現されており、再現性のある解法を身に付けることができます。
早慶など、難関私立大を受ける方は取り組むべき参考書です。
③<アウトプット編>『関正生の英語長文ポラリス3』
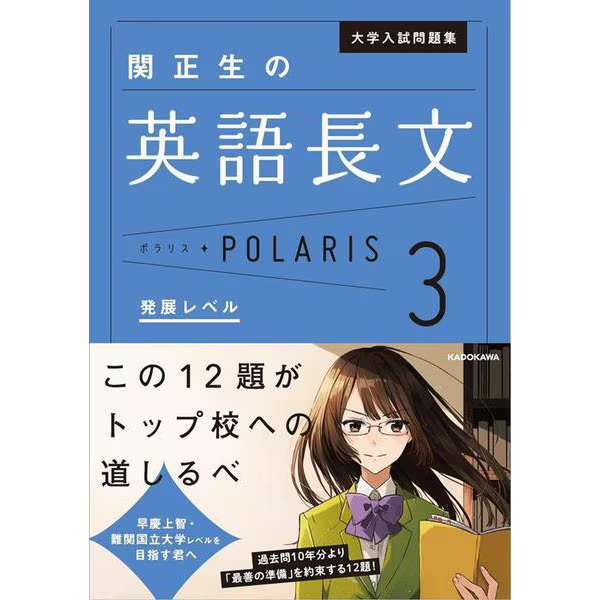
2冊目は『関正生の英語長文ポラリス3』をご紹介します!
レベル別で分かれているので、自分に適したレベルを選ぶようにしましょう。
『関正生の英語長文ポラリス1(標準)』:日東駒専・産近甲龍レベル
『関正生の英語長文ポラリス2(応用)』:GMARCH・関関同立・難関国公立レベル
『関正生の英語長文ポラリス3(発展)』:旧帝・早慶・東京一科レベル
旧帝大、早慶、東京一科レベル(偏差値~70)の場合は、『関正生の英語長文ポラリス3』で問題演習を重ねましょう!
学習戦略
このレベルでは、盤石な読解力を前提に、極めて長く抽象度の高い文章を処理し、文章の核心を掴んで誤った選択肢がどのように違うのかを言語化するまでが必要になります。
- 【STEP 1. <アウトプット>最難関レベルの読解戦略を身につける】
- まずは『関正生のThe Rules英語長文問題集3』と『パラグラフリーディングのストラテジー①』を使い、文章全体の構成や、一見繋がって見えない文同士の関係性(言い換え・対比・因果など)を見抜く、高度な読解法をインプットします。
- 【STEP 2. <アウトプット>『関正生の英語長文ポラリス3』『関正生の英語長文ポラリス4』と『パラグラフリーディングのストラテジー②』、志望校の過去問で問題演習を積む】
- 次に志望校の過去問に取り組み、STEP1.で学んだ戦略を総動員して、時間内に合格点を取る演習を行います。
- 『関正生の英語長文ポラリス3』は、過去問だけでは不足しがちな演習量を補い、様々なテーマの文章に触れるために活用します。
- 『パラグラフリーディングのストラテジー①』で学んだ内容は、『パラグラフリーディングのストラテジー②』でアウトプットし、定着率を高めます。
- 【STEP 3. <弱点補強>解答の根拠を言語化する】
- 復習の際、「なぜこの選択肢が正解で、他の選択肢はどこが、どのように違うのか」を、他人に授業できるレベルまで言語化するトレーニングを行います。
- このプロセスを通じて、解答の根拠が曖昧な部分がなくなり、どんな難問にも自信を持って答えられるようになります。
④東京一科レベル(偏差値~70)
🔹 最難関大レベルを目指し、共通テスト9割以上を狙いたい人
🔹 最難関大二次試験で合格点を取れるようにする
おすすめ参考書
①<インプット編>『関正生のThe Rules英語長文問題集4』
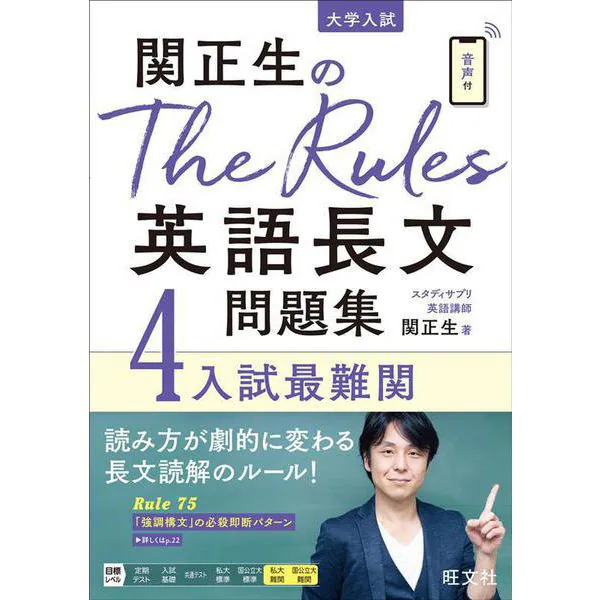
まずご紹介するのは『関正生のThe Rules英語長文問題集4』です。こちらはレベル別で4冊に分かれており、旧帝大、早慶、東京一科レベル(偏差値~70)では、『関正生のThe Rules英語長文問題集4』に取り組むことをお勧めします。
②<インプット編>『パラグラフリーディングのストラテジー①』
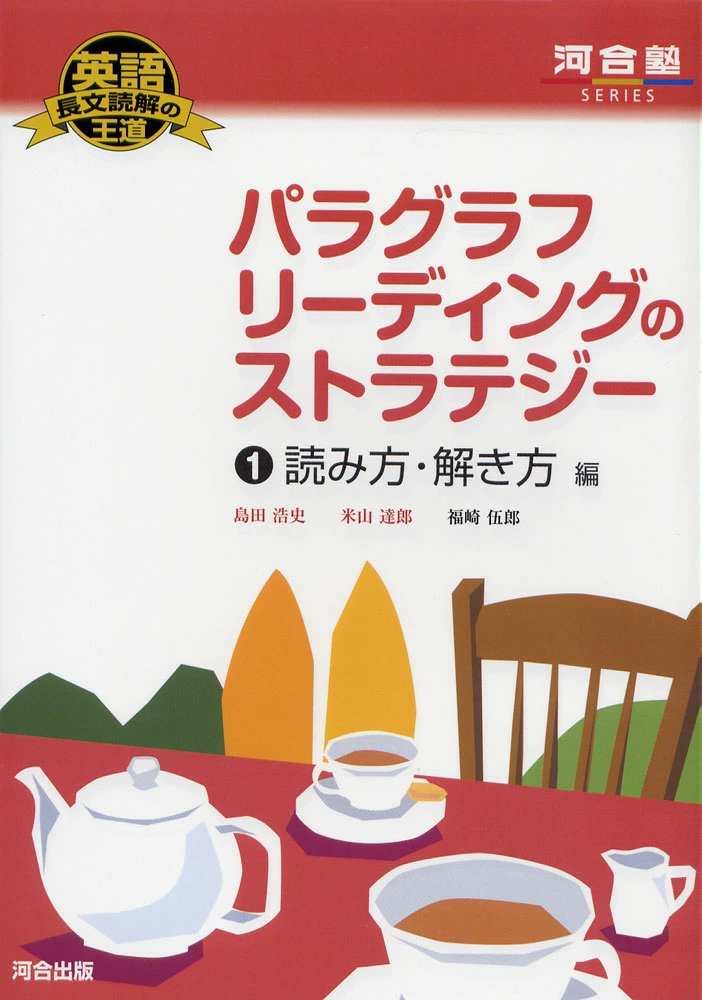
次に紹介するのは、『パラグラフリーディングのストラテジー①』です。
このシリーズは、志望校によって以下のように分かれています。
①読み方・解き方編
②実践編:私立大対策
③実践編:国公立大対策
①読み方・解き方編は、私立大・国公立大共通の長文の読み方を学ぶことができるため、どの大学を志望する方も読んでほしい一冊です。
こちらのシリーズは、文章の論理的展開がどのようになっているのかや、難単語の類推の仕方など、入試問題を解く上で必要な方法論が載っています。
例えば、第1パラグラフの次の第2パラグラフの先頭にHoweverがついている場合、第1パラグラフの内容とは反対のものがくるという事が分かります。
その後、英文解釈のアウトプットを兼ねて英語長文問題集に入っていくことができます。
英語長文は、難易度が上がれば上がるほど構文が複雑になります。
構文が取れなかった場合、必ず英文解釈の参考書に戻って復習し、再度構文を取り直してみましょう!
『関正生のThe Rules英語長文問題集』シリーズが、全文構文解説がついており、早く正確に長文を読み解く訓練をする問題集であるのに対し、『パラグラフリーディングのストラテジー』シリーズは、部分的に未知な箇所があったとしても、主張を捉え論理的に正解を導けることを伝える参考書となっています。
③<アウトプット編>『パラグラフリーディングのストラテジー③』

アウトプット編としてまずご紹介するのは、『パラグラフリーディングのストラテジー③』です。
こちらは、参考書として珍しいことに、『パラグラフリーディングのストラテジー①』の読み方と解き方と並行して問題演習をこなせる参考書となっています。
問題演習では『パラグラフリーディングのストラテジー①』で学んだ読み方と解き方が最後まで忠実に再現されており、再現性のある解法を身に付けることができます。
つまり、インプットした内容をアウトプットを通じて効率良く身につけることができます。
こちらの『パラグラフリーディングのストラテジー③』は、国公立大対策に特化した内容になっており、最難関国公立を目指す方にはぜひ取り組んでいただきたい一冊です。
④<アウトプット編>『関正生の英語長文ポラリス3』
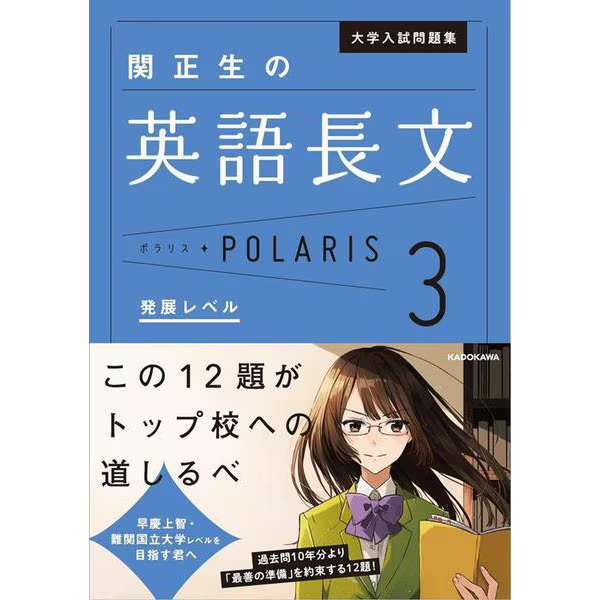
次に『関正生の英語長文ポラリス3』をご紹介します!
レベル別で分かれているので、自分に適したレベルを選ぶようにしましょう。
『関正生の英語長文ポラリス1(標準)』:日東駒専・産近甲龍レベル
『関正生の英語長文ポラリス2(応用)』:GMARCH・関関同立・難関国公立レベル
『関正生の英語長文ポラリス3(発展)』:旧帝・早慶、東京一科レベル
『関正生の英語長文ポラリス3』は難関国公立の問題も掲載されているため、東京一科を志望する方にもおすすめの参考書です。
学習戦略
このレベルでは、盤石な読解力を前提に、極めて長く抽象度の高い文章を処理し、制限時間内に自分の言葉で再構築する「表現力」までが問われます。
- 【STEP 1. <アウトプット>最難関レベルの読解戦略を身につける】
- 『関正生のThe Rules英語長文問題集4』で、要約・和訳といった特殊設問の「解法ルール」を学び、採点基準を意識した答案作成術を身につけましょう。また、『パラグラフリーディングのストラテジー①』で読み方のルールを学びます。
- 【STEP 2. <アウトプット>『関正生の英語長文ポラリス3』と『パラグラフリーディングのストラテジー③』、志望校の過去問で問題演習を積む】
- 次に志望校の過去問に取り組み、STEP1.で学んだ戦略を総動員して、時間内に合格点を取る演習を行います。
- 『関正生の英語長文ポラリス3』は、過去問だけでは不足しがちな演習量を補い、様々なテーマの文章に触れるために活用します。
- 『パラグラフリーディングのストラテジー③』で演習することによって、『パラグラフリーディングのストラテジー①』で学んだ内容を定着させます。
- 【STEP 3. <弱点補強>解答根拠の言語化と添削で、答案を完成させる】
- 東京一科の英語長文問題では、要約や和訳・説明問題の解答が重要になります。復習の際は、必ず学校の先生や塾の講師など第三者に添削してもらいましょう。客観的な視点を得ることで、自分では気づけない減点ポイントをなくし、答案を合格レベルへと磨き上げます。
- 第三者の添削に加え、自分でも参考書の解説を参考にして添削できるようにしましょう。
まとめ
長文読解は、大学受験英語における最大の得点源となる重要なステップです。
あなたに合った一冊から始めよう
あなたの現在の学力レベルに合わせて、最適な参考書から学習を始めましょう。
- 英語が苦手な方は、『関正生のThe Rules英語長文問題集1』でインプットして『関正生の英語長文ポラリス1』でアウトプット
- 基礎固めには『関正生のThe Rules英語長文問題集2』と『パラグラフリーディングのストラテジー①』でインプットして『関正生の英語長文ポラリス2』でアウトプット
- 応用力強化には『関正生のThe Rules英語長文問題集3』と『パラグラフリーディングのストラテジー①』でインプットして『パラグラフリーディングのストラテジー②』『関正生の英語長文ポラリス3』と過去問でアウトプット
- 発展力育成には、『関正生のThe Rules英語長文問題集4』『パラグラフリーディングのストラテジー①』でインプットし、『パラグラフリーディングのストラテジー③』『関正生の英語長文ポラリス3』と過去問でアウトプット
それぞれで、「インプット」「アウトプット」「反復学習」という3つのステップを丁寧に実践することが、長文読解攻略の最短ルートです。
プロのサポート
もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。
あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。
監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博
開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。
現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。
「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。
YouTubeチャンネル・Twitterのご紹介