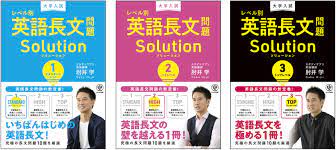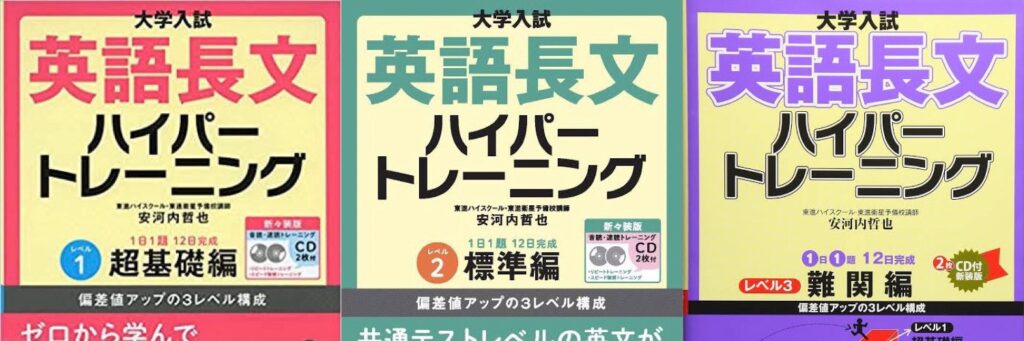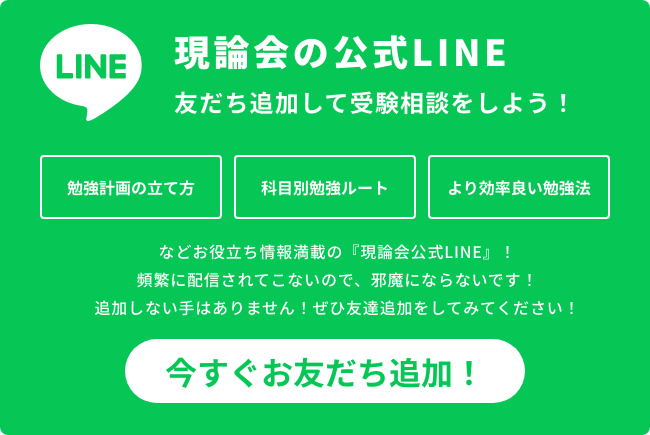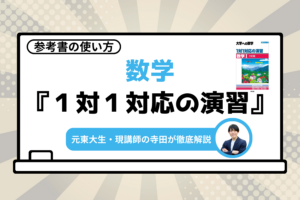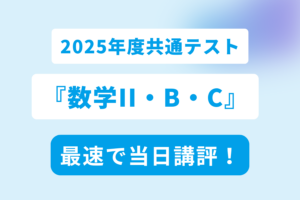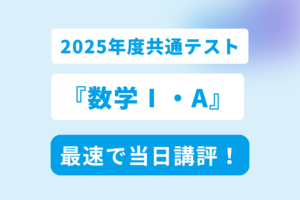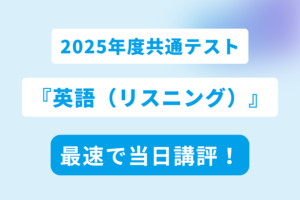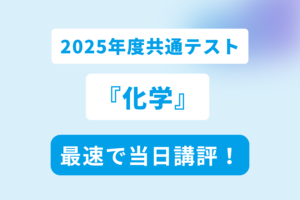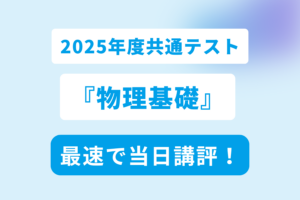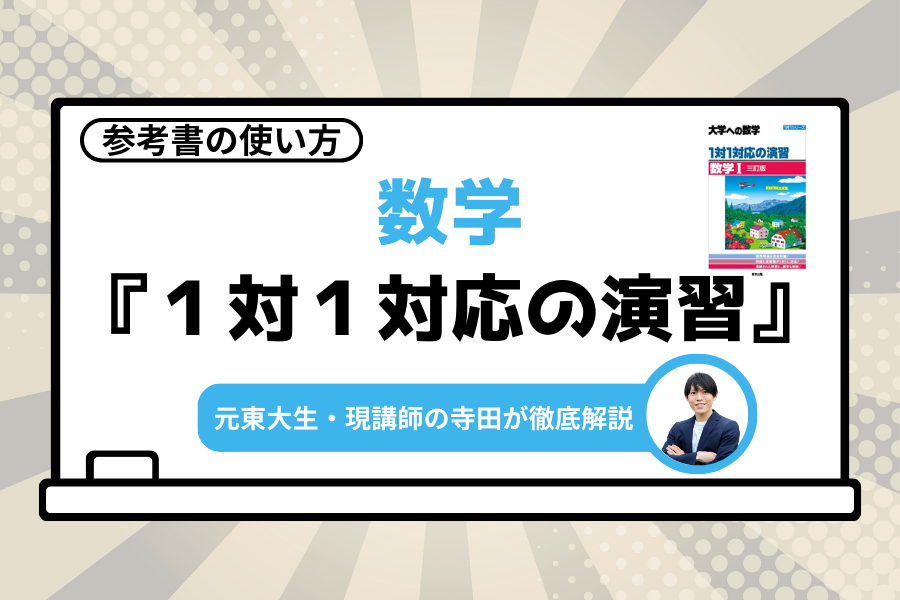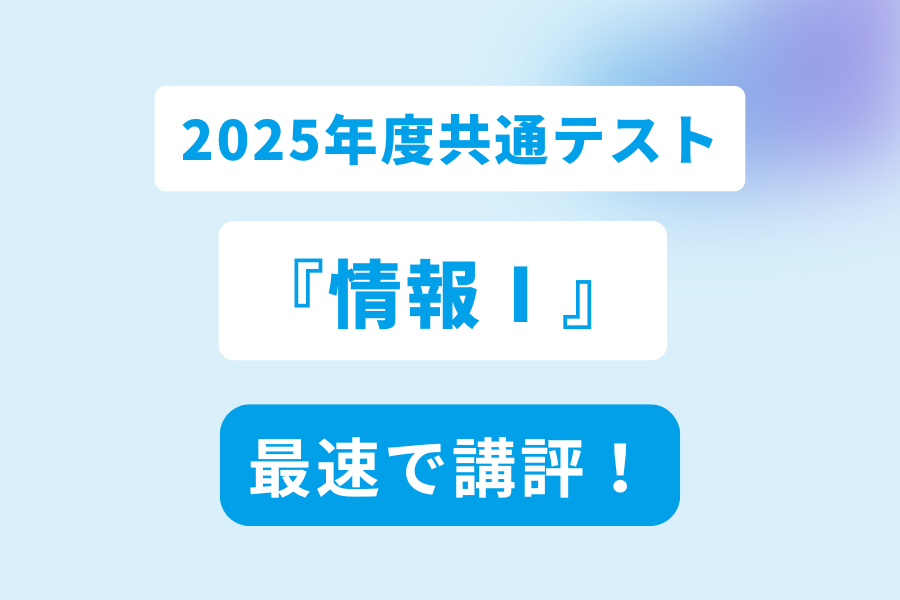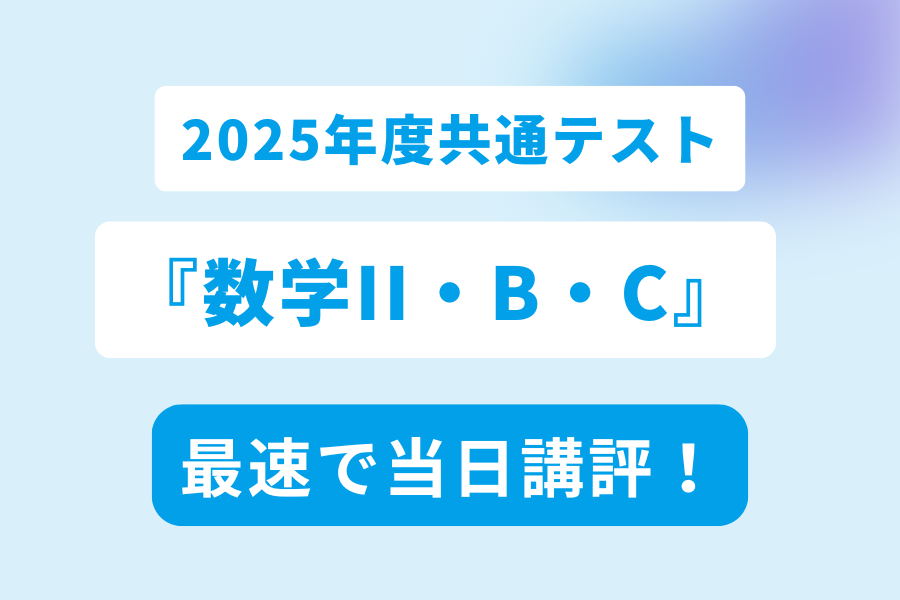『パラグラフリーディングのストラテジー』の使い方と特徴【決定版】【英語長文対策】
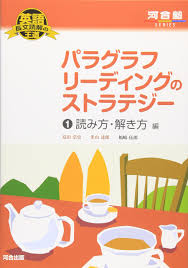
今回は『パラグラフリーディングのストラテジー』という参考書を取り上げていきたいと思います。
有名な参考書ですが、「実際いつにやるの?」「どういう人に向いているの?」
実はこの参考書なんですが、実際に長文が読めるようになったと大評判なんです。
ですので是非皆さんにも実際使っていただいて英語力をアップしてください。
・使い方とやる時期がわかる
・対応できる志望校のレベルがわかる
・この参考書で身に付く英語力がわかる
英語の勉強法についてまだ知らないという方はこちらの記事も参考にしてみてください!
『パラグラフリーディングのストラテジー』をお勧めしたい受験生

『パラグラフリーディングのストラテジー』をお勧めしたい受験生は「英語長文初心者の方」です!
- 単語・文法・解釈はやったのに長文が読めない
- 長文の答えを勘で答えてしまっている
- 返り読みが多すぎて結局時間が足りない
このような受験生にお勧めしたい参考書となっております!
英語長文のなかで筆者の主張を掴んで根拠を持って解答できるようなりたい受験生が使うことをお勧めします。
『パラグラフリーディングのストラテジー』の特徴
役割別の三冊
『パラグラフリーディングのストラテジー』には役割別で三冊あります。①の「読み方・解き方編」で勉強した後に自分の進路に合わせて②実践編「私立大対策」もしくは③実践編「国公立対策」で演習していってください。シリーズを通して読み方・解き方〜演習までできる参考書になっています。
『パラグラフリーディングのストラテジー』は「読み方・解き方」編から!
パラグラフリーディングを学べる
この参考書最大の特徴といえるのがこの「パラグラフリーディング」です。
「パラグラフリーディング」とは、段落ごとに要旨をつかんで、先の展開を予想しながら読む読み方です。これを学ぶと、枝葉末節を省き要旨をとらえることで話の全体像を素早く理解し、短時間でスムーズな読解ができるようになります。文章の100%の理解を目指すのではなく、現在持ち合わせている単語や解釈の知識でくみ取れる文意の量を最大化する力を養成するのが目的の参考書です。
「パラグラフリーディング」で短時間でスムーズな読解ができるようになろう!
論理展開を学べる
主張がどこによく現れやすいのかといった傾向や頻出の論理展開パターン(抽象➡具体・対比⇔逆説、原因⇄結果の因果関係)を学ぶことができます。
また、その論理展開に基づいたわからない単語の推測方法、指示語・言い換え・省略よる反復回避のパターンを知ることができ、各段落の論理展開のまとめ方などがしっかり説明されている参考書になっています。
論理展開のパターンや推測方法を学習し、英語長文を得意にしよう!
実践的な方法論の明記
下線部和訳、空欄補充、並べ替えなど多くの問題が扱われており、総合的な長文読解のノウハウが紹介されています。また、文章量が多い中、短時間で重要な部分を読み主張をしっかりと掴む方法論とその情報をもとに論理的に記号問題を解いていくためのトレーニング方法も紹介されています。どんな英文が出ても、「パラグラフリーディング」に沿った減点されない答案づくりを行えるように丁寧に解説されていることもこの参考書の特徴です。
実践的な読み方・解き方を学んで根拠を持って解答できるようになろう
『パラグラフリーディングのストラテジー』で対応できる志望校レベル
①読み方・解き方編
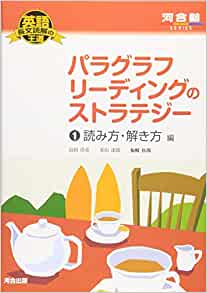
こちらは英語長文の読み方と解き方なので「全ての志望校に対応」します。
②私立大対策編
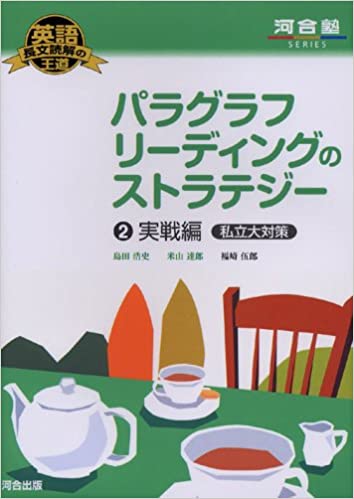
難易度は偏差値60突破向けでしょう。レベルは有名私大から早慶の難関大まで幅広く扱っています。レベルが徐々に上がっていく参考書になっているので幅広く私立大学の問題を演習していくことができます。
③国公立大対策編
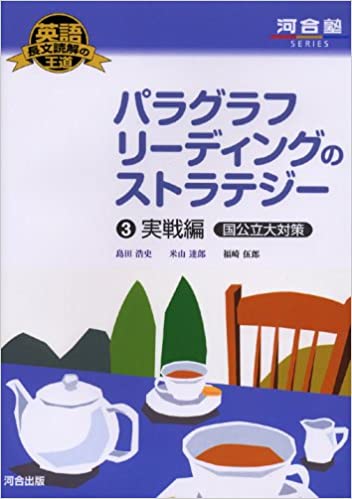
難易度は同じく偏差値60突破向けでしょう。
「国公立大対策」は記述や和訳など、国公立大対策に特化しているだけでなく、基本的な問題も取り扱いがあります。私立大編を終えた後取り組めばにさらなるレベルアップも可能です。
どちらをどのように取り組むかは自分の志望校に合わせて取り組んでください。
「パラグラフリーディングのストラテジー」は長文読解の一冊目に有効
『パラグラフリーディングのストラテジー』の使い方

注意点を守って使いましょう!
必ず一冊目からやる
長文が苦手な人はこんな特徴をもっています。「文は訳せるのに文章全体で何言ってるかわからない!」
これを解決してくれるのが「読み方・解き方編」です。
しっかり「読み方・解き方」を学び、それを「私立大対策編」と「国公立大対策編」で実践していけるようにしましょう。
読み方・解き方編
ここでは「パラグラフリーディングの基本ストラテジー」「長文問題の解法ストラテジー」「論理マーカーの働き」を学びます。覚えるところは覚えながらしっかり読み込みましょう。
英文の読み方・解き方の解法ストラテジーを学ぶ
まずは英文を読み、問題に解答を自己流の戦略で取り組んでください。
その後解説を読み、自分のやり方と照らし合わせてみてください。
おそらく多くの受験生が「論理的に英語長文を読む・問題を解くということは、こういう感覚なのか!」ということを実感することができるでしょう。これがパラグラフリーディングの基本ストラテジーを学ぶ際に一番効果的な使い方です。
論理マーカーは一気に覚える
英文を読み、解説を読んで基本的なフォームを学んだ後はその表現などをまとめたものと「パラグラフリーディング」のやり方を具体的に学んでいきます。この表現が来たら、「対比(+譲歩➡主張)/具体/言い換え/追加/因果」のどれになるかが見てわかるレベルまで暗記してください。この参考書は1周した後に、長文を解くたびにこの参考書で出来ないストラテジーのポイントを確認して行く作業を繰り返してその都度暗記するようにしてください。
私立大・国公立大対策編
これら二つは演習用ですが、あくまで『パラグラフリーディングのストラテジー1』のやり方を実践的に練習するためものと活用してください。
問題を解く
まずは問題を解いてください。ここで意識すべきことは『パラグラフリーディングのストラテジー1』で勉強した読み方と解き方を実践的に活用することです。
実際に使うことで自分自身の力にし、使いこなせるようになることが目的です。本番同様の意識で問題に取り組み絶対に空欄は作らないようにしましょう。復習の際に自分はどこが弱点かを発見するためにも熟考するようにしてください。
解説を読む
解説では読み方と解き方が詳細に書かれているのでまずは熟読しましょう。
ここで注意したいことは、「なぜそのように読めるか」「なぜそのように解くのか」という視点を持つことです。
根拠をもって解けるようになるために、パラグラフリーディング解説やリーズニングやマーキングなどの論理的な解説を長文問題演習や過去問演習で再現できるようになるまで時間をかけて復習を重ねましょう。
音読
解説を熟読した後、どのような参考書でも行って欲しいことそれが「音読」です。
論理マーカーや文章の流れを掴むことはあくまでテクニックであり、実際の英語力とは少し違います。「パラグラフリーディング」は基礎的な単語・文法・解釈力あってこそです。目の前の文章が一番理解できているこの段階での音読は英語力向上に直結します。英語を英語のまま理解する脳【英語脳】を作るため、また実践的にパラグラフリーディングを使いこなすためにも是非「音読」を実践してください。
『パラグラフリーディングのストラテジー』この時期に使う
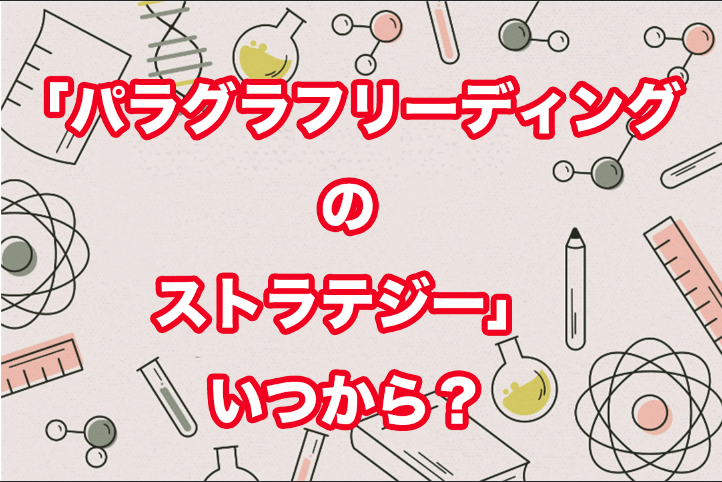

『パラグラフリーディングのストラテジー』は英文解釈の勉強が固まってすぐ!!
英文解釈の勉強終了後すぐ
「英文解釈」が終わってからになります。各英文のSVOCが把握でき、一通りの意味で確定させることを英文解釈といいます。これを一通り学習したら長文の読み方を一冊目で学び、二冊目と三冊目でさらに演習をつんでいきましょう。
具体的な時期
『パラグラフリーディングのストラテジー』を使う具体的な時期は、最低9月初めには一冊目に。
10月中旬には演習編が終了が目安です。
理由としては、受験勉強の時期的な個人差の部分もありますが、過去問演習を10月末もしくは11月初めから取り組むことを目指すのが理想だからです。
『パラグラフリーディングのストラテジー』と合わせて使いたい参考書
『パラグラフリーディングのストラテジー』を使った後にオススメの参考書としては肘井先生の『solution』や安河内先生の『英語長文ハイパートレーニング』関先生の『英語長文ポラリス』があります!
solution
英語長文ハイパートレーニング
英語長文ポラリス
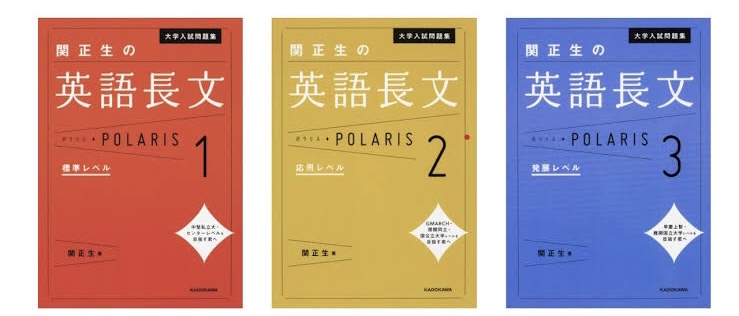
なぜかというと、この3つはレベル別に演習ができるので自分にあった問題だけを解くことが可能だからです!先述したとおり、『パラグラフリーディングのストラテジー』は幅広く私大対策ができますが、この3つは志望校のレベル別に事細かく構文解析や解説を行っており、演習用教材として長けています。過去問演習で効果を発揮させたい方は『パラグラフリーディングのストラテジー』に取り組んだ後に、『solution』『英語長文ハイパートレーニング』『英語長文ポラリス』のいずれかをすることをオススメします。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回のまとめです。『パラグラフリーディングのストラテジー』は「英文解釈」が終了後必ず一冊目から取り組んでください。
また、論理マーカーをしっかり暗記し、長文で確認しつつ復習の際は音読で英語脳をつくることを意識してみてください。
するとみなさんも英語長文の演習の勉強に弾みがつくでしょう!また『パラグラフリーディングのストラテジー』で学んだことを過去問演習で最大限の効果を発揮されるように、『solution』『英語長文ハイパートレーニング』『英語長文ポラリス』のいずれかで演習を積んでみてください!
YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介