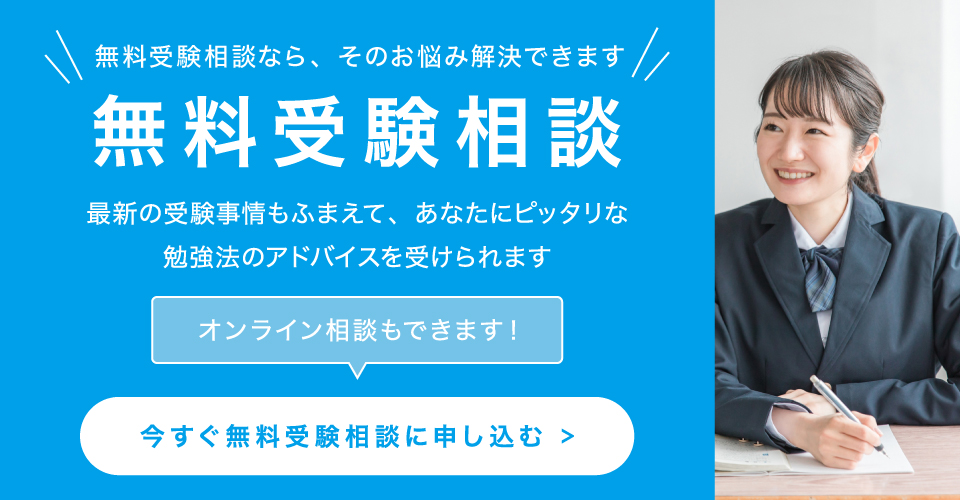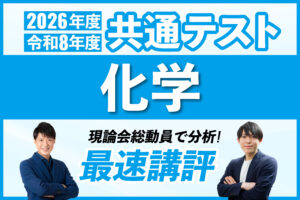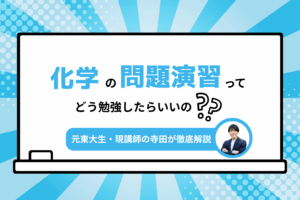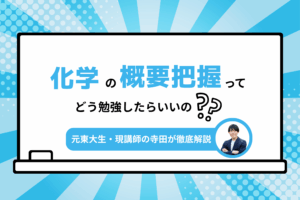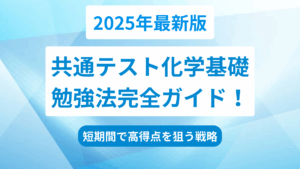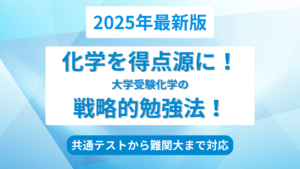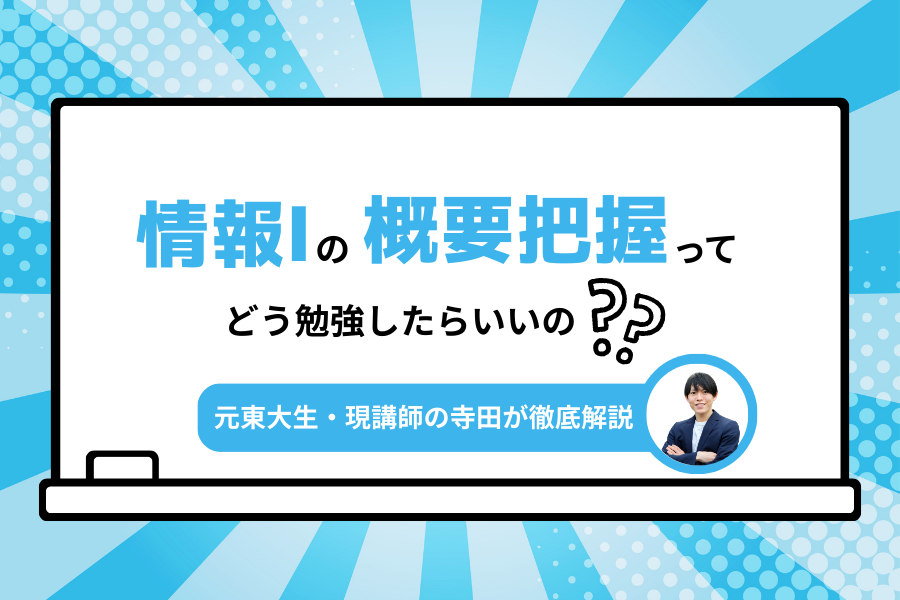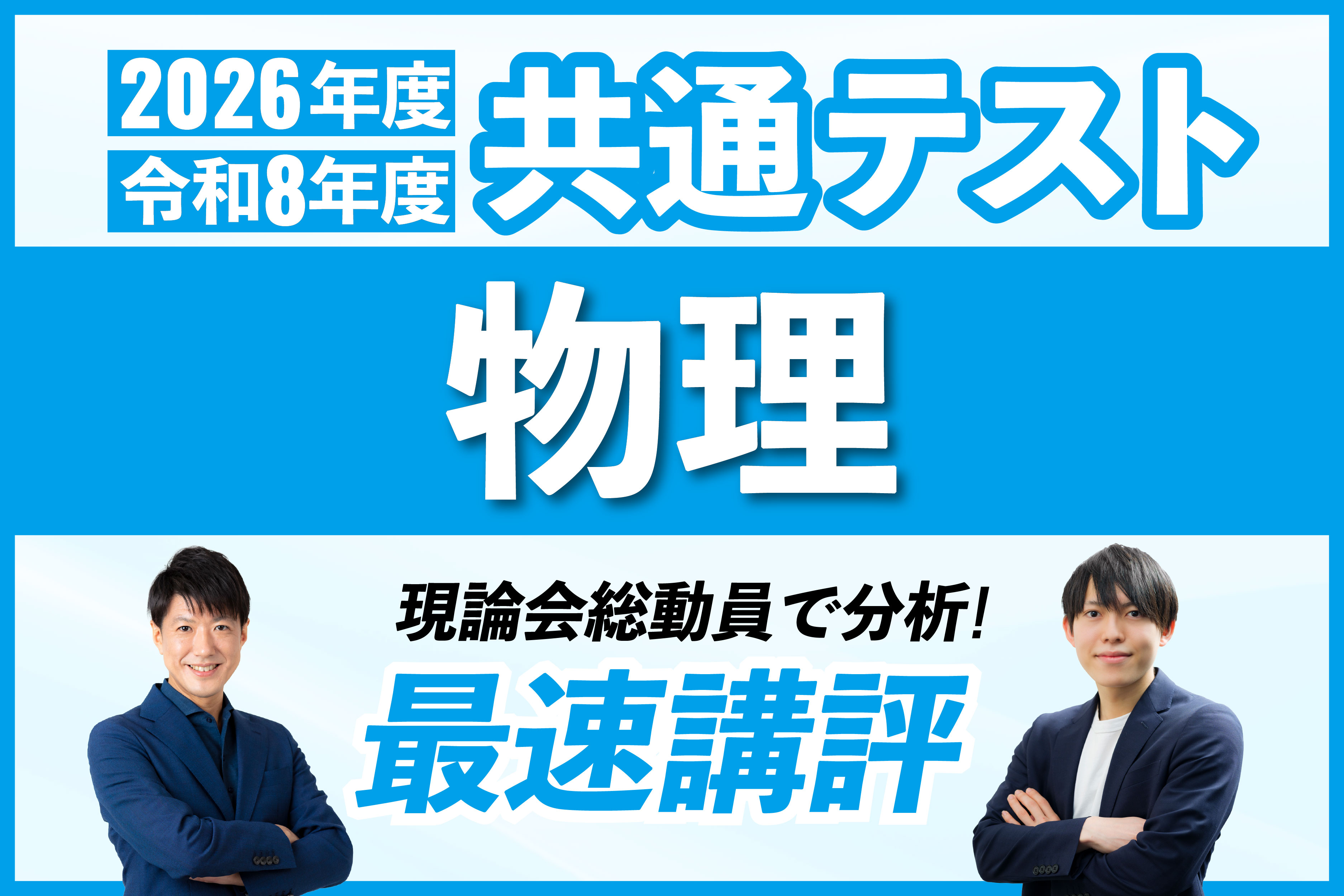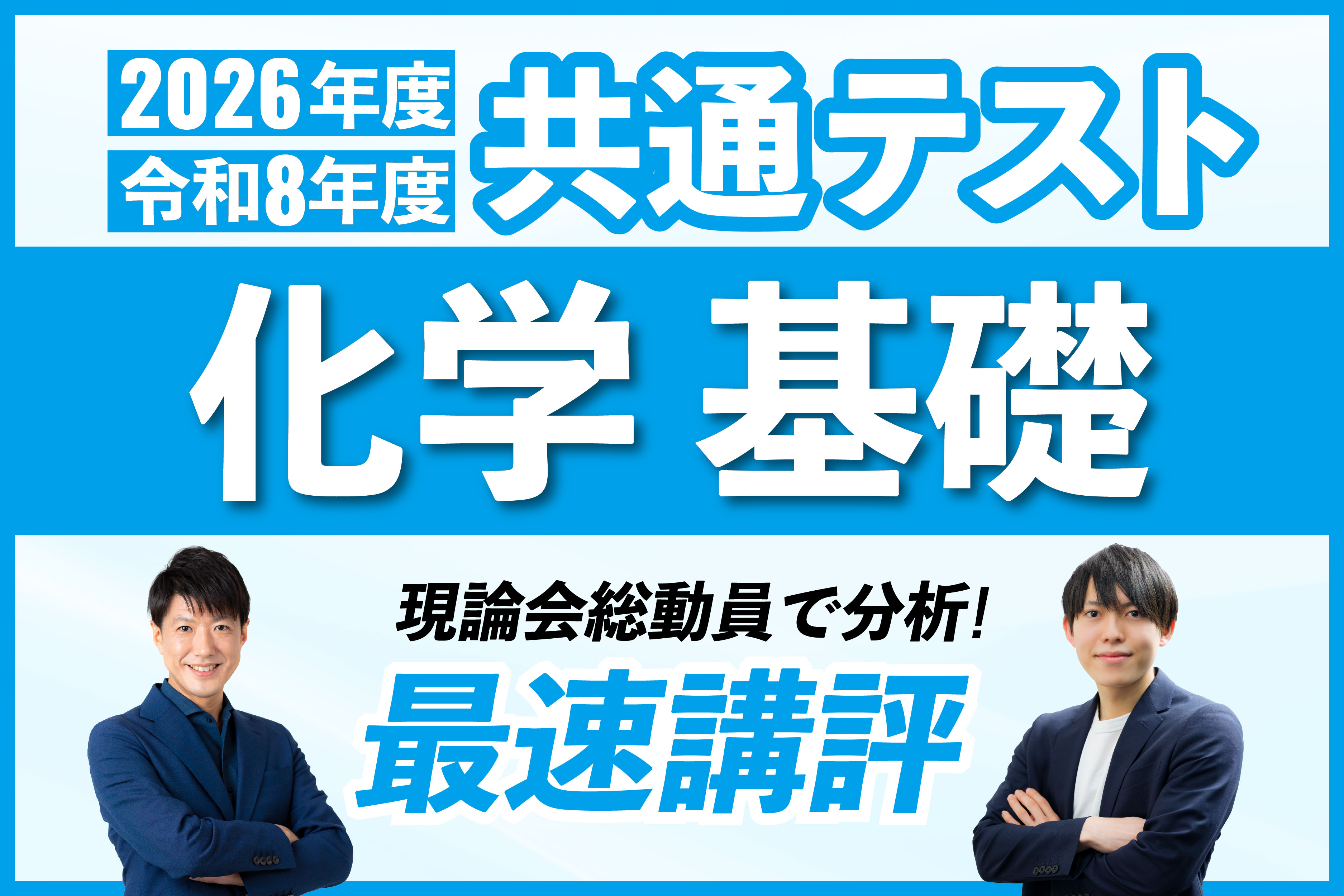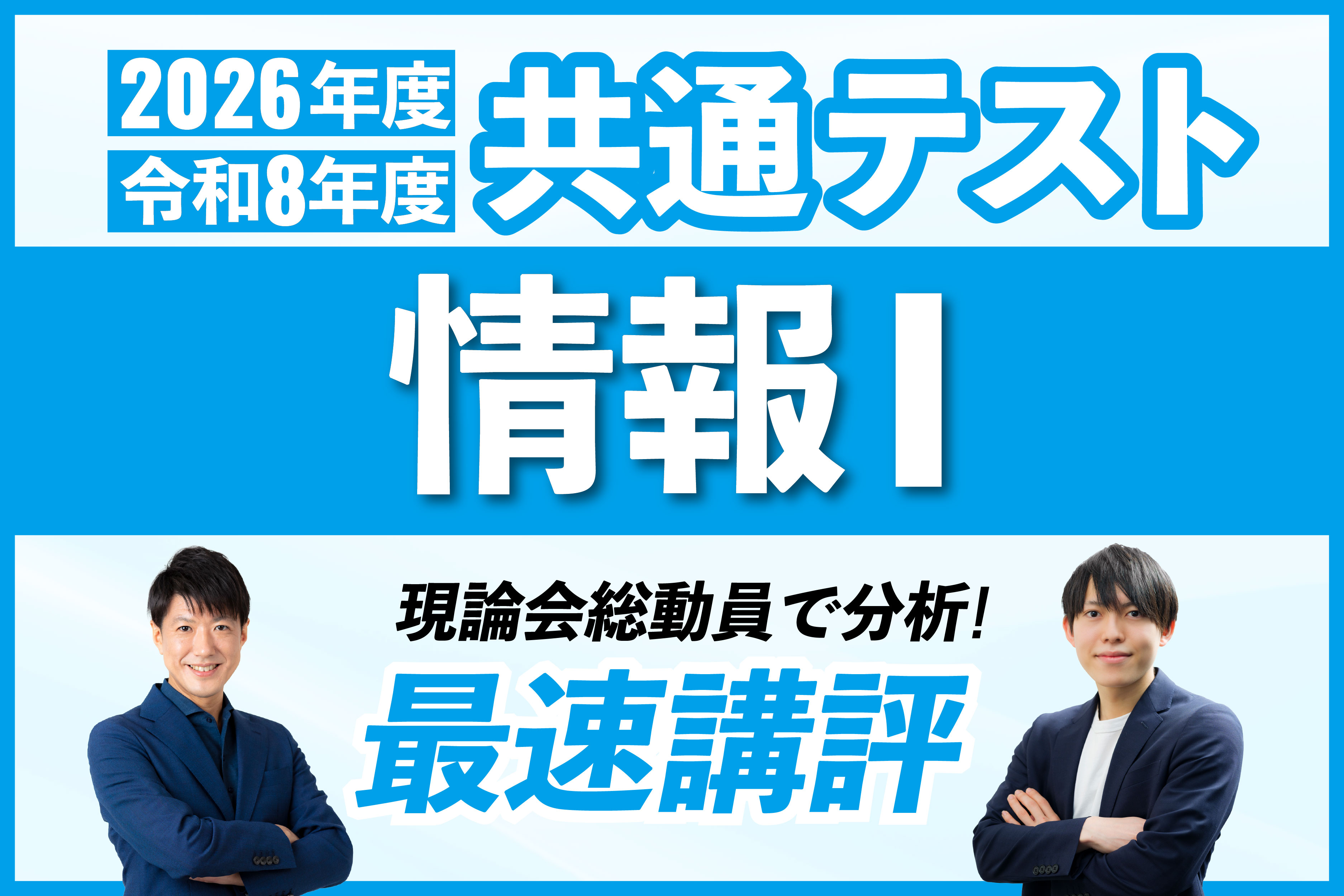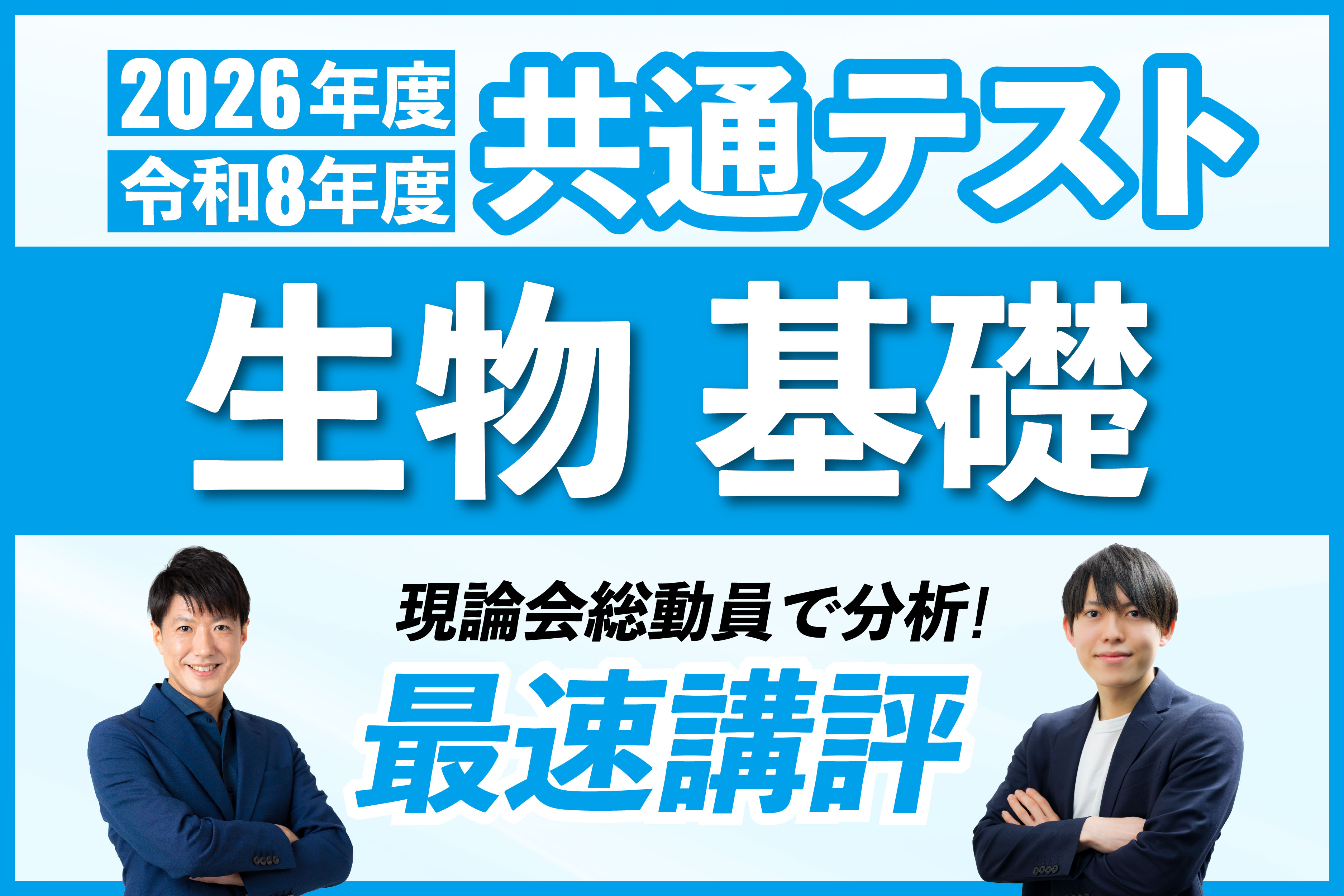化学の概要把握を攻略!【暗記と論理の土台を築く勉強法】
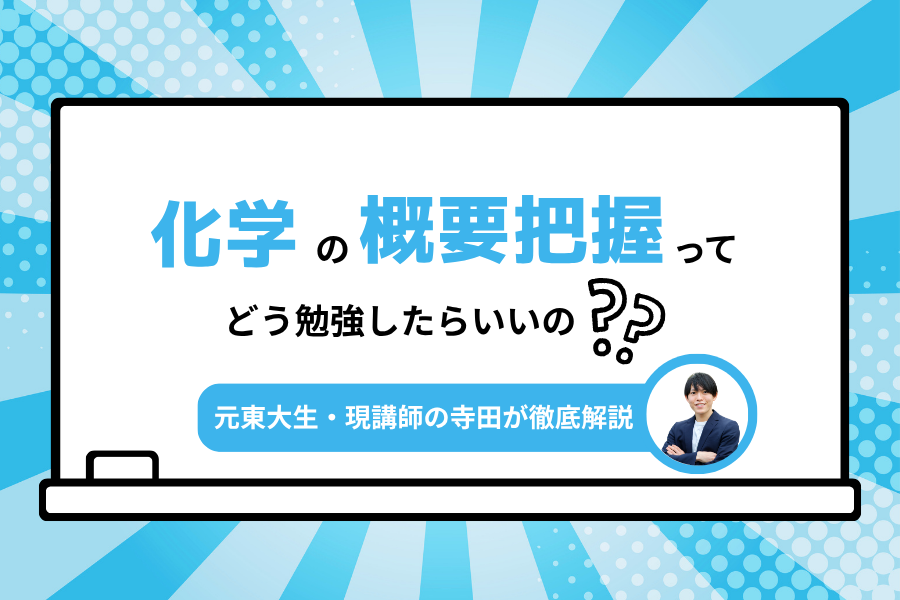

ここでは、化学の学習の第一歩である「概要把握」の全体像と具体的な勉強法、そしてこの段階に最適な参考書について解説します!!
このサイトでは以下の内容を詳しく解説していきます。
- 概要把握の全体像と具体的な勉強方法
- 概要把握に適した参考書や問題集
- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略
また、概要把握を勉強する前に、化学の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!
化学の勉強法の詳しい情報についてはこちら
概要把握の攻略法
概要把握とは?

化学の勉強法は「概要把握」「問題演習」「分野別対策」「過去問演習」という段階に分類できます。
概要把握
教科書に書かれている内容を一通り理解し、各分野の基本知識を習得することを目指します。 問題演習に進むための土台を固める段階です。
問題演習
要把握で身につけた知識をもとに、実戦的な問題演習に取り組みます。 公式の使い方や計算手順、頻出パターンなどを定着させ、得点に直結する力を磨いていきます。
分野別対策
志望校の出題傾向に合わせて、無機・有機・理論などの特定分野を重点的に強化していきます。
過去問演習
過去問に十分な分量で取り組み、出題形式への慣れと本番での立ち回りを完成させていきます。 合格に必要な得点力を仕上げていく段階です。
概要把握とは、高校化学で習う「理論化学」「無機化学」「有機化学」の全単元を一通り理解する段階です。この段階のゴールは、教科書の例題レベルの知識と基本的な反応式を理解し、次のステップに進むための「地図」を作ることです。

後の学習との関係:この段階を疎かにすると、後の問題演習で「この反応式は何だ?」「この法則は何に使われる?」と、知識の前提でつまずくことになります。
概要把握を学ぶ3つのメリット

化学の概要把握は、単なる暗記ではありません。論理的思考力と記憶力を両立させるための重要なステップです!
1.「なぜ?」がわかるから暗記量が減る
化学は暗記が多いと思われがちですが、実際は多くの反応や性質が原子の構造や電気的な性質といった一つの原理で説明できます。概要把握の段階でこの「原理」を理解することで、単なる丸暗記ではなく、論理的に記憶できるようになり、結果的に覚える量が大幅に減ります。
2.理論・無機・有機のつながりが見える
化学の各分野は独立しているように見えて、実は密接に繋がっています。(例:理論化学の「酸と塩基」の知識は、有機化学や無機化学の反応で必須)。概要把握で全ての単元に触れることで、各分野の知識がどこで結びつくかという学習の全体像が見えます。
3.計算問題への抵抗感をなくす
化学の計算問題(モル計算、平衡定数など)は、数学的な計算よりも「どの公式をいつ、どのように使うか」という化学的な判断が重要です。概要把握を通じて基本的な計算パターンに触れることで、次の問題演習段階へスムーズに移行できます。
なぜ化学は「理論→無機→有機」の順で学ぶべきか??
化学を効率よく学ぶためには、知識の依存関係に基づいた正しい順番で進めることが不可欠です。
この順序は、知識の依存関係(積み上げ)に基づいています。理論化学がすべての分野の「原理」であり「土台」となるからです。

各分野の学習手順
1. 理論化学:すべての土台(言葉と法則)
【最優先】化学のすべての土台となる原理を学びます。
- 役割:化学全体の計算規則、定義(モル、酸塩基、平衡など)、根本原理を学ぶ。
- 時期の目安:
高校2年生の夏休みまで - ゴール:
原子構造、物質量、酸と塩基など、化学全体の原理を理解し、計算の基礎を固める。
この知識がないと、他の分野の現象が「なぜそうなるのか」理解できず、丸暗記に頼らざるを得なくなります。化学計算のスキルもここで習得します。
2. 無機化学:理論の知識を応用する場
理論化学で学んだ「酸と塩基」「酸化還元」などの原理を応用して、各物質の反応や性質を理解します。
- 役割:元素の反応や性質を学ぶ。
- 時期の目安:
高校2年生の冬休みまで - ゴール:
理論化学(酸塩基、酸化還元)の原理を応用し、代表的な反応や性質を理解する。
無機化学で出てくる多くの反応(酸化還元、沈殿、気体発生など)は、理論化学で学ぶ原理(酸塩基、イオン化傾向など)を具体的な物質に当てはめた応用例です。先に理論を理解しておくことで、暗記量が大幅に削減できます。
3. 有機化学:最後に時間をかけて攻略する応用分野
理論・無機とは独立性が高いですが、最後の知識整理として取り組みます
- 役割:炭素化合物の構造、反応、合成を学ぶ。
- 時期の目安:
高校3年生の春休みまで - ゴール:
官能基の構造や反応の基本を理解し、構造決定の基礎力を身につける。
他の分野からの知識の依存度が比較的低いため、後回しにしても学習に支障が出にくいです。その分、最難関大入試で差がつきやすい複雑な構造決定や合成問題に、まとまった時間を確保してじっくり取り組むことができます。
結論:化学は原理から応用へと進む「積み上げ型」の科目です。 土台となる理論化学を盤石にすることが、効率的な学習の鍵です。
この段階で陥りがちな3つの失敗
- 【失敗1】:無機・有機を丸暗記しようとする:原理を理解せずにただ暗記しようとすると、すぐに忘れます。理論化学の土台の上に知識を積み重ねてください。
- 【失敗2】:複雑な計算問題で立ち止まる:概要把握のゴールは「解法の理解」です。複雑な計算は後の問題演習に回し、解法のパターン理解を優先しましょう。
- 【失敗3】: 知識の整理を怠る:用語や反応式を覚えたつもりになっても、すぐに忘れます。白紙に書き出すなど、必ずアウトプットして定着させましょう。
この土台が盤石であれば、その後の問題演習は飛躍的に効率が上がります。
概要把握の勉強法

次に具体的な「概要把握」の勉強法を紹介します。特に、暗記と計算のバランスを意識して進めましょう。
STEP 1.【原理理解】講義系参考書で精読する
まずは、教科書や講義系参考書の本文、図、表をすべて読み込み、各単元の定義を理解します。特に、「なぜその法則が成り立つのか」という原理や、「この反応が起こる理由」といった背景知識に重点を置いて理解します。
STEP 2.【知識定着】教科書で定義を確認・整理する
講義系参考書で理解した後、学校の教科書に戻り、定義されている用語や例題を再確認します。入試は教科書準拠が原則なので、この段階で知識の基準を明確にしておきます。
STEP 3.【再現練習】例題を自分で解き切る
教科書の例題を、解答を見ずに自力で解き切る練習をします。ここで解けなかった問題は、知識の理解が曖昧であることを示します。計算問題でも暗記問題でも、「自分で再現できる」状態を目指しましょう。
- 【原理理解】講義系参考書で精読する
- 【知識定着】教科書で定義を確認・整理する
- 【再現練習】例題を自分で解き切る
おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

現論会でも使用している、【2025最新版】志望校レベル別おすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します。
ここでは、化学の概要把握の学習に特化した、おすすめの参考書とその効果的な使い方を、具体的な学習ステップに沿って解説します。
参考書ポジションマップ
以下のマップは、あなたの現在の学習段階と志望校レベルに応じて、どの参考書を使うべきかを示しています。基礎から発展へと順序立てて取り組むことが、化学攻略の鉄則です。

マップの活用順序:
- 導入(全員必須):まずは『宇宙一わかりやすい高校化学』で原理をざっくりと理解し、苦手意識をなくすことから始めます。
- 網羅・標準(主要科目):次に、より本格的な講義系参考書(鎌田・福間の講義)で知識を網羅し、体系化します。
- 辞書・発展(トップレベル):最後に、『化学の新研究』を辞書として活用し、最難関レベルの深い疑問や知識の補完を行います。
旧帝大、早慶レベル、GMARCH理科大、地方国公立(偏差値~65)
🔹 難関大レベルを目指し、共通テスト9割以上を狙いたい人
🔹 難関大二次試験で合格点を取れるようにする
おすすめ参考書
『宇宙一わかりやすい高校化学』

商品リンク
あわせて読みたい
学習戦略
- 【インプットの導入と原理の理解】:化学が苦手な人や初学者が、視覚的な解説を通じて原理から理解するためのメイン教材です。本文や図を読み込み、「なぜ?」を解決することに集中します。
🔹 効果的な学習戦略:
- 【STEP 1. 原理理解】講義系参考書を精読する
- まずは、『宇宙一わかりやすい高校化学』をメインに、一章ずつ丁寧に読み進めます。
- 難しい計算や複雑な理論は、完璧に解けなくても構わないので、「どんな原理で成り立っているか」をざっくりと理解することを優先します。
- 【STEP 2. 知識定着】教科書で定義を確認・整理する
- この参考書で理解した内容を、すぐに学校の教科書に戻って定義されている用語や例題と照らし合わせます。
- 【STEP 3. 再現練習】例題を自分で解き切る
- 各章の終わりに掲載されている基本例題を解く際に、この参考書を使って「解法の原理」を確認します。
- 解けなかった問題は、この参考書の該当ページに戻り、「解法の原理」を再確認してから解き直し、自分で再現できる状態を目指しましょう。
原理よりも全体的なざっくりとした理解を優先しましょう!!
おすすめ参考書
『鎌田・福間の化学の講義』



🔹 シリーズ概要:
旺文社から出版されている講義系参考書の定番で、元東進ハイスクール講師の鎌田先生(理論・有機)と福間先生(無機)が執筆しています。高校化学の全範囲を扱っており、『理論化学』『無機化学』『有機化学』の計3冊で構成されています。詳細な解説と入試の出題ポイントが明確なため、知識を体系的に網羅したい受験生に最適です。
学習戦略
- これらの参考書は、旧帝大・早慶レベルを目指す受験生が、『宇宙一わかりやすい高校化学』で得た原理の知識を、入試に必要なレベルまで深く、かつ体系的に整理するためのメイン教材です。
🔹 効果的な学習戦略:
- 【STEP 1. 原理理解】講義系参考書を精読する
- 『宇宙一わかりやすい高校化学』でざっくりと原理を掴んだ後、これらの講義を辞書的に使用します。特に原理や法則の導出過程について、なぜそうなるのかを丁寧に読み込み、理解を深めます。
- 高校化学の原理に関する疑問点をすべて解消しましょう。
- 【STEP 2. 知識定着】教科書で定義を確認・整理する
- 講義の中で覚えるべき重要な公式や定義(例:平衡定数の式、錯イオンの構造)を抜き出し、教科書と照らし合わせます。特に『福間の無機化学』では、各物質の反応式を理論の原理(酸化還元など)とセットで整理し直します。
- 知識をただ覚えるだけでなく、「理論→無機」への知識の応用を意識して整理し、体系化します。
- 【STEP 3. 再現練習】例題を自分で解き切る
- 各単元の基本例題(特に計算問題)を自力で解き、解法パターンを暗記します。解けない場合は、鎌田先生・福間先生の解説を読んで解法の「手順」を理解し、その後すぐに解答を伏せて解き直します。
- 講義系参考書に載っている基礎的な計算と知識問題の解法を、他者に説明できるレベルで習得します。
原理を常に意識することで現象に対する理解を深めましょう!!
東京一科、難関国立医学部レベル(偏差値70~)
🔹 対象: 最難関大学を志望し、合格圏内に入りたい人
🔹 目標:東京一工・医学部の二次試験で高得点を取る
おすすめ参考書
『化学の新研究』

商品リンク
学習戦略
【深い疑問の解決と知識の補完】:教科書や講義系参考書だけでは解決できない発展的な内容や、なぜそうなるのかという深い原理を調べたいときに使う「上級の参考書」です。
🔹 効果的な学習戦略:
東京一科、難関国立医学部レベルの受験生もまずは教科書や講義系参考書で理解に徹してから着手することをお勧めします。

実際、本格的に化学の新研究を読み始めるのは過去問に着手してからがおすすめになります!!
- 【全STEPを通じて 】
- 基本的には自習時に手が止まったとき、より深く原理を知りたいときのみ使用します。例えば、「なぜこの物質は水に溶けるのか?」といった疑問が生まれたときに、該当箇所を引いて知識を補完しましょう。
注意:この参考書は情報量が膨大で、本文から読み進めるのは非効率です。疑問が生じたときの辞書として活用することを推奨します。
事象の暗記ではなく根本の理解による記憶を意識しましょう!!
あわせて読みたい
各参考書の役割と効果的な活用法まとめ
| 参考書 | 対象レベル | 役割と学習戦略 |
| 『宇宙一わかりやすい高校化学』 | 全レベルの導入・初期段階 | 【導入と原理のイメージ化】 フルカラーの図解で、化学の原理や仕組みを視覚的に理解します。知識のインプットを「嫌いにならない」ための初期教材です。 |
| 『鎌田の理論化学の講義』『福間の無機化学の講義』 | 旧帝大・早慶、GMARCH、地方国公立 | 【知識の網羅と体系化】 これらが本格的な学習のメイン教材です。無機・理論に分けて、入試で必要な知識の論理的背景を深掘りし、問題を解くための知識を体系的に整理します。 |
| 『化学の新研究』 | 東京一科、難関国立医学部 | 【知識の辞書・最終確認】 難関大の入試で問われる発展的な原理や深い知識を補完するための辞書です。本文を最初から読むのではなく、問題集や過去問で疑問が出た際に、原理の源流を調べるために活用します。 |
まとめ
化学の概要把握は、論理的な理解と知識の暗記の土台を築くための、最も重要なステップです。この記事で解説したように、『宇宙一わかりやすい高校化学』で原理を理解し、『教科書』で知識を定着させるという流れを丁寧に実践することが、化学攻略の最短ルートです。
この土台が盤石であれば、その後の問題演習は飛躍的に効率が上がります。
あなたに合った一冊から始めよう
あなたの現在の学力レベルに合わせて、最適な参考書から学習を始めましょう。
- 旧帝大、早慶レベル、GMARCH理科大、地方国公立には『宇宙一わかりやすい高校化学』、『鎌田・福間の化学の講義』
- 東京一科、難関国立医学部レベル(偏差値70~)には『化学の新研究』
それぞれの参考書で、「教科書・講義系参考書を精読する」「基本的な反応式と公式を覚える」「例題を自分で再現する」という3つのステップを丁寧に実践することが、概要把握攻略の最短ルートです。
概要把握のその先へ
概要把握を完璧にしたら、次は問題演習に移りましょう。
あわせて読みたい
もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。
あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博
開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。
現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。
「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。