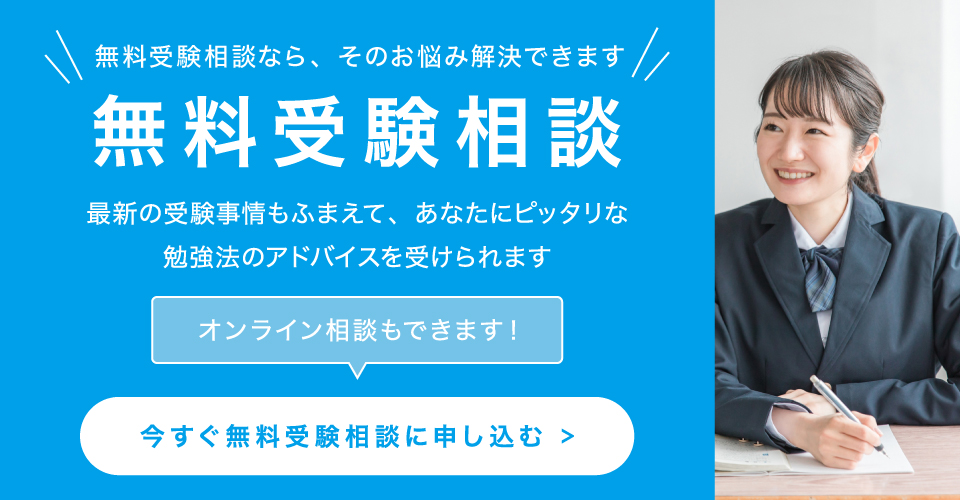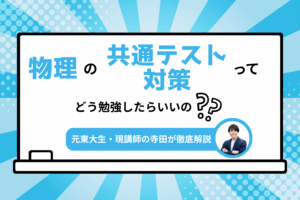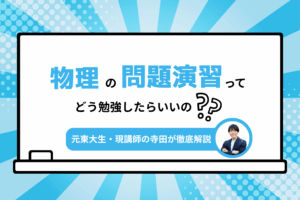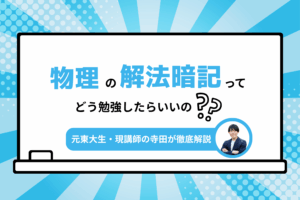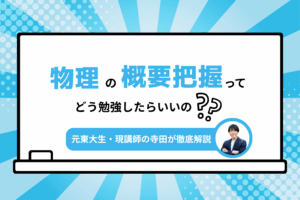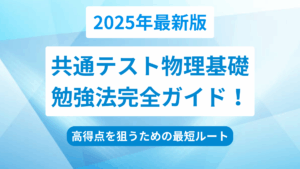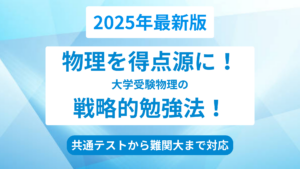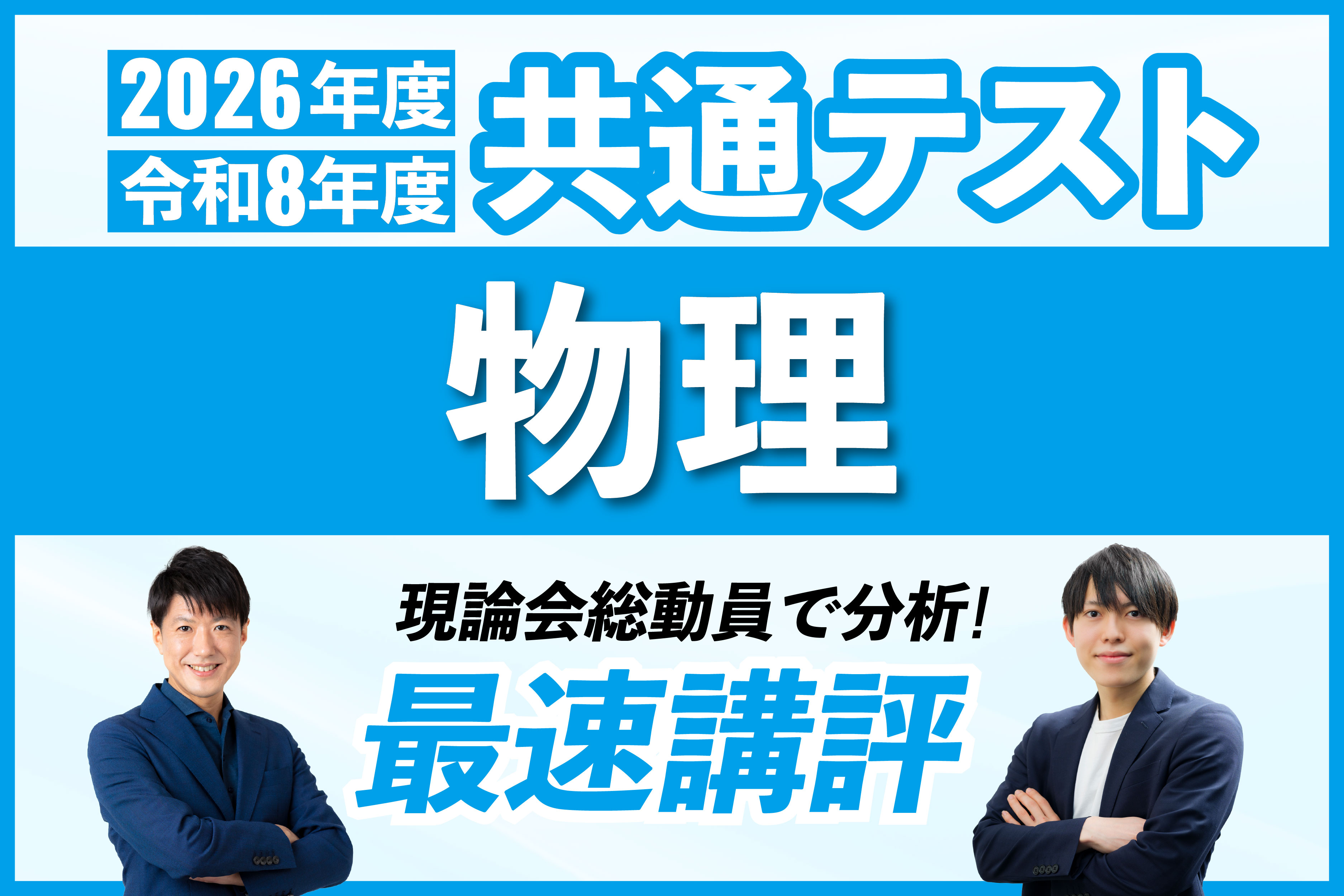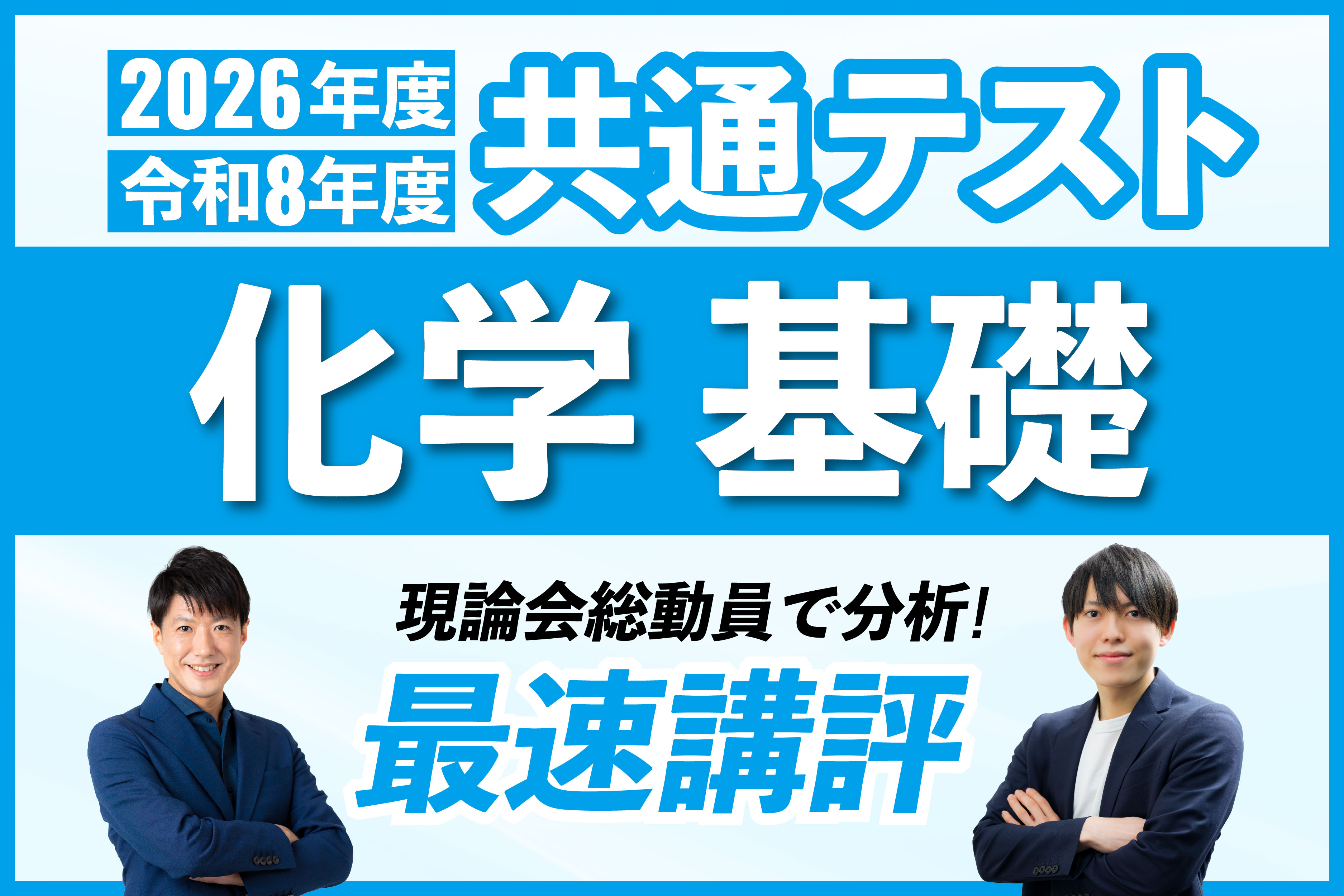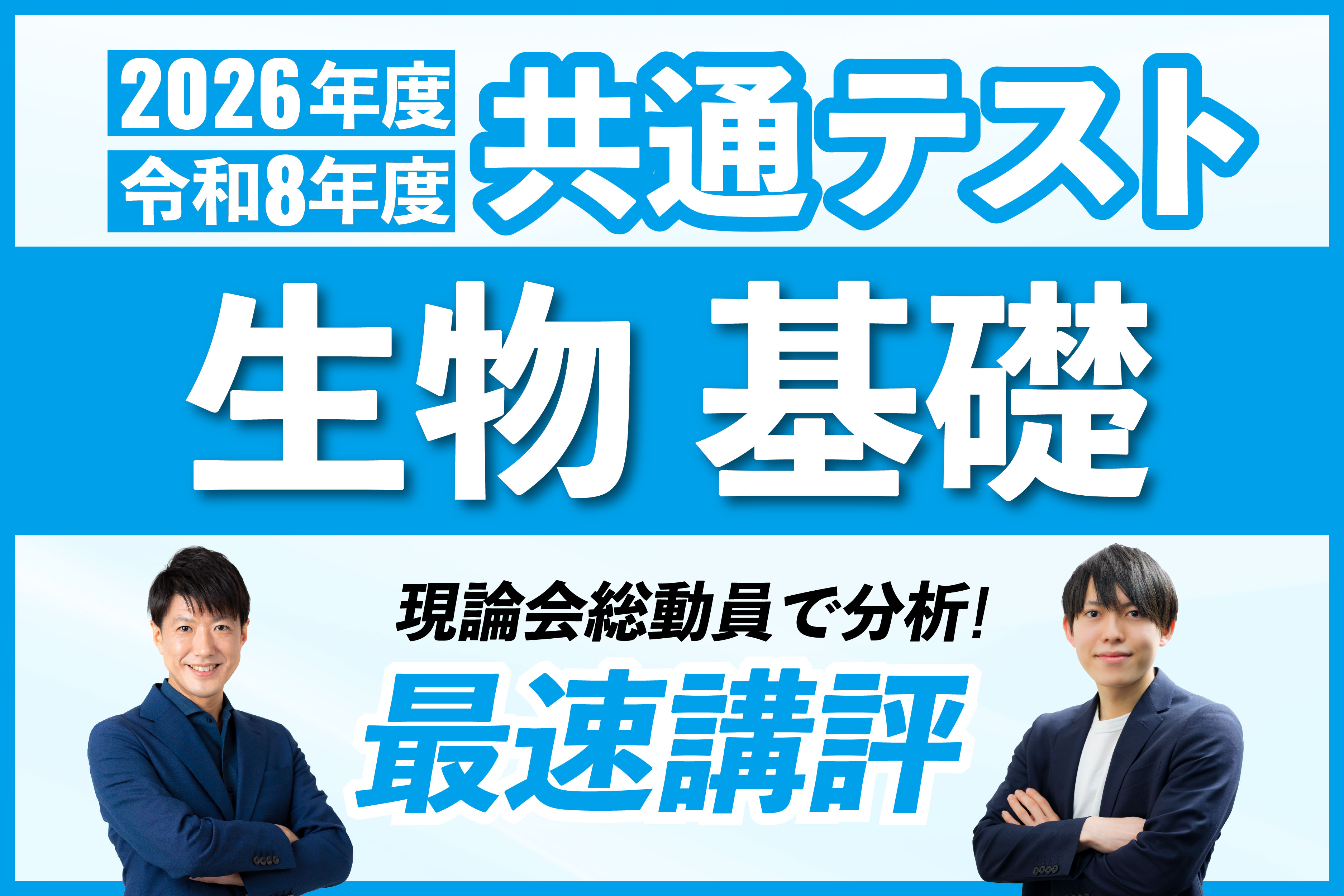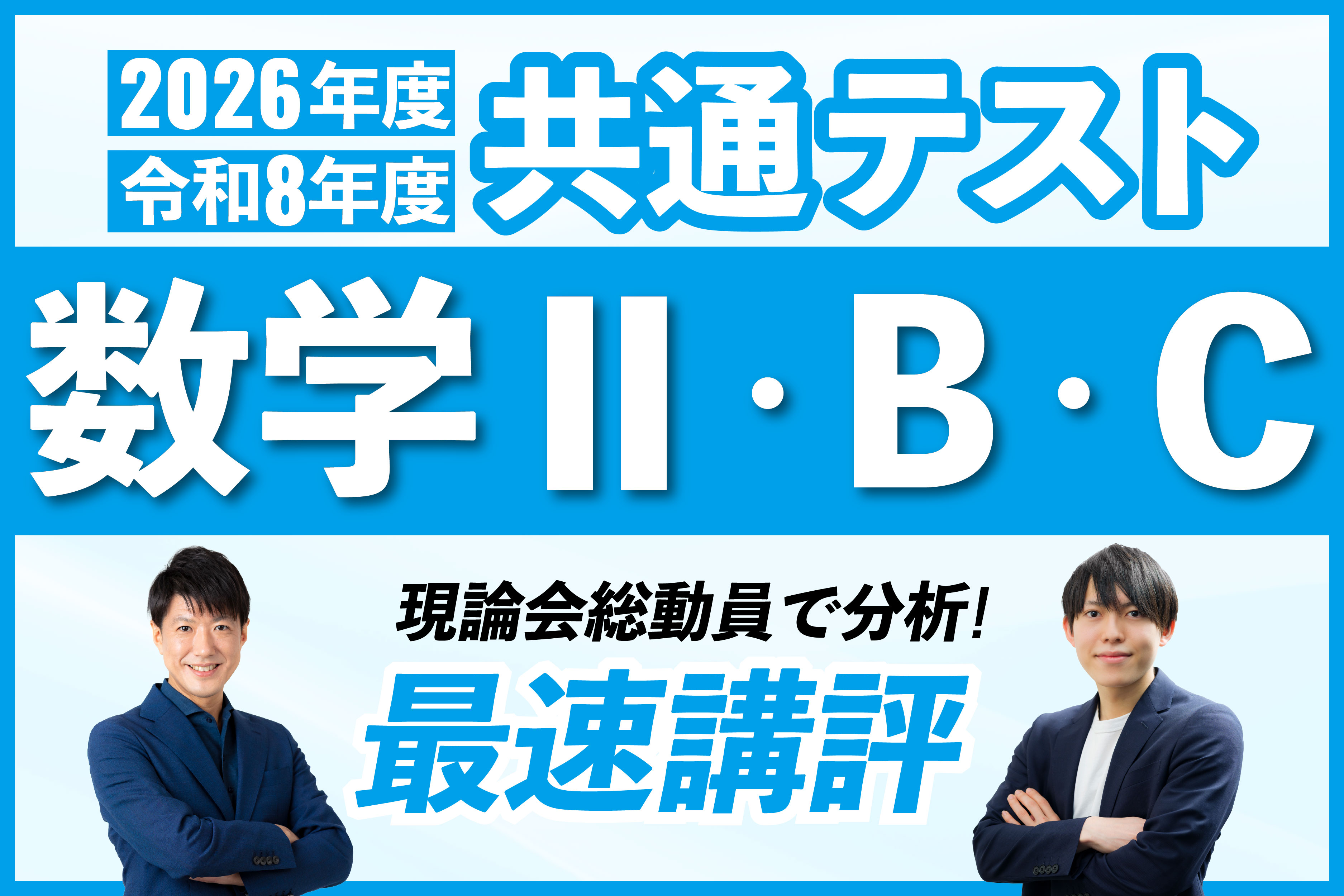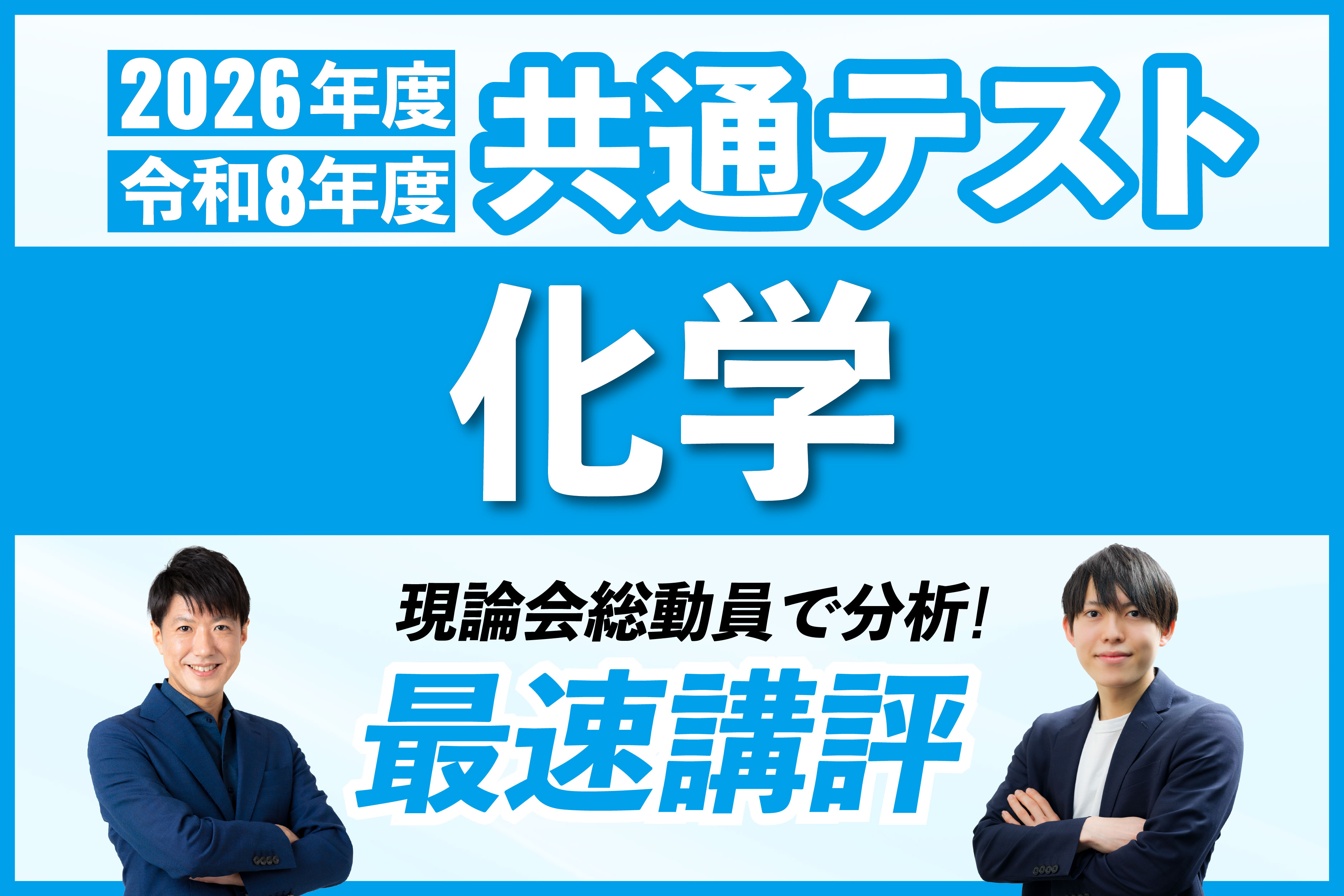【大学受験物理】問題演習の進め方とおすすめ参考書を徹底解説
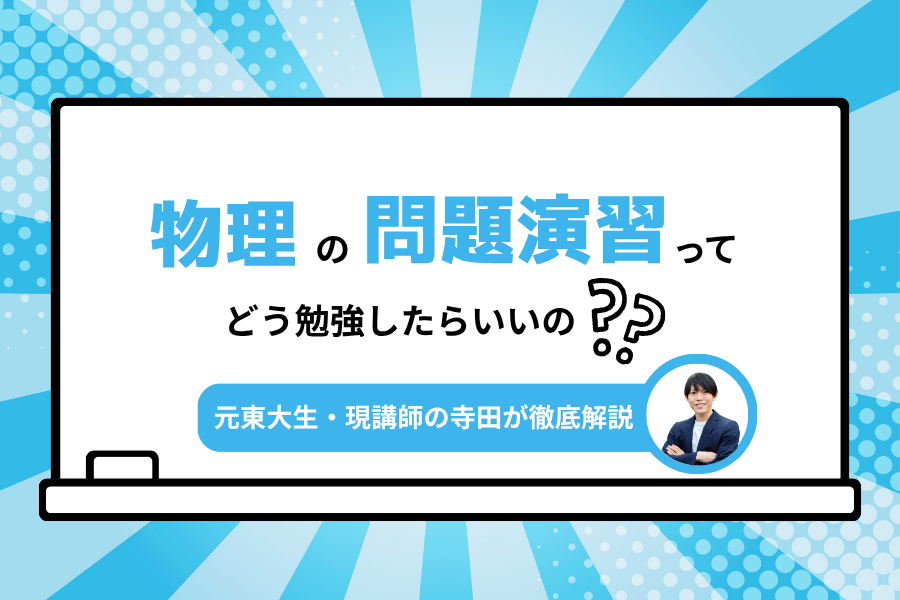

「物理の問題演習をどのように勉強を進めて良いかわからない。」
「物理の問題演習の勉強はいつの時期にすれば良いの?」
このようなお悩みに徹底的にお答えしていきたいと思います!
そしてこの記事では以下の内容を詳しく解説していきます!
- 物理の問題演習の全体像と具体的な勉強方法
- 問題演習に最適な参考書や問題集
- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略
また、物理の問題演習に取り組む前に、物理の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!
物理の勉強法の詳しい情報についてはこちら
問題演習の攻略法
問題演習とは?

物理の勉強法は「概要把握」「解法暗記」「問題演習」「過去問対策」という段階に分類できます。
概要把握
高校物理の全範囲を一通り理解する段階です。教科書や参考書にある例題レベルの問題を自力で解けるようになること、そして基本的な公式の使い方が一通り分かることを目標とします。
解法暗記
入試で出題される典型的な問題の解き方を習得する段階です。ここでは問題を見たら、使うべき公式や考え方がすぐに浮かび、手を動かせる状態を目指します。 世の中の入試問題は、これら典型的な解法を組み合わせて作られており、難関大の問題でも基本的な解法の積み重ねで対応できます。 この条件ならこの公式を使うと即答できるよう練習を重ねましょう。
問題演習
入試本番レベルの問題で合格点を取れるようにする段階です。ここでは解法暗記で身につけた典型的な解法を複数組み合わせて使う問題を中心に扱います。 単に公式や解法パターンを覚えているだけでは、実際の入試問題を解き切ることはできません。大切なのは「どの公式を使うか」「どの順番で組み合わせるか」を自分で見抜く力です。 この段階では、実際に問題を解きながら考え方の流れを身につけていきます。なぜこのアプローチを選んだのかを言語化しながら復習することで、応用問題にも対応できるようになります。
過去問対策
志望校の過去問を使い、本番で合格点を取るための実戦力を仕上げる段階です。大学ごとに出題傾向や記述量は大きく異なるため、分析して重点分野や答案の書き方を最適化しましょう。同時に、時間配分・解答順序・取捨選択・見直し方法など本番を想定した立ち回りも固めていきます。
物理の学習は、基礎から順に積み上げていくことで、最終的には入試レベルの問題にも対応できる実力を身につけられます。
問題演習の段階は、解法暗記で身につけた解法パターンを自在に使いこなせるようにするための学習段階です。ここでは、複数の解法を組み合わせて解くタイプの問題を中心に扱います。
入試問題に近い形式の問題を解くことで、過去問演習の際に必要な思考の流れや方針立ての力を養うことができます。
解法暗記の詳しい情報についてはこちら
問題演習を行う2つのメリット

問題演習の学習は、解法の組み合わせ方を学び、物理の得点力を飛躍的に高めるための重要なステップです。以下のような大きなメリットが得られます。
1.融合問題での方針を立てる力を養える
実際の入試問題は、解法暗記で学んだ典型的な解法をいくつも組み合わせて作られており、無数のバリエーションがあります。複数の考え方が絡み合った問題を読み解く力は、同じように複合的な問題を解くことでしか身につきません。
問題演習ではまさにそのような問題を扱うため、初めて見る設定に対しても解法の方針を自分で立てる力を養うことができます。最初は手が止まることもありますが、演習を重ねるうちに、どの量に注目し、どの解法を使い、どの順番で式を立てるかといった思考の流れが自然に身についていきます。
2.実戦感覚が身に付く
問題演習の特徴の一つに、典型的な解法パターンを組み合わせながら、入試に近い形式の問題で練習を重ねることがあります。
これにより、解法暗記で身につけた知識がどのように入試問題で活かされるのかを、実際の形式を通して学ぶことができます。
また、一問一問を試験問題として意識して解くことで、限られた時間の中で思考を整理する力が身につきます。時間配分や集中力のコントロールも自然と鍛えられ、得点力へとつながっていきます。
問題演習に取り組む2つのメリット
1.融合問題の方針を立てる力を養える
2.実戦感覚が身に付く
問題演習の勉強法

次に具体的な「問題演習の勉強法」について紹介します。
具体的な問題演習の進め方を3つのSTEPに沿って紹介します。効率よく実力を伸ばすために、以下のステップで演習を進めてみましょう。
STEP 1.時間を計って解く
メリットでも触れたように、この段階では入試本番に近い実戦形式の問題を扱います。解く際は必ず時間制限を設け、試験本番を意識して取り組みましょう。標準レベルの問題では10〜15分、難問では20分程度が目安です。
時間を計ることで、だらだらと解いてしまい方針立てが曖昧になることや、時間を延長し続けて達成感だけを得るといった状態を防ぐことができます。制限時間という負荷の中で方針を立て、途中計算を正確に進めることで、与えられた条件から使うべき解法を時間内に見抜く力と計算処理速度を同時に鍛えることができます。
STEP 2.自分の解答と模範解答を比較する
答え合わせの結果に一喜一憂するのではなく、自分と模範解答の差を言葉にすることが重要です。解答にどのようなな違いがあったのかを分析することで、次に同じタイプの問題に出会ったときに、より正確に方針を立てられるようになります。

特に下のようなことを意識して、比較してみましょう!
模範解答との比較で意識したいこと
・着眼点は同じか、どこに注目して方針を立てたか
・適用した公式は妥当か、条件とのずれがないか
・立式の順番は正しいか、不要な回り道をしていないか
・単位や符号の扱いは適当か
模範解答を読むだけで終わったり、式を写すだけの復習では、次に活かせる学びは得られません。
こうした気付きを言語化して整理することで、次の初見問題でも再現できる思考パターンが少しずつ構築されていきます。
STEP 3. 解法を再現し、定着させる
問題を解いたあとは、解説を熟読したうえで、何も見ずに自分の力で解答の流れを再現することを意識しましょう。単に解答を写すのではなく、どの採点項目を満たせたのか、どの部分で迷ったのか、どの解法の定着が不十分だったのかを丁寧に確認します。
この作業を通して、解法の組み合わせ方や式の導き方を自分の言葉で整理でき、知識が理解から使いこなせる段階へと変わります。
さらに、同じ問題の解き直しだけでなく、設定や形式を少し変えた類題演習にも取り組みましょう。条件を変えながら繰り返すことで、応用力と再現性の両方を高めることができます。こうした復習を重ねることで、入試本番でも安定して得点できる実戦力が身につきます。
- 時間を計って解く
- 自分の解答と模範解答を比較する
- 解法を再現し、定着させる

以上3つのステップで物理の得点力を飛躍的に伸ばせます!
おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

現論会でも使用している、おすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します!
ここでは、現論会でも実際に使用している、問題演習に特化したおすすめの問題集を紹介します。それぞれの特徴やレベル感を踏まえて解説するので、自分の到達目標や学習スタイルに合わせて、最も効果的な一冊を選びましょう。
おすすめ参考書
物理 入門問題精講
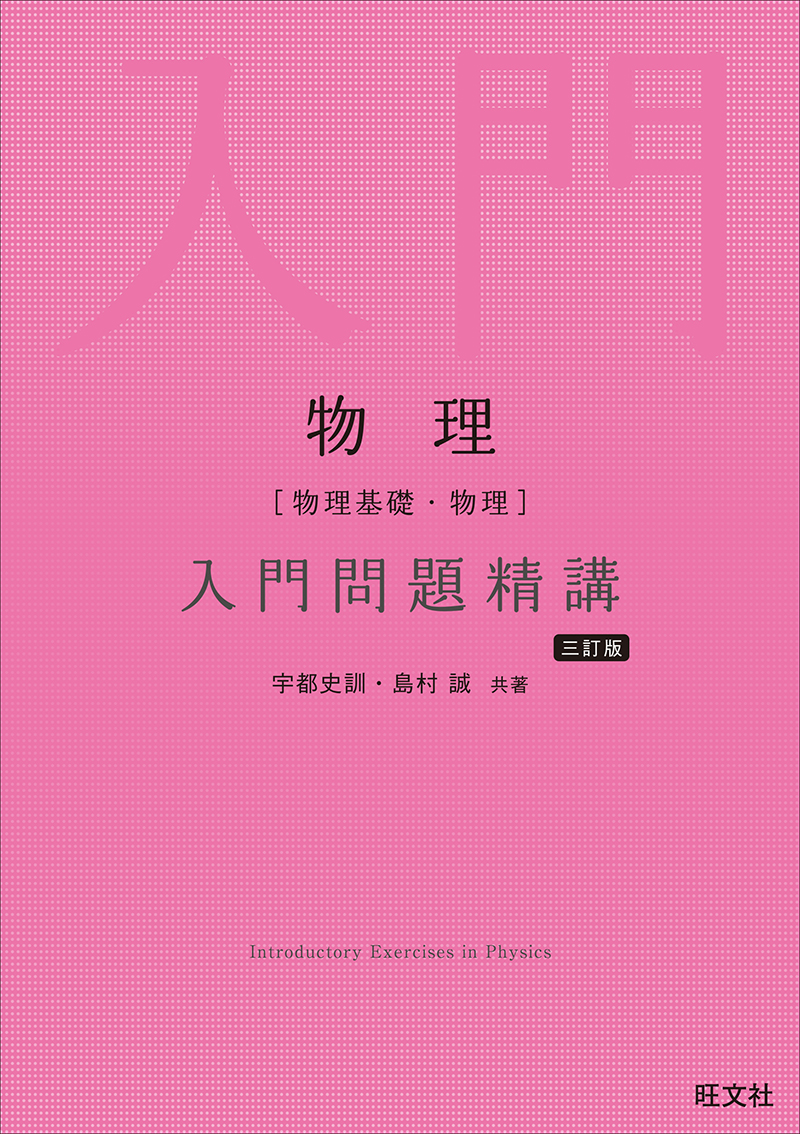
問題演習の導入に最適な一冊です。
入試基礎〜標準レベルの良問が121題、見開き2ページ構成でまとめられています。各題にはテーマが明示されており、大事な公式や知識も合わせて取り上げられています。覚えた解法をどう組み合わせて使うかを確認しながら、入試レベルへの第一歩を踏み出せます。
分量も適度で、授業や概要把握の復習と並行して進めやすく、無理なく取り組める構成です。
物理の入試問題を解くための土台を固めたい人に、まさに最初の一冊としておすすめです。
良問の風 物理
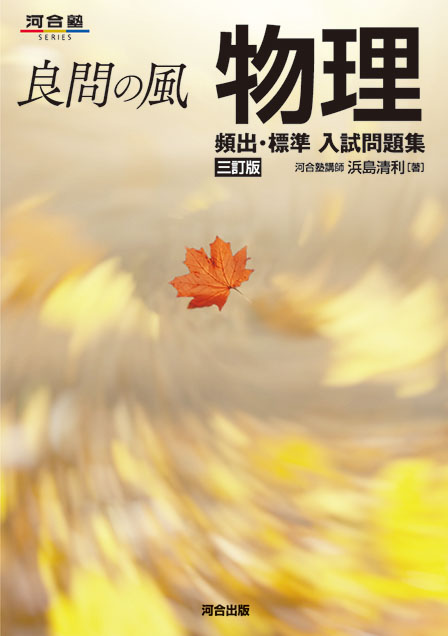
標準レベルの実戦力(MARCH・地方国公立レベル)を養うのに最適な一冊です。
入試本番に近い形式の演習を通して実戦感覚を磨くことができます。単元ごとに章は分かれていますが、各章内の問題にはタイトルが付いていないため、初見の問題で方針を立てる練習にぴったりです。
解説は要点が整理されていて流れがつかみやすく、今の実力を客観的に把握しやすい構成です。同じテーマでも設定が少しずつ異なるため、条件の読み取りや解法の切り替えを通して応用力を高めることができます。
解法暗記で身につけた型を、基礎レベルから一歩進んで実戦形式で使いこなすのに最適な問題集です。
同じく標準問題の問題集としては
物理 基礎問題精講:各題にタイトルと要点が付いており、苦手が分かりやすく復習がしやすい一冊です。
がおすすめです。
名門の森 物理
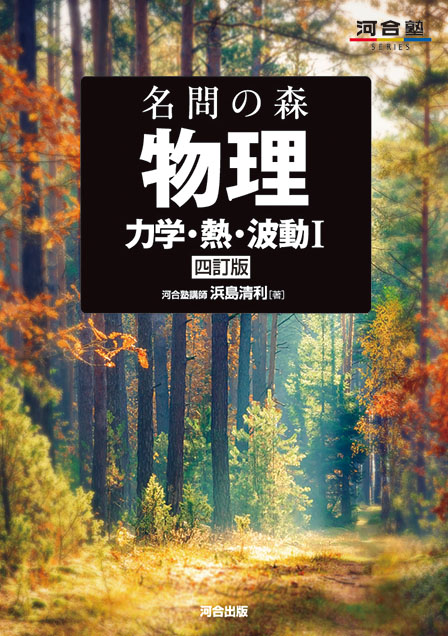
応用レベルの思考力(早慶や最上位国公立レベル)を養うのに最適な一冊です。
設定が複雑な良問が揃っています。複数の解法をどの順番で組み合わせ、どのように方針を立てていくかを練習するのに最適です。
収録されている問題は、過去問をもとに学んでほしいテーマが際立つように抜粋・改題されたものが中心です。狙いが明確な分、実際の入試そのままではない点には注意が必要です。
解説は思考の流れを重視した構成で、方針決定から立式・検算までの過程を追いやすく、解法の筋道を深く理解できます。標準レベルからステップアップしたい人、難問に対しても筋道を立てて取り組める力を身につけたい人におすすめの問題集です。
同じく応用レベルの問題集としては
漆原の物理 最強の99題:解法の積み立てで入試問題を攻略できる感覚を鍛えることができる一冊です。
おすすめです。
物理 標準問題精講
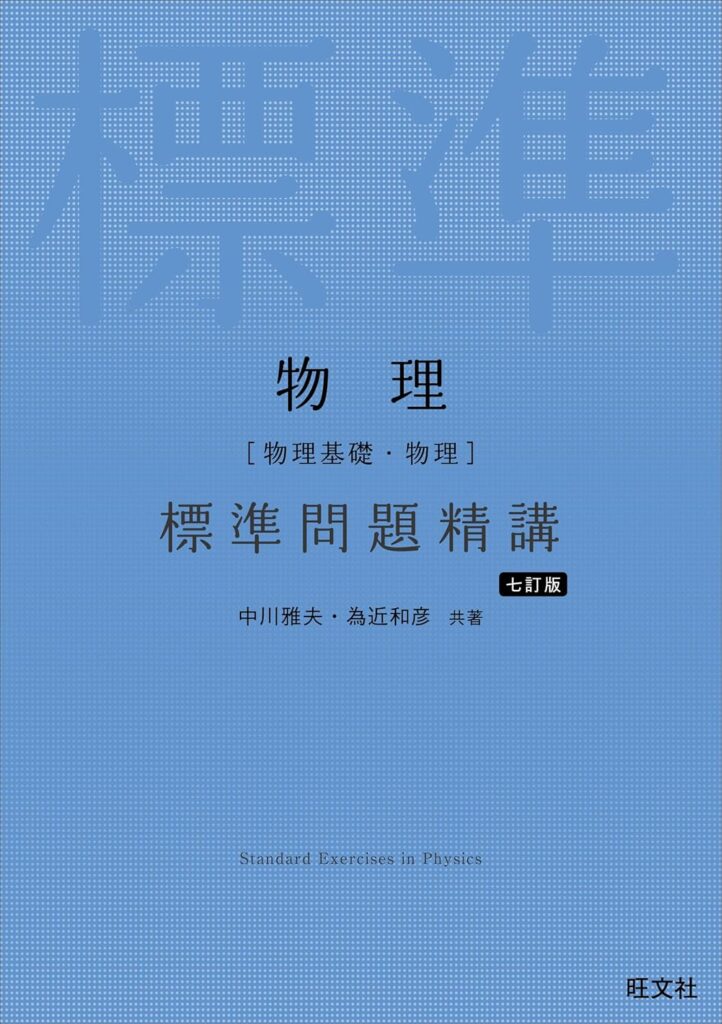
最難関大レベルの問題を通して、入試本番で通用する総合力を仕上げられる一冊です。
収録されているのは、ほぼ過去問そのままの良問ばかりで、実際の入試に近い条件・記述量・難度を体験しながら、方針立てから計算のやり切りまでを本番水準で鍛えることができます。
誘導が少なく、設定も精緻な問題が多いため、条件整理の正確さや論理展開の粘り強さが問われます。過去問に入る前の仕上げ段階として、また志望校の過去問と並行してある分野の強化や弱点補修に使うのがおすすめです。
難問でも一問ずつ腰を据えて取り組み、解説を読んだ後は解答の流れを自力で再現するところまで仕上げましょう。こうした復習を積み重ねることで、入試本番に通用する実力が確実に身についていきます。
同じく発展レベルの問題集として
漆原晃の物理[物理基礎・物理]解法研究:30題の限られた問題を緻密に解説した一冊で、難関大に適したテクニックや実力が身につきます。
秘伝の微積物理:余裕があり、微積を活用したい人向けの問題集です。
がおすすめです。
まとめ
物理の問題演習では、解法暗記で覚えた解法を実際の入試形式の中で使いこなせるようになることが目的といいうです。時間を意識して解き、解説との比較を通して思考の流れを言語化し、解答を自分の手で再現するプロセスを積み重ねることで、入試本番でも安定して得点できる物理の総合力が完成します。
問題演習のその先へ
問題演習の参考書を一周したら、次は過去問に着手しましょう。過去問の着手が遅くなることは自分と大学とのギャップを体感する時期が遅れることと同義です。問題演習を一周したらなるべく早めに過去問に進みましょう。また過去問を解いてみて自分の苦手分野や大学独自の頻出分野などは解法暗記や問題演習に立ち帰り復習しましょう。
もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。
あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博
開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。
現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。
「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。