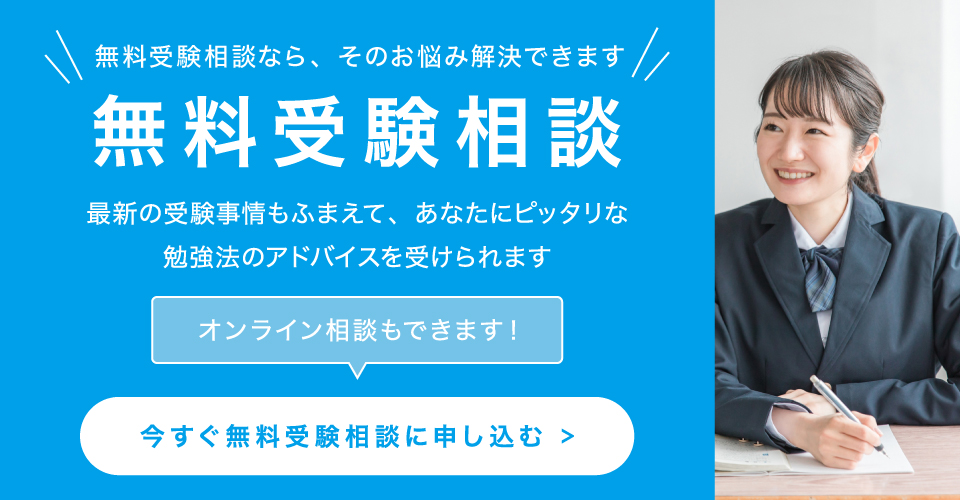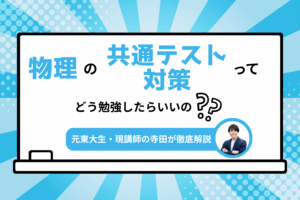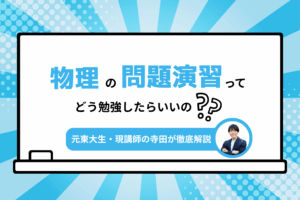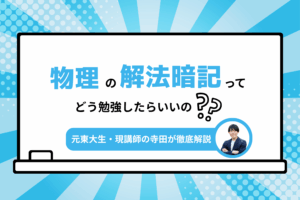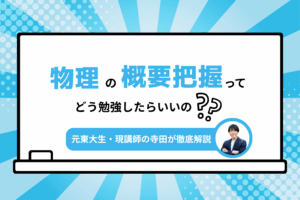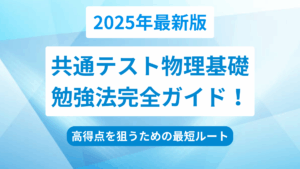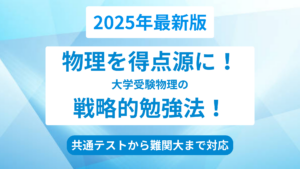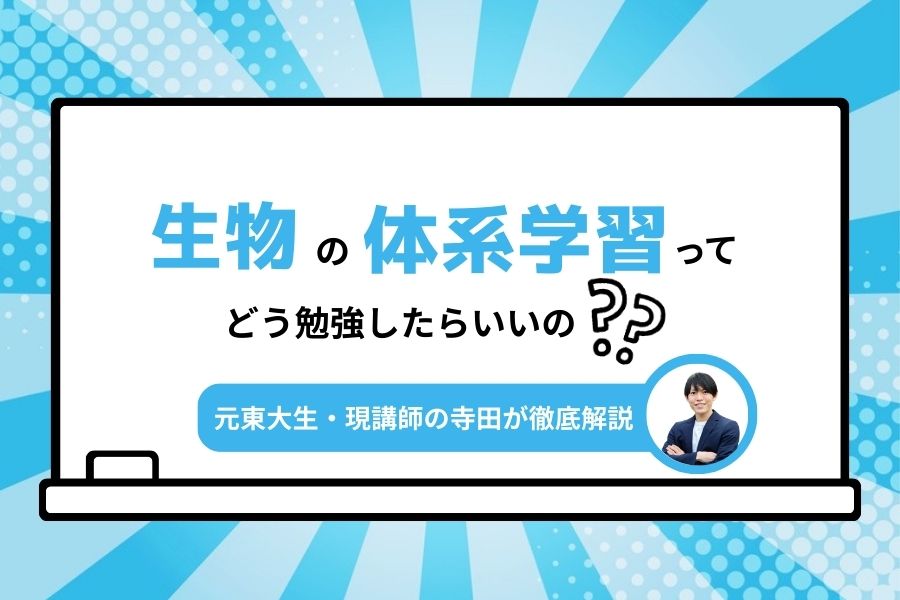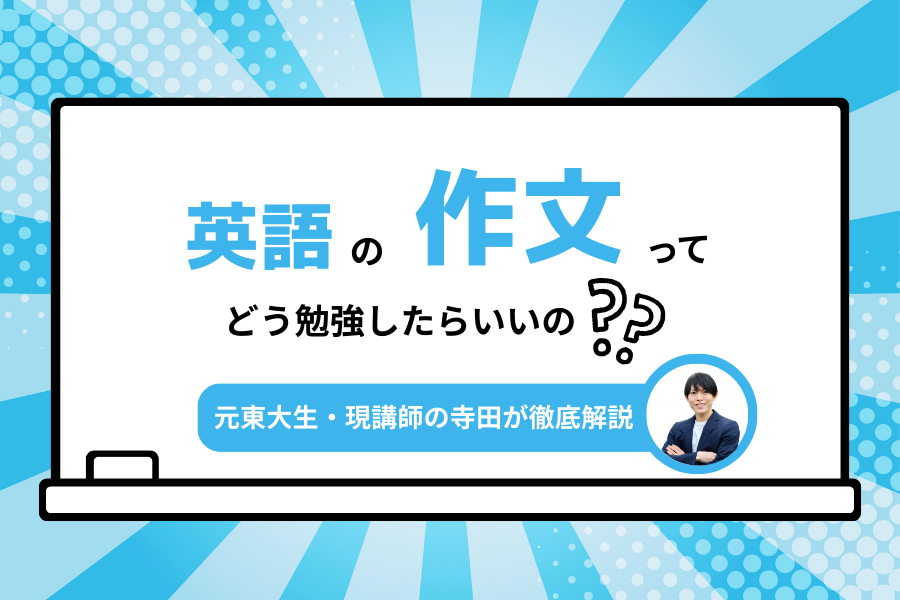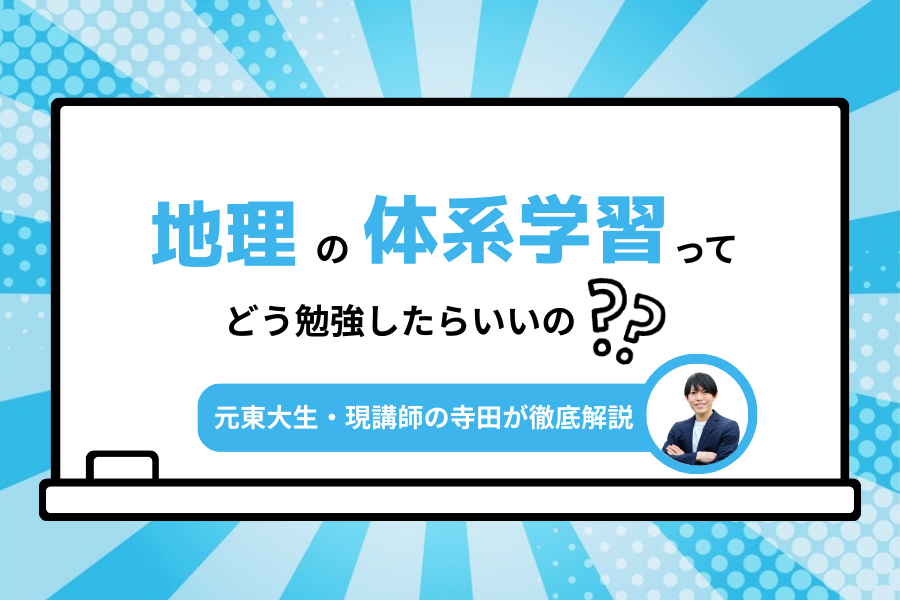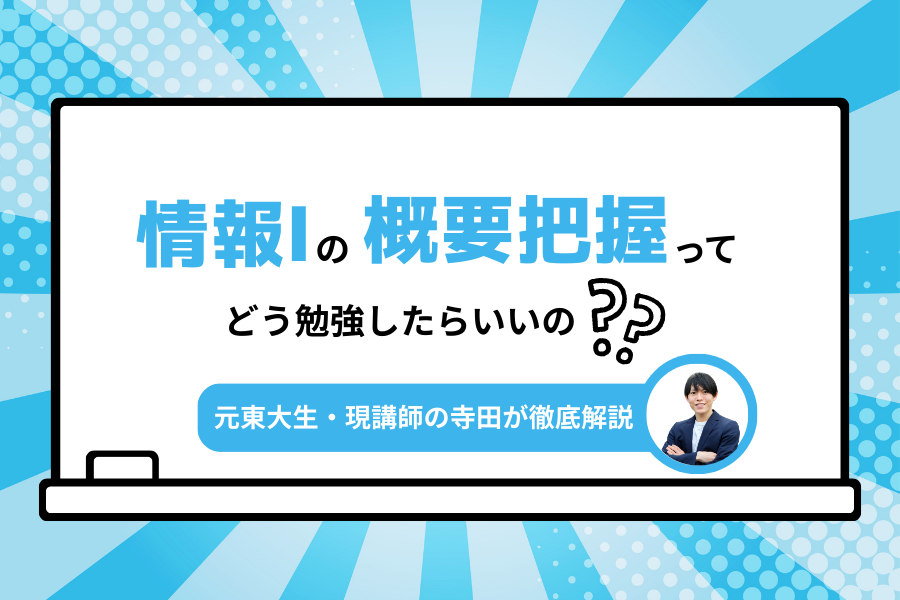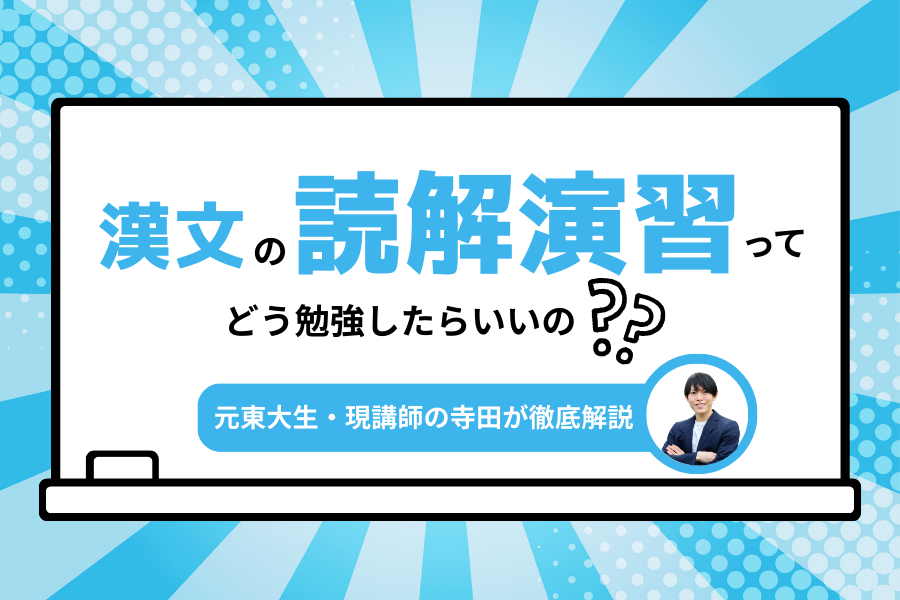【大学受験物理】解法暗記の進め方とおすすめ参考書を徹底解説
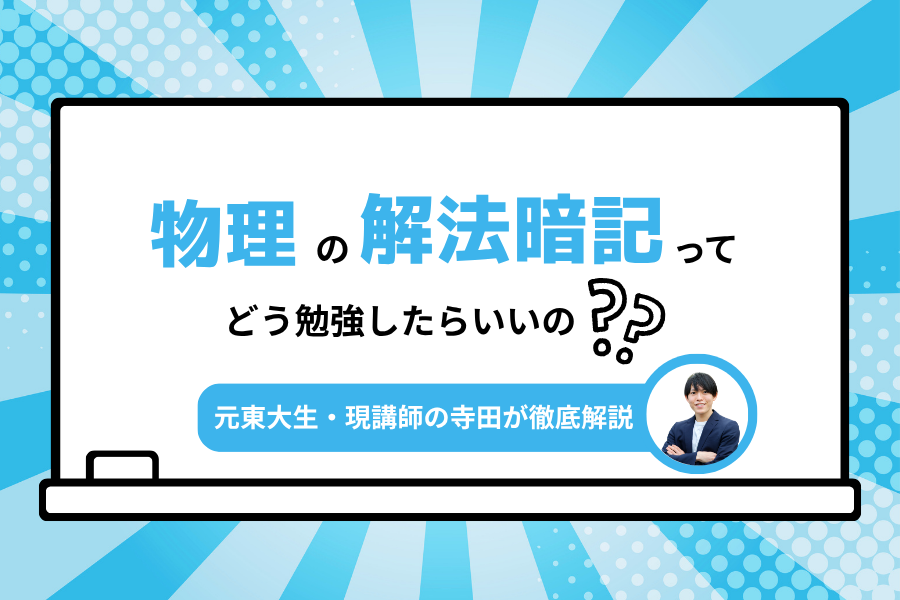

「物理の解法暗記をどのように勉強を進めて良いかわからない。」
「物理の解法暗記の勉強はいつの時期にすれば良いの?」
このようなお悩みに徹底的にお答えしていきたいと思います!
そしてこの記事では以下の内容を詳しく解説していきます!
- 物理の解法暗記の全体像と具体的な勉強方法
- 解法暗記に最適な参考書や問題集
- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略
また、物理の解法暗記に取り組む前に、 物理の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!
物理の勉強法の詳しい情報についてはこちら
解法暗記の攻略法
解法暗記とは?

物理の勉強法は「概要把握」「解法暗記」「問題演習」「過去問対策」という段階に分類できます。
概要把握
高校物理の全範囲を一通り理解する段階です。教科書や参考書にある例題レベルの問題を自力で解けるようになること、そして基本的な公式の使い方が一通り分かることを目標とします。
解法暗記
入試で出題される典型的な問題の解き方を習得する段階です。ここでは問題を見たら、使うべき公式や考え方がすぐに浮かび、手を動かせる状態を目指します。 世の中の入試問題は、これら典型的な解法を組み合わせて作られており、難関大の問題でも基本的な解法の積み重ねで対応できます。 この条件ならこの公式を使うと即答できるよう練習を重ねましょう。
問題演習
入試本番レベルの問題で合格点を取れるようにする段階です。ここでは解法暗記で身につけた典型的な解法を複数組み合わせて使う問題を中心に扱います。 単に公式や解法パターンを覚えているだけでは、実際の入試問題を解き切ることはできません。大切なのは「どの公式を使うか」「どの順番で組み合わせるか」を自分で見抜く力です。 この段階では、実際に問題を解きながら考え方の流れを身につけていきます。なぜこのアプローチを選んだのかを言語化しながら復習することで、応用問題にも対応できるようになります。
過去問対策
志望校の過去問を使い、本番で合格点を取るための実戦力を仕上げる段階です。大学ごとに出題傾向や記述量は大きく異なるため、分析して重点分野や答案の書き方を最適化しましょう。同時に、時間配分・解答順序・取捨選択・見直し方法など本番を想定した立ち回りも固めていきます。
物理の学習は、基礎から順に積み上げていくことで、最終的には入試レベルの問題にも対応できる実力を身につけられます。
解法暗記の段階では、入試で繰り返し出題される定番問題の解き方をあらかじめ覚えることを目的とします。
この段階をしっかり固めておけば、標準的な入試問題は反射的に手が動くレベルまで到達できます。
さらに、難易度が上がって問題が複雑になっても、問題の形から使うべき解法を素早く判断できるようになり、解答スピードと安定感が一気に向上します。
解法暗記を学ぶ2つのメリット

解法暗記の学習は、高校物理の知識を体系的に整理し、実戦で使えるようにするための重要なステップです。以下のような大きなメリットが得られます。
1.理解から実践への橋渡しになる
解法暗記では、概要把握で学んだ公式が実際の問題でどのような条件・パターンで使われるのかを学びます。
どんな場面でその公式が成り立つのかを具体的に確認することで、理解をより深めることができます。
概要把握の段階で得た知識を、実際に使える力へと変える橋渡しをしてくれるのが、この解法暗記のステップです。
2.思考の型が身につく
物理の問題は表面的に違って見えても、実際に使う公式や考え方のパターンは限られています。
解法暗記を重ねることで、問題の見方や考える順序、立式の型が自然と統一され、思考のブレがなくなります。
この段階で思考の型が定着すると、標準的な入試問題はほとんど迷わずに解答できるレベルまで到達できます。
さらに、難易度が上がり複雑な設定になっても落ち着いてアプローチできるようになります。
解法暗記に取り組む2つのメリット
1.理解から実践への橋渡しになる
2.思考の型が身につく
解法暗記の勉強法

次に具体的な「解法暗記の勉強法」について紹介します。
まずは、自力で問題を解いてみてから、解説を読みましょう。
解法を身につけるために、解き終わったあとは次の3つのSTEPで復習してください。
STEP 1.解法のタイトルを意識する
まずは、扱う問題がどんな解法を学ぶことを目的としているのかを明確にしましょう。
物理の入試問題は見た目が違っても、根本的に問われている解法パターンはいくつかに分類できます。
たとえば、力のつり合いを立式する問題なのか、エネルギー保存を利用する問題なのか、回路でオームの法則を使い分ける問題なのかなど、この問題で学ぶ解法のタイトルは何かを意識して整理しておくことが重要です。
この段階では、問題のタイトルがそのまま覚えるべき解法名になっている参考書を使うと効率的です。
また、入試問題をそのまま載せるのではなく、テーマがぶれないよう適度に編集されている教材を選ぶと、理解と暗記の両立がしやすくなります。

どの参考書がこの条件を満たしているかは、後半で詳しく紹介します!
解法のタイトルを意識して学ぶことで、後から似た問題に出会ったときに、どのタイプの解法を使えばよいかを瞬時に判断できるようになります。
STEP 2.解法の思考プロセスを吸収する
テーマが分かったら、次はその問題をどう考えて解くかを分析します。
ここで大切なのは答そのものではなく、方針が定まるまでの流れを身につけること。問題文から必要な情報を拾い、どのような作図をして、どの順番で立式するかを決める一連のプロセスを丁寧になぞりましょう。

特に下のようなことを意識して、解法の流れを確認しましょう!
解法暗記で意識したいこと
ゴールと設定の確認: 何を求めるか、与えられている量は何かを明確にする。
作図方法: 座標や基準の設定、力の分解、電流の向き、位相の基準などを図に落とす。
公式の選択とその成立条件: どの公式や法則を使うか、その適用条件が満たされているか確認する。
立式の順序: 問題の流れを整理し、どの順番で式を立てているかを意識する。
検算: 特に次元や符号をチェックする。
STEP 3. 類題で定着させる
基本的な解法を覚えたら、次は設定が少し異なる類題に取り組んでみましょう。
たとえば、角度や向き、条件が少し変わっただけでも、使う式や考え方の流れはほとんど同じです。
こうした類題でアウトプットすることで、覚えた解法を実戦で使いこなせる状態へと仕上げられます。
この段階で条件が変わっても使う解法を見抜ける状態になれば、解法暗記の目的はほぼ達成です。
次の問題演習にもスムーズに移行できます。
- 問題のテーマを把握する
- 解法の思考プロセスを吸収する
- 類題で定着させる

以上3つのステップで解法を完璧に身につけることができます!
おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

現論会でも使用している、おすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します!
先ほど紹介したように、解法暗記で使用する参考書は、問題のタイトルがそのまま覚える解法のタイトルになっていること、そして一つの問題が一貫したテーマで構成されていることが重要です。
以下では、その二つの条件を満たし、現論会でも実際に使用しているおすすめの参考書を紹介します。
おすすめ参考書
漆原の物理 明快解法講座
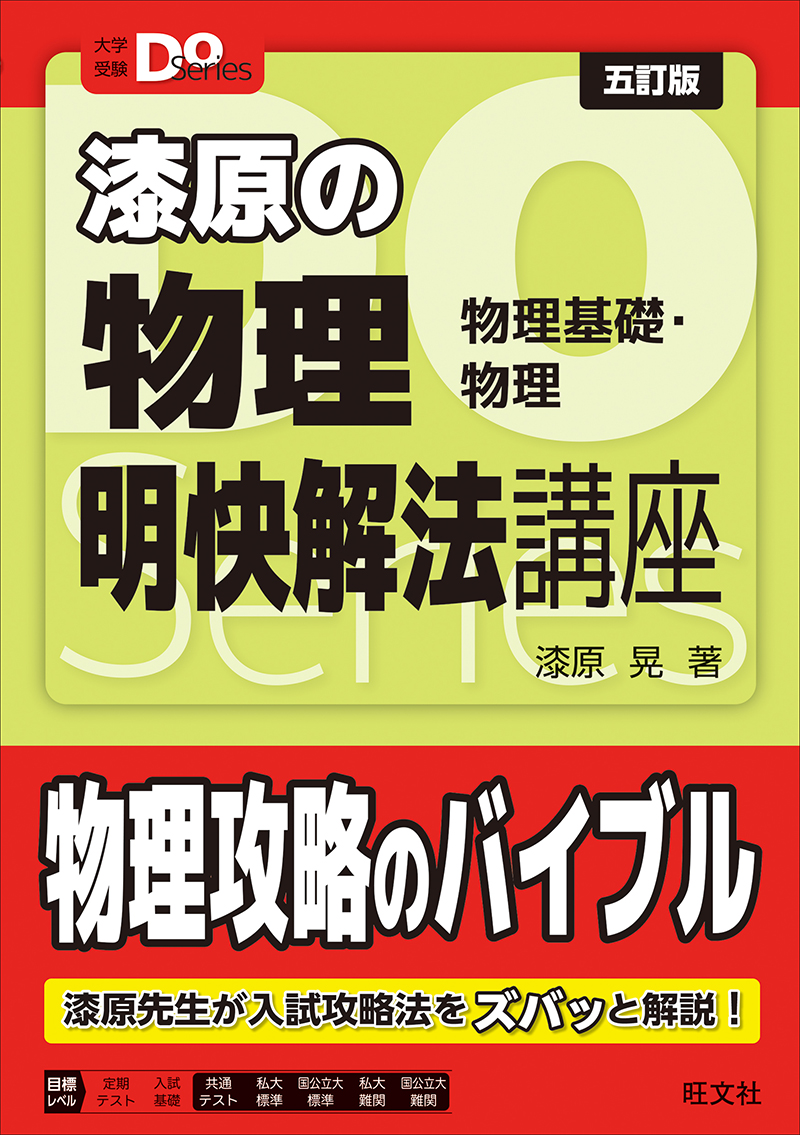
解法の型を短期間で身につけたい人におすすめの一冊です。
入試で頻出する典型問題を中心に構成されており、約100題というコンパクトな分量で、解法暗記に必要な基本パターンを一通り網羅できます。
各テーマごとに解き方が明確に示されているため、学習の目的がぶれず、短期間でも効率よく知識を整理できます。説明も平易でテンポが良く、独学でも挫折しにくい構成です。
物理の解法の型を素早く固めたい人、まずは全範囲の解法を一周して得点の土台を作りたい人に最適な参考書です。
ひとりで学べる秘伝の物理講義
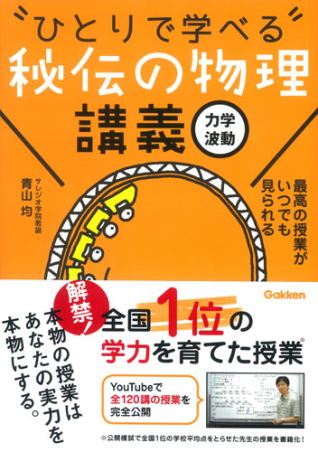
丁寧に基礎から固めつつ、解法の型までしっかり身につけたい人におすすめの一冊です。
全189題・約500ページのボリュームで、典型問題を軸に構成されており、各章を通して解法が自然に定着します。解説は簡潔で読みやすく、独学でも苦になりにくいのが特長です。
各問題にはQRコードの動画解説が用意されており、紙面で理解しづらい思考のつなぎ目や作図のポイントも、講義感覚で補えます。
じっくり時間をかけて確実に力をつけたいタイプ、標準レベルを確実にしつつ応用への足場も築きたい人に最適です。
体系物理
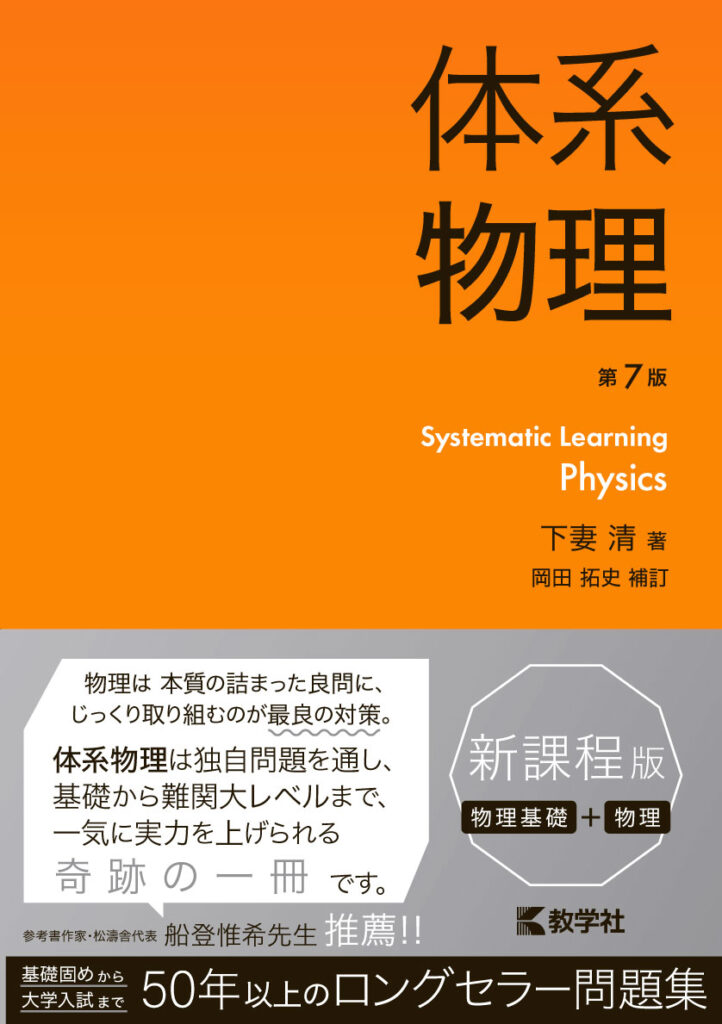
標準レベルを超えて、最難関大でも通用する思考力を養いたい人におすすめの一冊です。
最難関レベルの問題では、使う公式自体は同じでも、その成立条件の見抜き方や視点の切り替えが得点を左右します。
本書では、定義や成立条件への理解が求められる、解法が一手でも難易度の高い問題を扱っているのが特徴です。
こうした問題を通して、最難関大の問題にも対応できる力を養うことができます。
全383題という大ボリュームで、問題ごとに条件の違いや視点の転換を繰り返し体験できるのも魅力です。
深い理解を重ねながら、時間をかけて解法をより本質的に定着させたい受験生におすすめです。
まとめ
解法暗記は、物理の理解を実戦で使える力に変えるためのステップです。
この記事で解説したようなSTEPで丁寧に取り組むことで、標準問題は反射的に手が動くようになり、
複雑な設定の問題にも落ち着いて対応できるようになります。
解法暗記のその先へ
解法暗記を終えたら、次はより実戦的な問題演習へと進んでいきましょう。
いよいよ実際の入試問題に近い、解法暗記で覚えた解法を複数組み合わせるような問題を解く練習を行います。
もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。
あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博
開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。
現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。
「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。