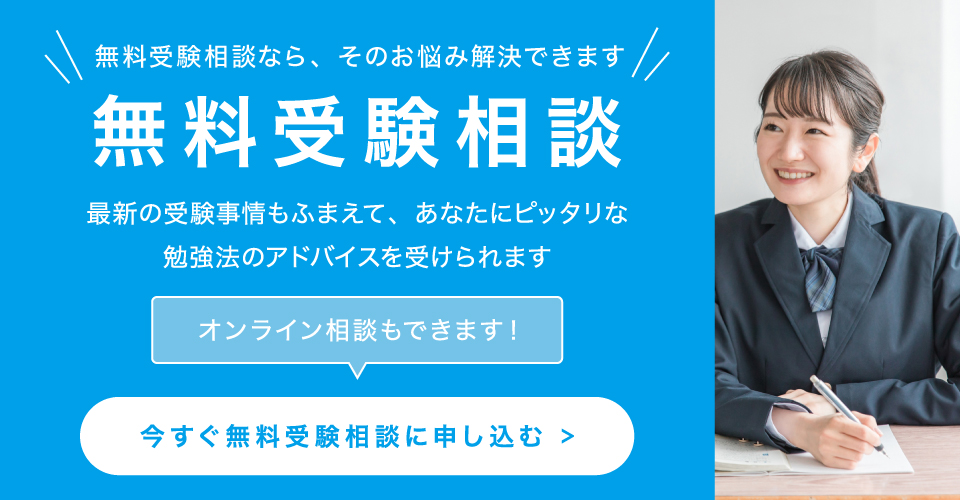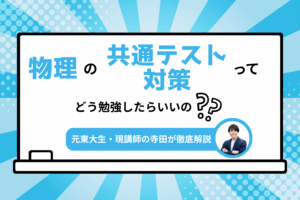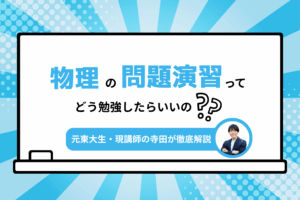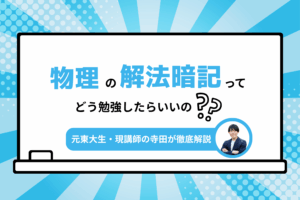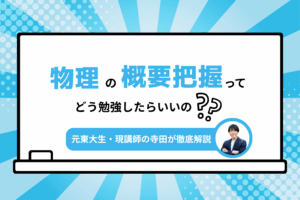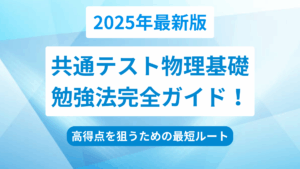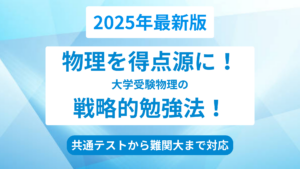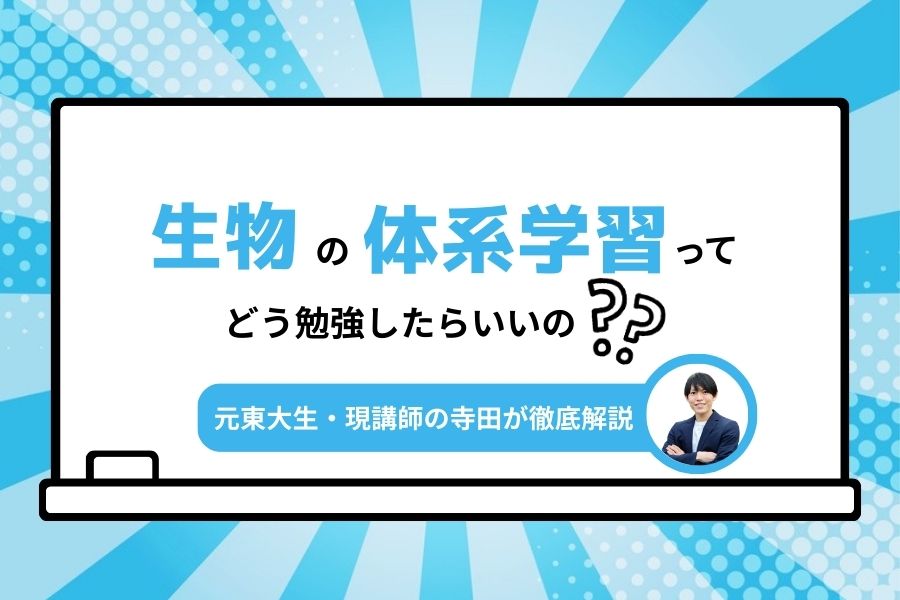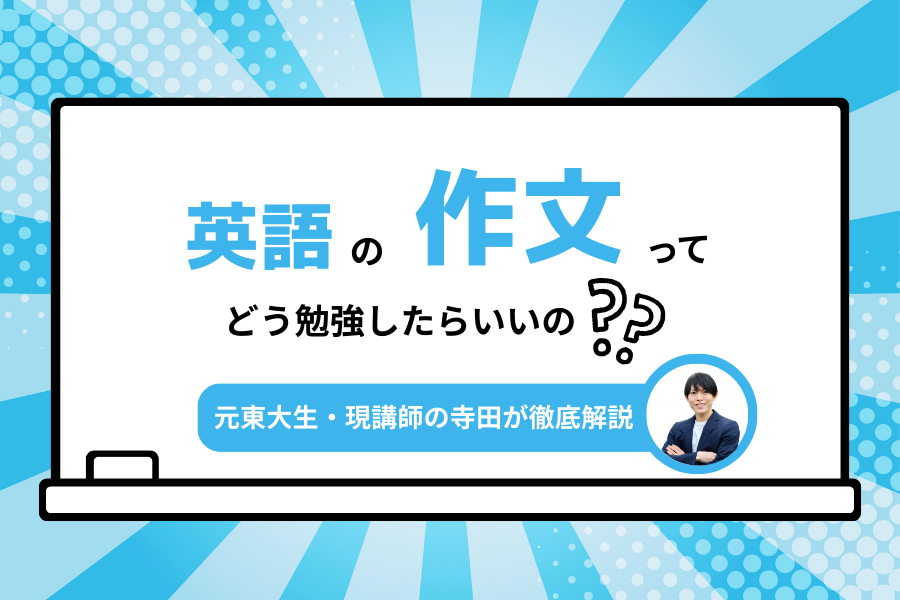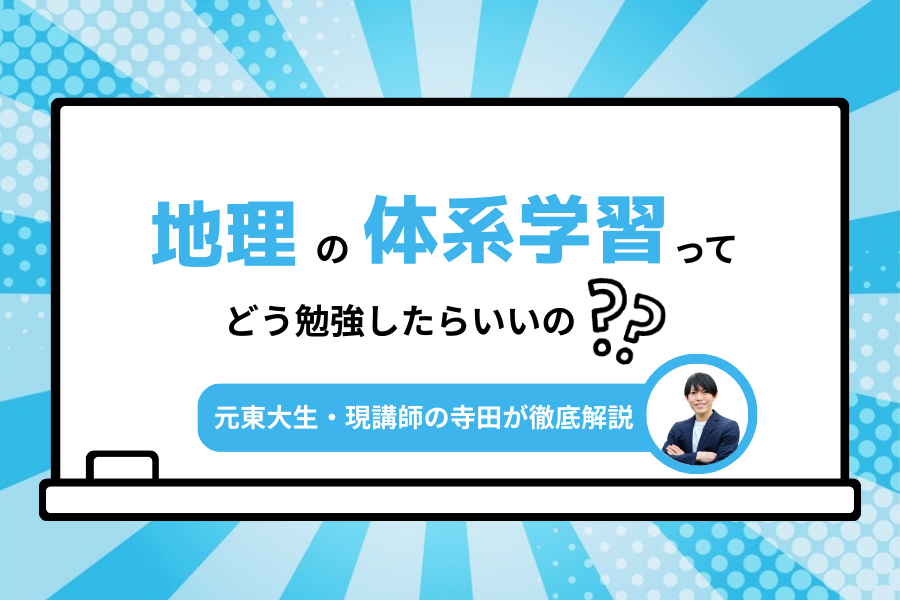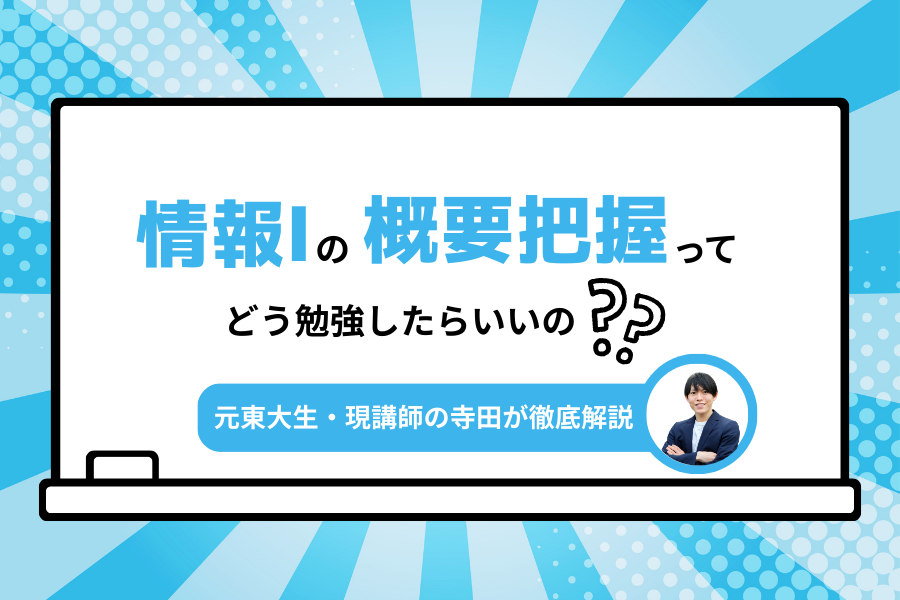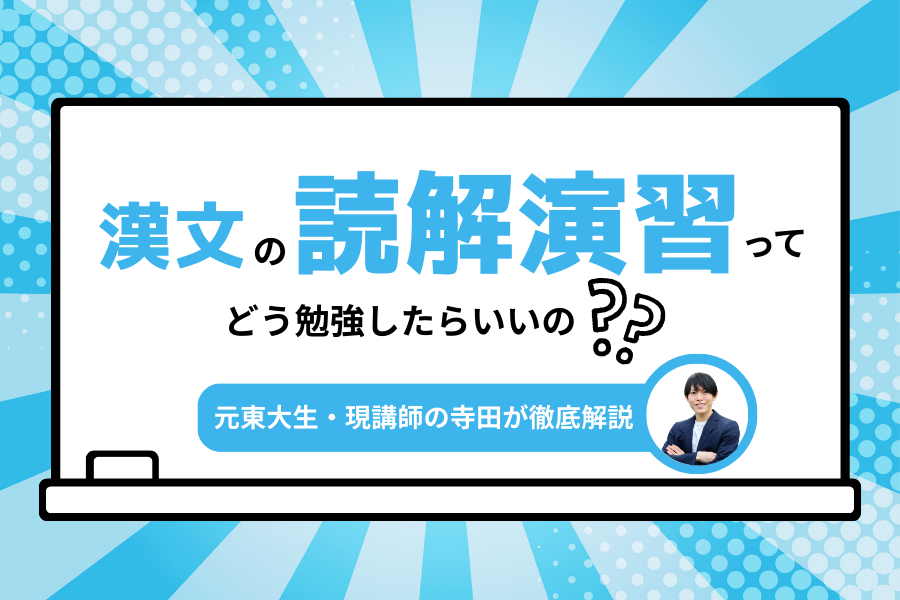【大学受験物理】概要把握の進め方とおすすめ参考書を徹底解説
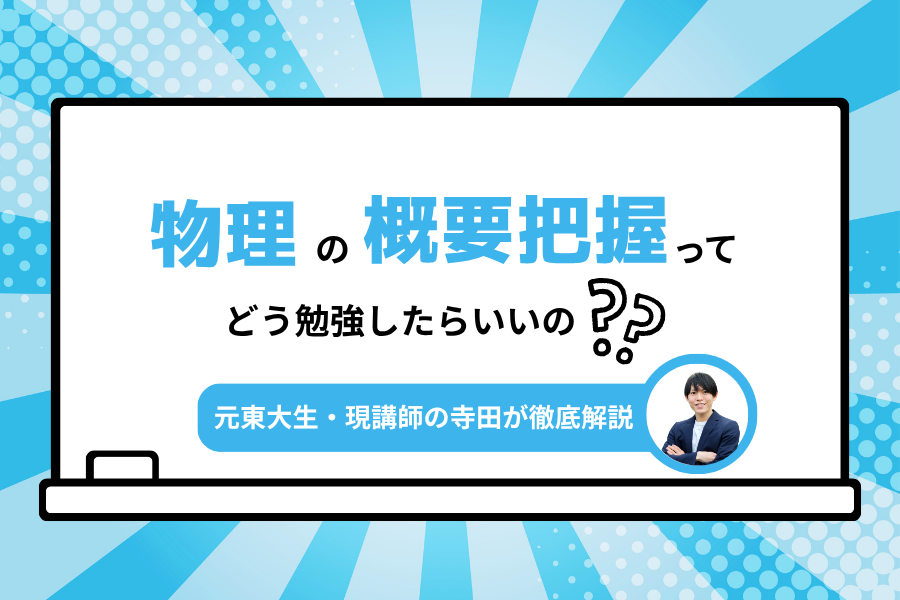

「物理の概要把握をどのように勉強を進めて良いかわからない。」
「物理の概要把握の勉強はいつの時期にすれば良いの?」
このようなお悩みに徹底的にお答えしていきたいと思います!
そしてこの記事では以下の内容を詳しく解説していきます!
- 物理の概要把握の全体像と具体的な勉強方法
- 概要把握に最適な参考書や問題集
- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略
また、物理の概要把握に取り組む前に、 物理の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!
物理の勉強法の詳しい情報についてはこちら
概要把握の攻略法
概要把握とは?

物理の勉強法は「概要把握」「解法暗記」「問題演習」「過去問対策」という段階に分類できます。
概要把握
高校物理の全範囲を一通り理解する段階です。教科書や参考書にある例題レベルの問題を自力で解けるようになること、そして基本的な公式の使い方が一通り分かることを目標とします。
解法暗記
入試で出題される典型的な問題の解き方を習得する段階です。ここでは問題を見たら、使うべき公式や考え方がすぐに浮かび、手を動かせる状態を目指します。 世の中の入試問題は、これら典型的な解法を組み合わせて作られており、難関大の問題でも基本的な解法の積み重ねで対応できます。 この条件ならこの公式を使うと即答できるよう練習を重ねましょう。
問題演習
入試本番レベルの問題で合格点を取れるようにする段階です。ここでは解法暗記で身につけた典型的な解法を複数組み合わせて使う問題を中心に扱います。 単に公式や解法パターンを覚えているだけでは、実際の入試問題を解き切ることはできません。大切なのは「どの公式を使うか」「どの順番で組み合わせるか」を自分で見抜く力です。 この段階では、実際に問題を解きながら考え方の流れを身につけていきます。なぜこのアプローチを選んだのかを言語化しながら復習することで、応用問題にも対応できるようになります。
過去問対策
志望校の過去問を使い、本番で合格点を取るための実戦力を仕上げる段階です。大学ごとに出題傾向や記述量は大きく異なるため、分析して重点分野や答案の書き方を最適化しましょう。同時に、時間配分・解答順序・取捨選択・見直し方法など本番を想定した立ち回りも固めていきます。
物理の学習は、基礎から順に積み上げていくことで、最終的には入試レベルの問題にも対応できる実力を身につけられます。
中でも概要把握は学習の出発点であり、ここで土台を固められるかどうかが今後の伸びを大きく左右します。教科書や参考書の例題レベルを疎かにしてしまうと、その後の学習で必ず壁にぶつかることになります。まずはこの段階でしっかり基礎を身につけましょう。
概要把握を学ぶ2つのメリット

概要把握の学習は、高校物理の知識を体系的に整理し、実戦で使えるようにするための重要なステップです。以下のような大きなメリットが得られます。
1.力学を軸に、物理全体を体系的に理解できる
物理は力学・波動・電磁気・熱・原子と分野が分かれていますが、根本には共通する考え方があります。概要把握でまず力学をしっかり学ぶことで、保存則や運動方程式といった原理を他分野にも応用でき、物理全体を一つの筋の通った体系として整理できます。
2.知識の整理によって、問題演習がしやすくなる
概要把握を通して、学んだ内容が物理全体の中でどこに位置づくのかを整理できるようになります。
知識どうしの関係が見えることで、どの公式をどの場面で使えばよいかを判断しやすくなり、問題を解く際の思考の流れも滑らかになります。
また、分野をまたぐ問題でも、どの分野の何に関連しているかを把握できているため、演習を効率的に進められます。
概要把握に取り組む2つのメリット
1.力学を軸に、物理全体を体系的に理解できる
2.知識の整理によって、問題演習がしやすくなる
概要把握の勉強法

次に具体的な「概要把握の勉強法」について紹介します。
STEP 1.力学から固める
物理の学習はまず力学から始めましょう。力学は運動方程式やエネルギー保存則など、他分野にも共通する考え方が多く含まれており、物理全体の土台となる分野です。力学をしっかり理解しておくことで、波動や電磁気といった他の分野でも力学の考え方を流用して解くことができるようになります。
さらに、入試では必ず出題されるテーマであるため、概要把握にとどまらず解法暗記まで優先的に固めてしまうことが重要です。力学をしっかり仕上げておけば、その後に学ぶ分野でも考え方をスムーズに応用でき、学習効率が大きく向上します。
STEP 2.現象を公式で表す
各分野の学習では、公式や法則がどんな物理現象を表していて、どのような場面で適用できるのかを意識して学びましょう。
この段階では、例えば物体の運動や音の波など、さまざまな物理現象を数式で表現できるようになることが最大の目標です。
現象を数式で表現できることは、物理の問題を解くための土台を築く第一歩です。
STEP 3. 例題レベルを自力で解く
教科書や参考書に載っている例題を使って、基本的な問題を実際に解いてみましょう。この段階の目標は解説を見ずに例題が解ける状態になることです。難問や入試問題に挑む必要はなく、例題レベルで公式をどう当てはめるかを経験しておくことが、次の解法暗記につながります。
概要把握の3つのステップ
- 力学から固める
- 現象を公式で表す
- 例題レベルを自力で解く
おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

現論会でも使用している、おすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します!
ここでは、物理概要把握の学習に特化した、おすすめの参考書を解説します。自分のレベルと学習スタイルに合った一冊を選ぶことが大切です。到達レベルの高さと学習形式の2軸で考えると選びやすくなります。
おすすめ参考書
一度読んだら絶対に忘れない物理の教科書
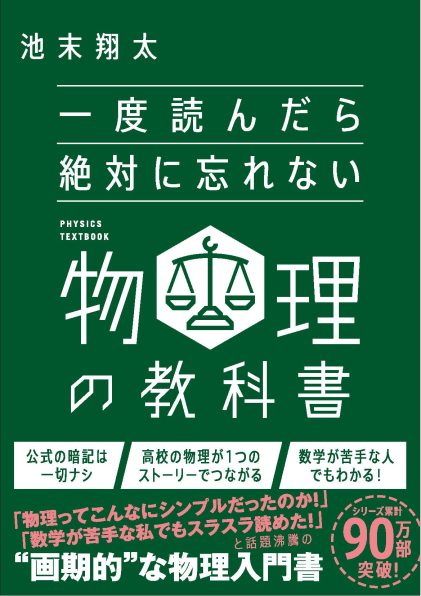
読むだけで物理がわかる講義形式の参考書で、基礎をしっかり押さえたい人におすすめの一冊です。古典物理が成立するまでに、どのような流れで現象やそれに関する法則が解き明かされてきたかをストーリーとして学べるため、物理が苦手な人でも内容がすっと頭に入ってきます。数式よりも考え方や背景の理解を重視しており、物理を知るための講義を受けているような感覚で読み進められる一冊です。
また、同様に演習題がほとんどなくインプットに特化した基礎的な講義系参考書としては
イメージでわかる物理基礎&物理 橋元流解法の大原則:直感的に物理を理解できます。
がおすすめです。
宇宙一わかりやすい高校物理
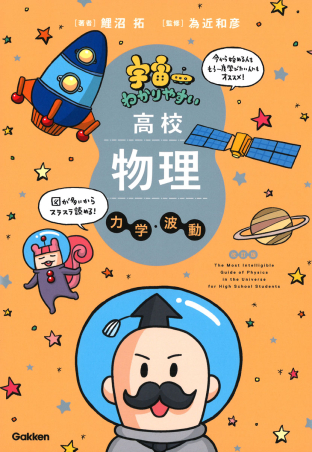
手を動かしながら理解する実践型の参考書です。文章による説明と図解が左右に並ぶ構成になっており、抽象的な原理も視覚的に理解しやすくなっています。さらに、確認問題が付属しているため、読んで終わりではなく説明 → 問題で確かめるという流れを実践できます。わかりやすさは物理参考書の中でもトップクラスで、初学者でも挫折しにくい一冊です。
同様に手を動かしながら学べるアウトプット重視の基礎的な参考書としては
秘伝の物理 物理のインプット講義:公式の導出が深く学べ、理解を定着できます。
やまぐち健一の わくわく物理探検隊 NEO:微積物理の入門として最適です。
おすすめです。
坂田アキラの物理基礎・物理の解法が面白いほどわかる本
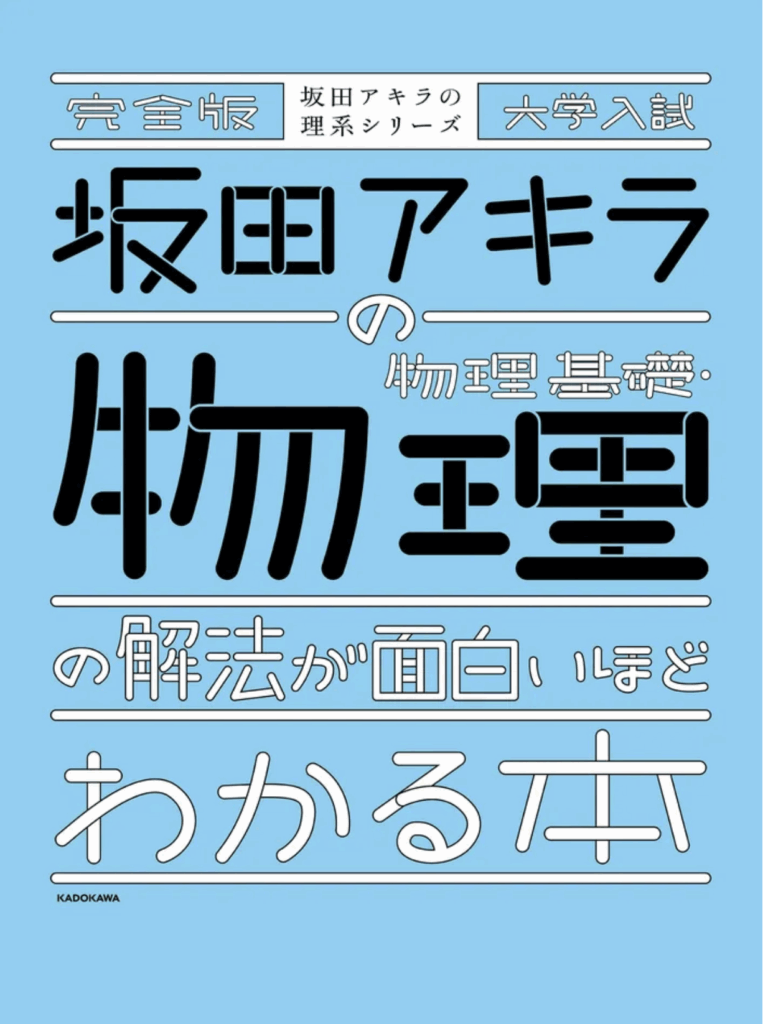
受験生の目線で丁寧に解説された参考書で、前の2冊よりも到達点を高めに設定したい人におすすめです。公式や法則の解説に加えて、問題を解くときに注意すべきポイントを具体的に示してくれるため、つまずきやすい箇所を確実に克服できます。
また、265問に及ぶ例題と確認問題が収録されており、インプットからアウトプットまでを一連の流れで学べる構成になっています。教科書レベルから標準レベルの問題までを無理なくカバーできる内容で、物理を得点源にしたい受験生の最初の一冊として最適です。
同じく1冊目から到達点を高めに設定したい場合は、
漆原晃の物理基礎・物理が面白いほどわかる本:数式で物理をロジカルに学べます。
がおすすめです。
まとめ
概要把握は、高校物理の膨大な内容を体系的に整理し、今後の学習効率を大きく左右する重要なステップです。この記事で解説したように、力学を軸に学ぶ→現象と公式を結びつける→例題レベルを自力で解くという3つのステップを丁寧に実践することが、物理の基礎を最短で固める道です。
概要把握のその先へ
概要把握を終えたら、次は解法暗記の段階に進みましょう。典型問題を通して公式の使い方を身につけ、条件の違いに応じて適切なアプローチを選べる力を養います。
もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。
あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博
開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。
現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。
「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。