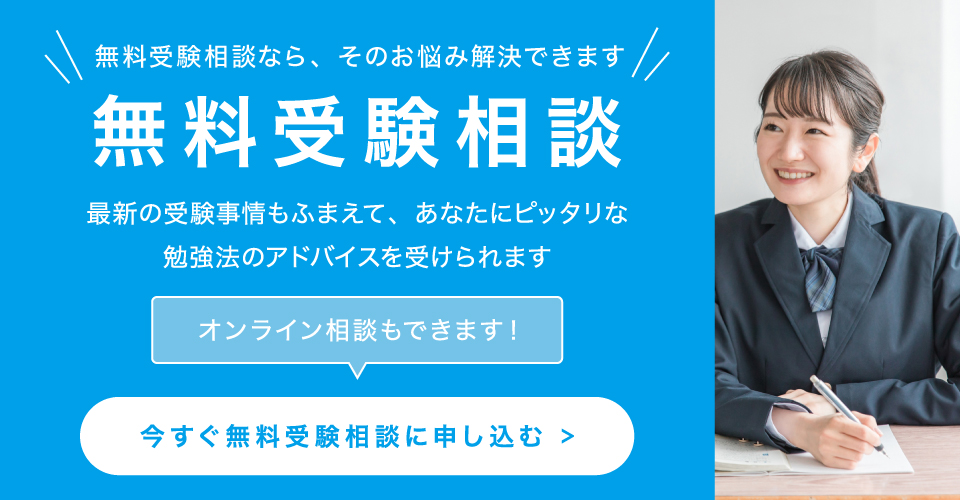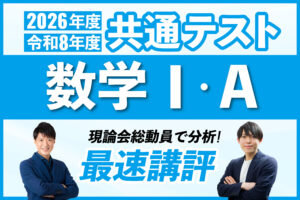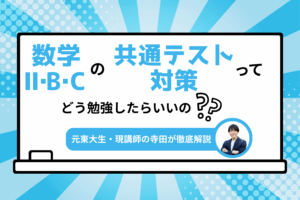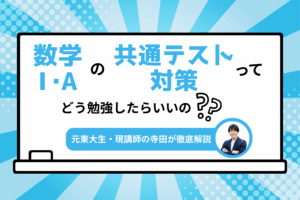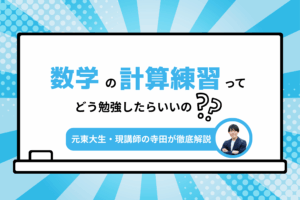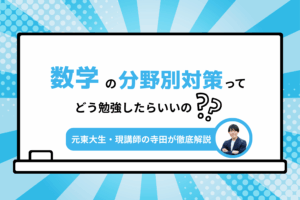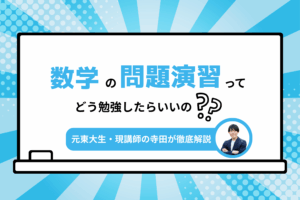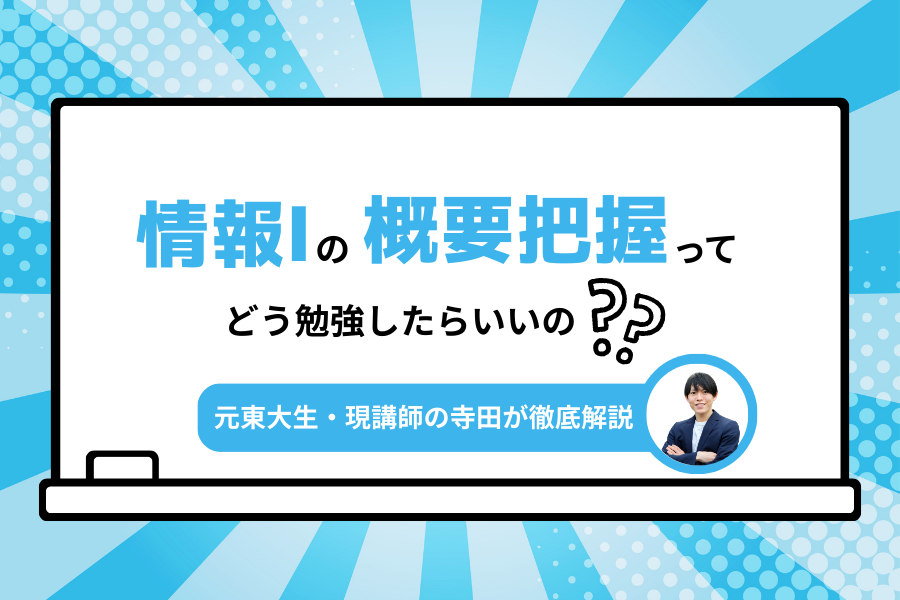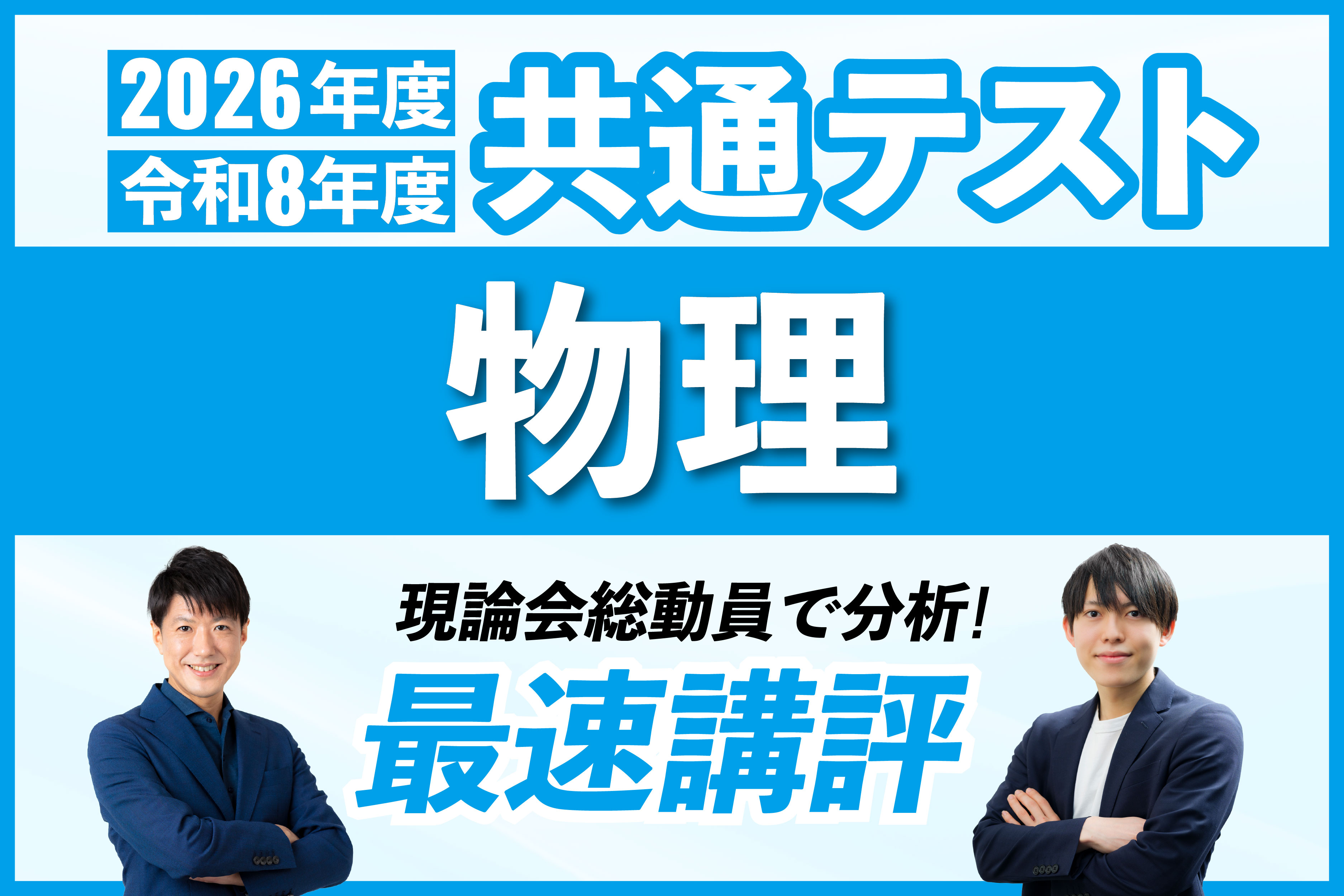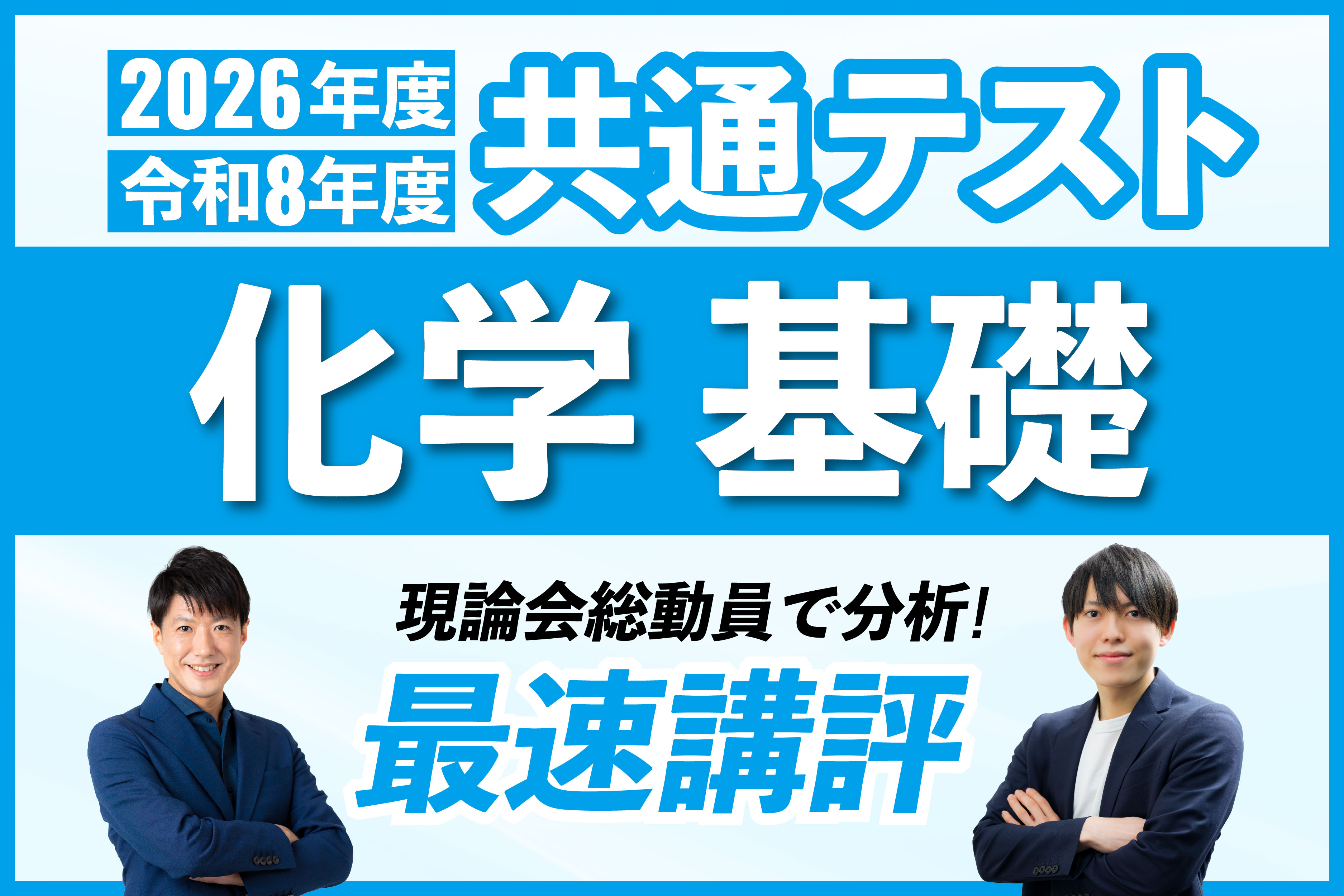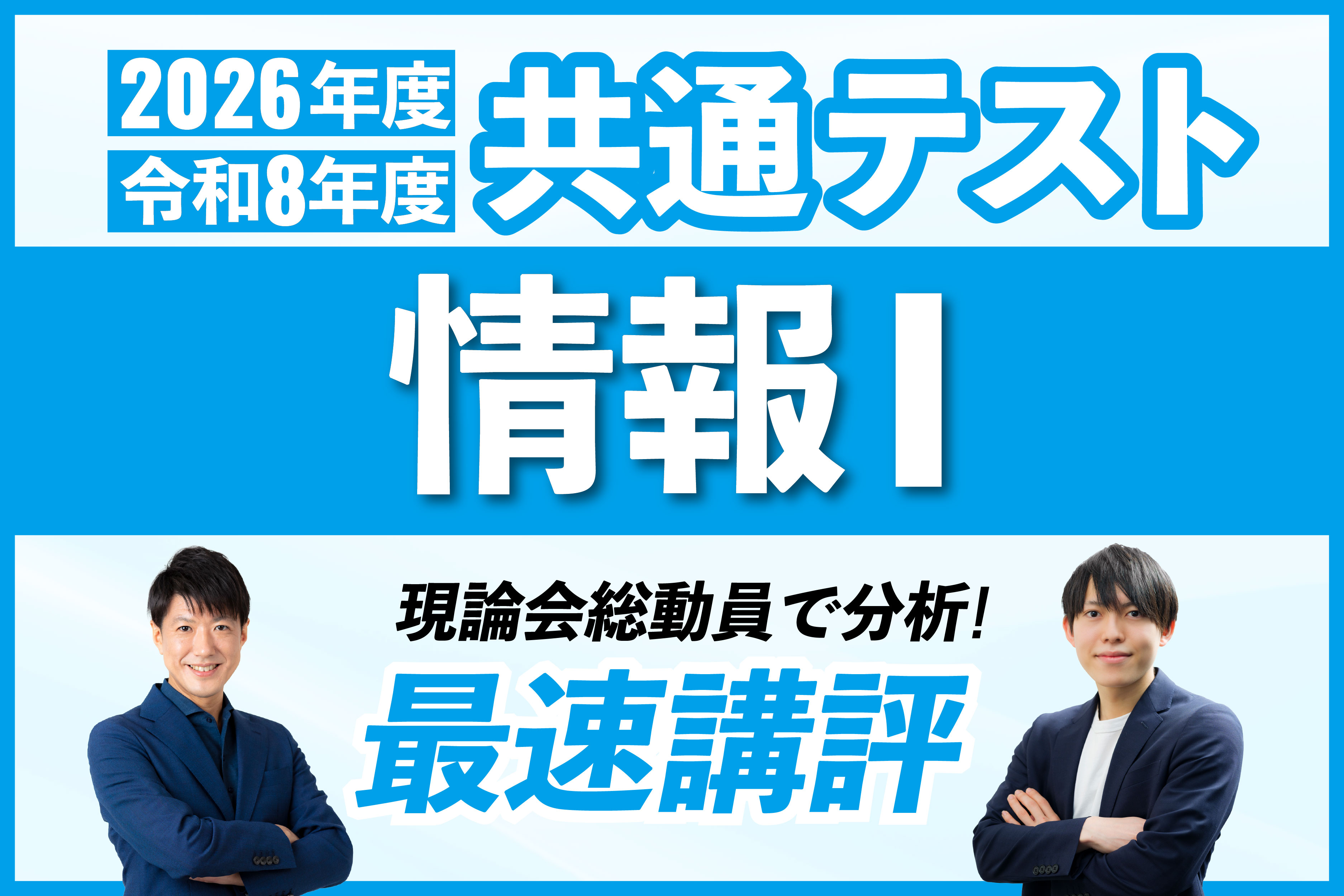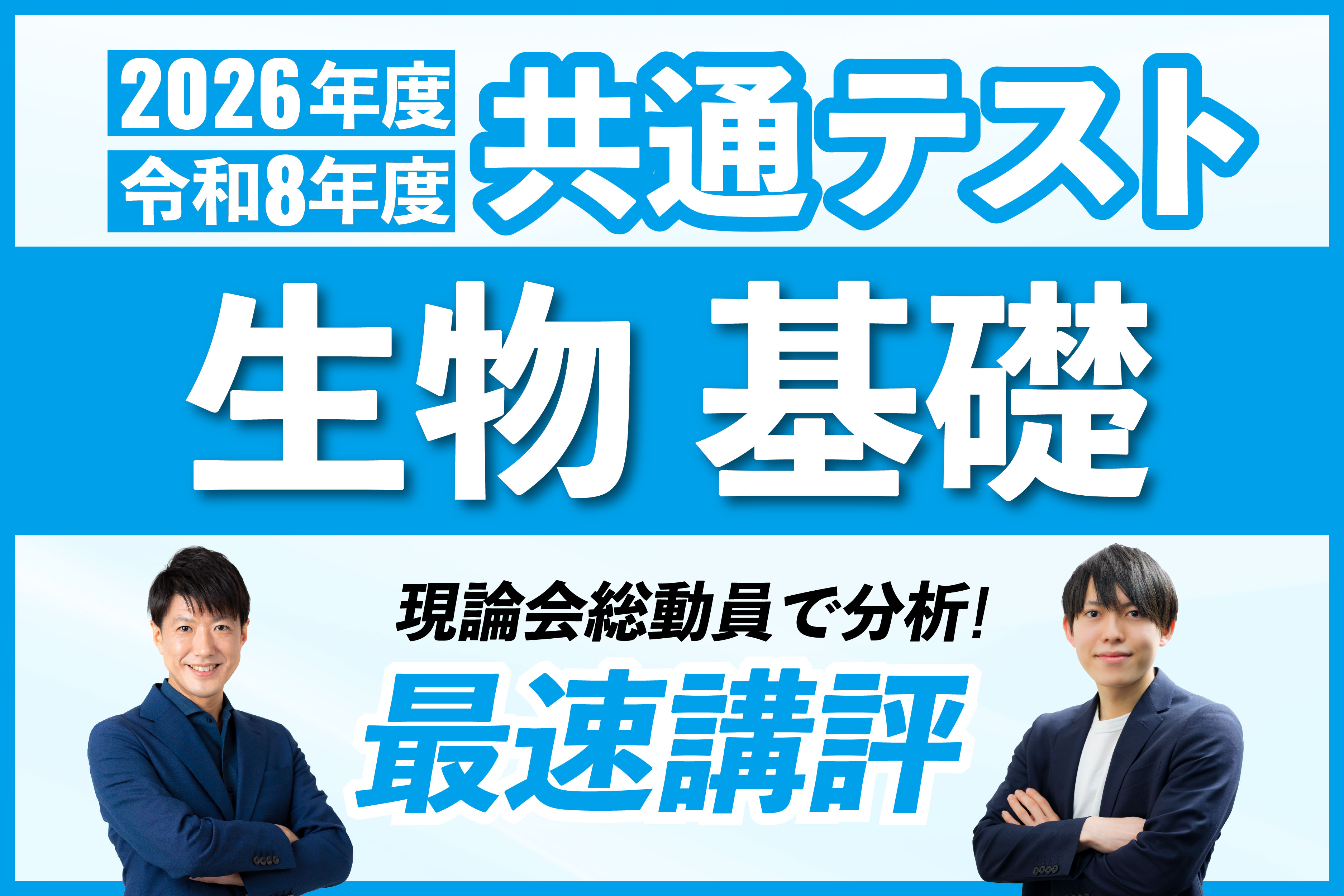数学の解法暗記を攻略!【入試基礎レベルをマスターする勉強法】
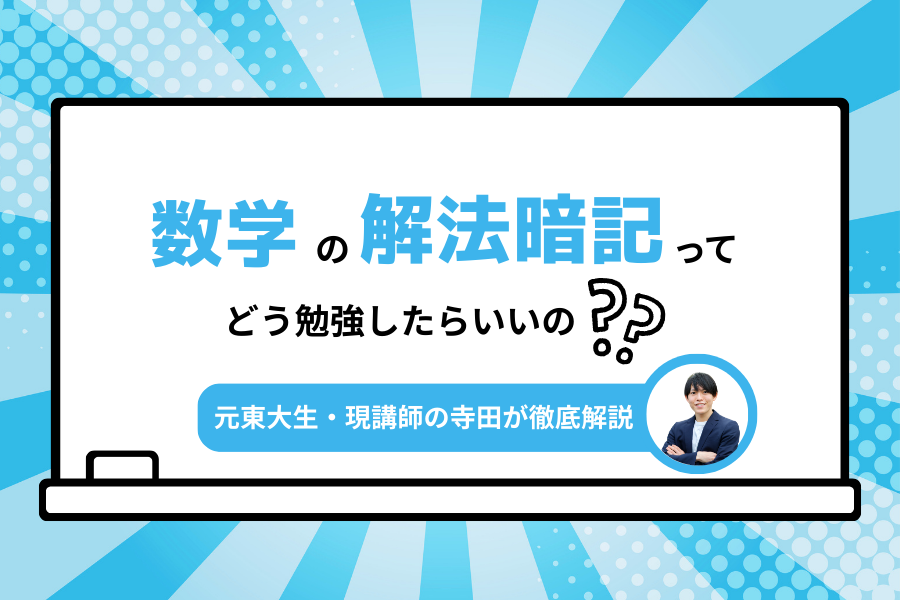
そしてこのサイトでは以下の内容を詳しく解説していきます!
- 解法暗記の全体像と具体的な勉強方法
- 解法暗記に適した参考書や問題集
- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略
また、解法暗記を勉強する前に、数学の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!
数学の勉強法の詳しい情報についてはこちら
解法暗記の攻略法
解法暗記とは?

数学の勉強法は「概要把握」「解法暗記」「問題演習」「計算練習」という段階に分類できます。
概要把握
高校1〜3年生までの数学単元を一通り理解する段階です。ここでは教科書の例題レベルの問題が自力で解けるようになることをゴールとします。
解法暗記
入試で出題される典型的な解法を用いた問題を即座に解けるようにする段階です。 二次関数のグラフを作図するためには、展開と因数分解の知識のもとに成り立つ平方完成の知識と、頂点と軸に関する理解が必要であります。 世の中の入試問題は武器と武器の組み合わせで新たな1題が作られており、東大・京大をはじめとした最難関大学でも、名前のついた解法に因数分解することが可能です。 最小の努力で難関大の入試の因数となる解法を覚えるのがこの段階の目標となります。
問題演習
難関大学入試レベルの問題で合格点を取れるようにする段階です。 解法暗記の解法を2つ以上使用する問題を主に取り扱います。 武器をただ持っているだけでは問題を解き切ることはできません。その武器が使えるシーンや解法の組み合わさり方を見抜くためには、実際に問題演習をしながら思考プロセスを身に着けていくことが重要です。
計算練習
計算のスピードと精度を高める段階です。 解法を立てる力と、計算を実行する力は別物です。 概要把握~問題演習はいずれも解法を立てられるようになることが目的の学習段階であるため、通年で計算練習を導入して実行力を養成します。
上から順に数学の基礎を積み上げていき、最終的に入試問題にも対応できる数学力を身につけていく必要があります。
解法暗記は次の学習段階である問題演習を進めていく上でも最も重要なステップと言えます。なぜなら問題演習は解法の選択や組み合わせの練習を行う学習段階だからです。そして問題演習の出来はそのまま入試数学における得点に直結します。つまり、この段階での完成度が、その後の学習効率、ひいては入試数学の得点力を決定づけます。また、概要把握の理解度を確認できるとい学習段階という意味合いでも解法暗記が入試数学の道標であることが伺えます。
完璧を求めすぎず問題演習に移行しよう
そして解法暗記を進めていく上で重要なのが一周目で完璧を求めすぎないことです。
出題範囲である分野の解法を一通りインプットできたら、解法暗記二周目問題演習と並行していくことをお勧めします。
アウトプットを通じてインプットを整理していくことで学習効果が高まります。

学習段階を並行して学習効果を高める手法は他の科目でも効果的ですよ!
解法暗記の段階
解法暗記は、「基礎解法暗記」と「標準解法暗記」の2つの段階に分けることができます。
基礎解法暗記
この段階のゴールは、教科書の章末問題や、入試で出題される最も基礎的な問題の解法を完璧にすることです。 数学の勉強を始めたばかりの人や、苦手意識がある人は、まずこの段階から始めることを強く推奨します。ここで解法のパターンを身につけておくことで、その後の標準的な問題にもスムーズに対応できます。
標準解法暗記
基礎解法暗記を終えた人が次に進む段階です。 ここでは、同一単元の複数の知識を組み合わせる問題や、より複雑な入試標準問題の解法を身につけることを目指します。 志望校のレベルによっては、この段階を完璧にすることで合格点が狙えることもあります。
解法暗記を学ぶ3つのメリット

解法暗記の学習は、数学の知識を実戦で使える「真の数学力」へと引き上げるための重要なステップです。以下のような大きなメリットが得られます。
1. 問題を見た瞬間に解法の糸口を見つけられる
入試問題は、見た目が複雑でも、多くは基礎的な解法の組み合わせで構成されています。解法暗記をすることで、問題のキーワードや構造から、どの解法を適用すべきかを瞬時に判断できるようになります。これは、数学の問題を解くスピードと正確性を飛躍的に向上させます。
2. 知識が体系的に整理される
解法暗記は、単に問題を覚えるだけでなく、「なぜその解法が成り立つのか」という原理を理解しながら進めます。これにより、バラバラだった知識が互いに結びつき、頭の中で体系的に整理されます。この状態は、初見の問題を解くための応用力を養う土台となります。
3. 記述問題で部分点を確実に取る力がつく
入試の記述問題では、最終的な答えだけでなく、そこに至るまでの論理的な過程も評価されます。解法暗記を通じて、模範解答の論理の流れを身につけることで、解答を分かりやすく、かつ正確に記述する力が養われます。これにより、たとえ完答できなくても、部分点を確実に積み重ねることができます。
解法暗記の勉強法
先ほど説明した通り、解法暗記は概要把握を基に成り立つ学習段階になります。
まだ、概要把握の学習が進んでいない方は、まず以下の記事を参考に数学の基盤を固めることをお勧めします。
数学の概要把握の詳しい情報についてはこちら

次に具体的な「解法暗記の勉強法」について紹介します。
STEP 1. 問題を分類し、解法の「型」を特定する
まずは、問題を解き始める前に、その問題がどの分野のどのタイプの問題かを見極めましょう。例えば、「最大最小問題」「証明問題」「ベクトルを使った図形問題」など、問題のカテゴリを意識します。そして、そのタイプに共通する基本的な解法(アプローチの「型」)を特定することを試みます。
STEP 2.模範解答の思考プロセスを完全に吸収する
問題を解いたら、自分の解答と模範解答を比較し、思考プロセスにギャップがないかを徹底的に分析します。特に、「なぜこの式変形をしたのか」「なぜこの補助線を引いたのか」といった、解答の裏側にある論理を理解することが重要です。単なる丸暗記ではなく、この思考プロセスを自分のものにする意識を持ちましょう。
STEP 3. 解法の「型」を完璧に再現する
解説を理解したら、何も見ずに、解法の「型」と論理の流れを完璧に再現する練習をします。類題を解く際に、「これはあの問題の型だな」とすぐに判断し、スムーズに解答が書けるようになるまで、繰り返し演習してください。この段階での「再現性」が、次の「実践演習」で初見の問題に対応するための基礎力となります。
- 問題を分類し、解法の「型」を特定する
- 模範解答の思考プロセスを完全に吸収する
- 解法の「型」を完璧に再現する
おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

現論会でも使用している、【2025最新版】志望校レベル別数学の解法暗記におすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します。
ここでは、解法暗記の学習に特化した、おすすめの参考書とその効果的な使い方を、具体的な学習ステップに沿って解説します。
東京一科、早慶レベル(偏差値70~)
🔹 難関大レベルを目指し、共通テスト9割以上を狙いたい人
🔹 難関大二次試験で合格点を取れるようにする
おすすめ参考書 1(標準解法暗記)
1対1対応の演習
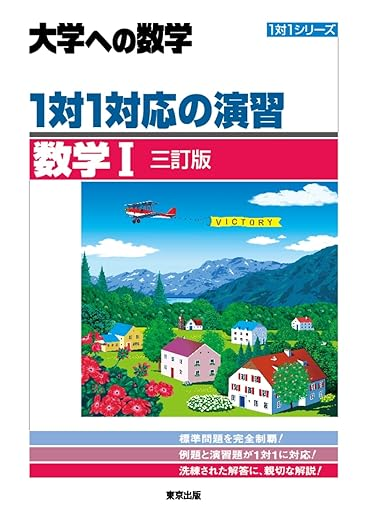

1対1対応の演習は東京一科、早慶志望の受験生の中でも数学を得点源にしたい、青チャートなどの網羅系参考書で数学の概要把握が定着している方におすすめです!
学習戦略
「一対一対応」の思想に基づき、似ているようで異なる発想を要求する良問が並んでいます。解法を深く理解し、思考力を鍛えることに特化しています。
- 【STEP 1. 問題を分類し、解法の「型」を特定する】
- 『1対1対応の演習』は、一見似た問題でも異なる解法を要求することがあります。まずは、問題のタイプを正確に見抜き、「この問題は一見○○のようだが、実は○○の解法を使うべきだ」といった識別眼を養います。この段階で、問題の奥深さを理解することが重要です。
- 【STEP 2.模範解答の思考プロセスを完璧に吸収する】
- 解答を見た後、「なぜこの解法がベストなのか」という選択理由を深く考察します。他の解法と比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを分析することで、応用問題で適切な解法を選択する力が身につきます。
- 【STEP 3.解法の「型」を完璧に再現する】
- 単に解答を覚えるのではなく、解法の「論理の流れ」を自分の言葉で説明できるように練習します。これを完璧に行うことで、初見の応用問題にも対応できる柔軟な思考力が身につきます。
似た問題のタイプを識別するためには言語化が突破の鍵になります!!
あわせて読みたい
おすすめ参考書2(標準解法暗記)
文系の数学 実戦力向上編
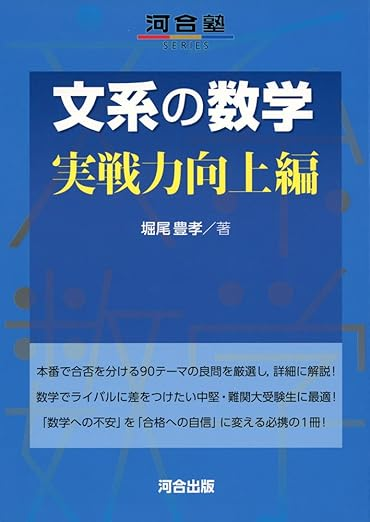

文系の数学 実戦力向上編は東京一科、早慶志望の受験生で解法暗記を着実に攻略していきたい方におすすめです!
学習戦略
入試の基礎〜標準レベルの典型的な問題を効率的に学べます。解説が丁寧で、独学でも解法の型を身につけやすい構成です。
- 【STEP 1. 問題を分類し、解法の「型」を特定する】
- 問題を解き始める前に、その問題が「微分・積分」の「最大最小問題」なのか、「数列」の「漸化式」なのかなど、問題のタイプを意識します。この段階で、どの解法を使うべきか見当をつける訓練をしましょう。
- 【STEP 2. 模範解答の思考プロセスを完璧に吸収する】
- 解答を見た後、単に答えを覚えるだけでなく、「なぜこの解法が選ばれたのか」という理由を、解説を読み込んで理解します。特に「精講」のセクションを熟読し、解法の背景にある数学的な思考を学び取りましょう。
- 【STEP 3. 解法の「型」を完璧に再現する】
- 一度解いた問題は、何も見ずに解答を最初から最後まで完璧に再現できるか確認します。もし詰まる箇所があれば、その解法はまだ身についていません。この再現練習を繰り返すことで、解法を長期記憶に定着させ、本番でスムーズに解答する力を養います。
問題を解く前にタイプを分析する習慣を身につけましょう!!
あわせて読みたい

もし上記のような標準解法暗記の参考書に取り組んでみて壁を感じた場合は次に紹介する基礎解法暗記の参考書を優先して攻略するといいかもしれません!
地方国公立、GMARCH理科大、関関同立レベル(偏差値~60)
🔹 対象: 基礎はある程度できていて、共通テストで8割を目指したい人
🔹 目標: 共通テスト8割、二次試験の基本問題を解けるようにする
おすすめ参考書(基礎解法暗記)
文系の数学 重要事項完全習得編
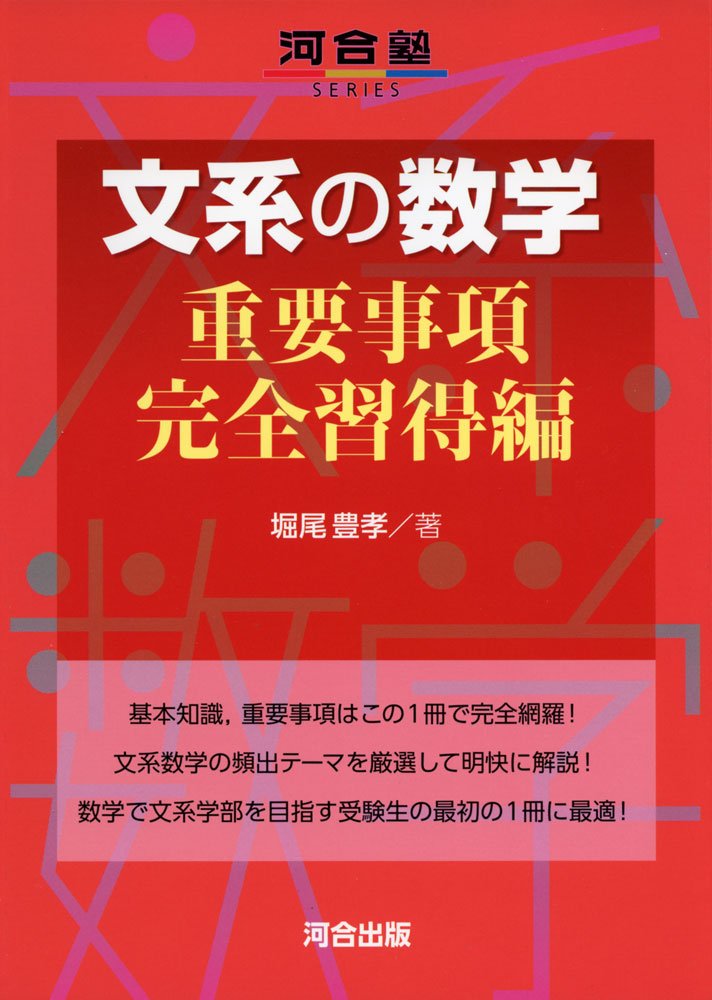
基礎問題精講
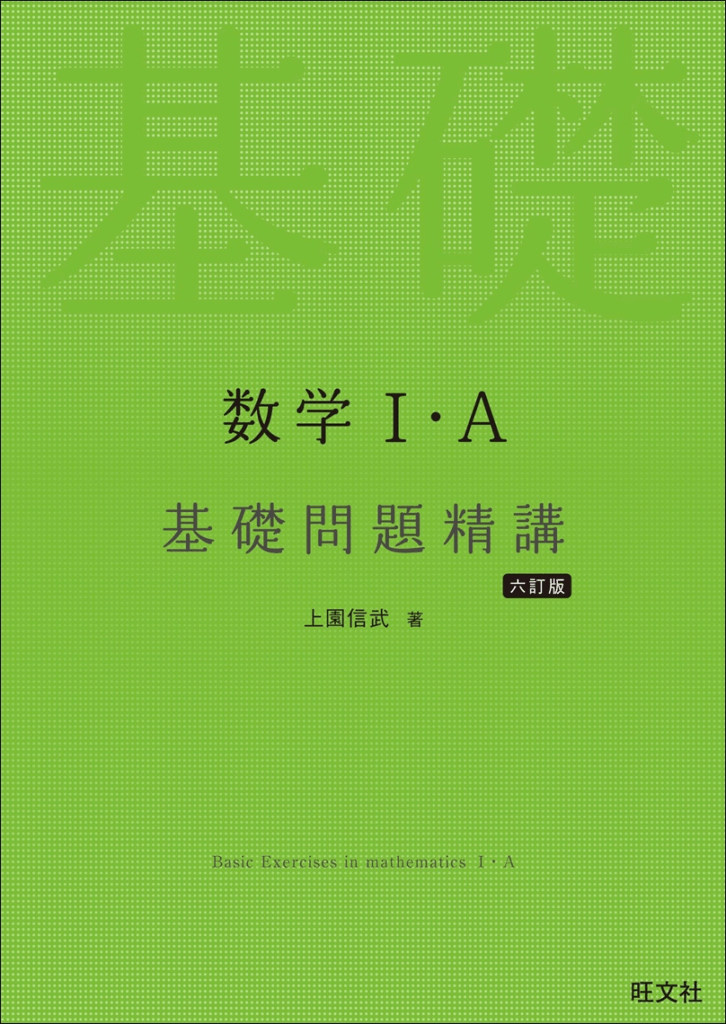

この段階では、数学の「解法」をインプットし、基本問題で確実に得点できる力を養います。
学習戦略
文系の数学 重要事項完全習得編も基礎問題精講のどちらも入試の基礎〜標準レベルの典型的な問題を効率的に学べます。解説が丁寧で、独学でも解法の型を身につけやすい構成です。2冊の違いや特徴は以下の通りです。
- 『文系の数学 重要事項完全習得編』: 誘導が少なく、自分で考える力が身につきます。問題数が少ないため、短期間で1周できます。
- 『基礎問題精講』: 誘導が丁寧で、数学が苦手な人でも挫折しにくいです。問題数が多いため、網羅性が高いです。
- 【STEP 1. 問題を分類し、解法の「型」を特定する】
- 問題のキーワードや見た目から、どの単元のどの問題かを見抜く訓練をします。これにより、基礎的な問題に対する反射的な対応力が身につきます。
- 【STEP 2. 模範解答の思考プロセスを完璧に吸収する】
- 解答を見る前に自分で考え、その後で模範解答の「考え方」や「論理」を丁寧に読み込み、完璧に理解することを目指します。
- 【STEP 3. 解法の「型」を完璧に再現する】
- 解説を理解したら、何も見ずに解答を再現できるまで、繰り返し演習します。この反復練習により、解法が長期記憶に定着し、どんな基礎問題にも対応できるようになります。
解答を再現できるまでの繰り返し演習が入試数学の突破口!!
まとめ
解法暗記は、数学の「型」を身につけ、問題を解くための武器を揃える重要なステップです。この記事で解説したように、「問題の解法を理解し」「完璧に再現し」「定期的に復習する」という3つのステップを丁寧に実践することが、解法暗記攻略の最短ルートです。
あなたに合った一冊から始めよう
あなたの現在の学力レベルに合わせて、最適な参考書から学習を始めましょう。
現論会としては
- 地方国公立、GMARCH理科大志望の受験生には『文系の数学 重要事項完全習得編』や『基礎問題精講』
- 東京一科、早慶志望の受験生には『1対1対応の演習』や『文系の数学 実戦力向上編』
を推奨しています。
また、それぞれの参考書で、「問題を見た瞬間に解法の糸口を見つけられる」、「知識が体系的に整理される」、「記述問題で部分点を確実に取る力がつく」
という3つのステップを丁寧に実践することが、解法暗記攻略の最短ルートです。
解法暗記のその先へ
解法暗記を一周したら、次は解法の選択や組み合わせの練習を行う学習段階である問題演習に移りましょう。
なぜなら問題演習は解法の選択や組み合わせの練習を行う学習段階であり、問題演習の出来はそのまま入試数学における得点に直結するからです。
また解法暗記のインプットを定着するには問題演習が必須なので、この二つの学習段階をバランスよく学習することが得点力につながります。
つまり、解法暗記を完璧にするよりも先に問題演習に着手すると効率よく理解度の深い学習できます。

問題演習に早めに移行し入試問題に触れる時間を増やすことはこれまでのインプットの定着が早くなります!
あわせて読みたい
もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。
あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博
開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。
現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。
「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。