【受験期の親の関わり方】子どもの学力を伸ばすために、親が「すべきこと・してはいけないこと」
更新日 : 2025年8月19日
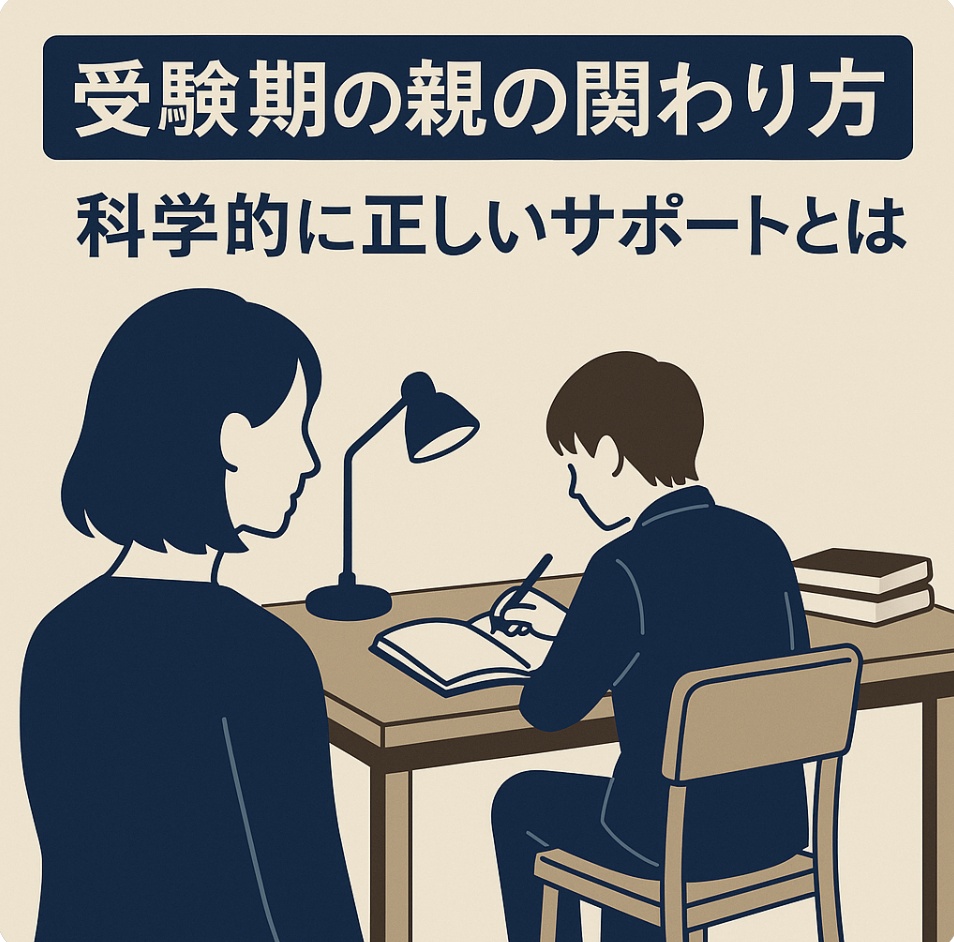
「うちの子、やる気がないように見えるけど大丈夫?」「口出しすべき?それとも静観?」
受験期における親の関わり方に悩む保護者は少なくありません。過干渉も放任も逆効果と言われる中、どのような距離感が最適なのでしょうか?
本記事では、教育心理学や脳科学の研究をもとに、子どものやる気と学力を引き出す「正しい親の関わり方」について詳しく解説します。
現論会の現場でも実感している、成果につながる保護者のサポート方法をお伝えします。
親の関わり方が成績に影響する?科学的な根拠とは
親の「関心」と「期待」が子どもの学力を伸ばす
アメリカの教育学者ホプキンズら(2011)は、「親の教育への関心・期待が、子どもの学力や進学意欲に強い影響を与える」と報告しています。
特に重要なのは「成績」よりも「努力」に焦点を当てる姿勢です。
- NG:「もっと良い点取れないの?」
- OK:「毎日頑張ってるの、見てるよ」
努力を認める声かけは、自己効力感(=自分はできるという感覚)を育て、継続的な学習を促します。
受験期に親が「してはいけない」NG行動
① 勉強を監視する
親が常に学習状況をチェックしたり、時間を計ったりすると、子どもは「管理されている」と感じ、内発的動機(=自分からやる気)が下がります。
参考:Deci & Ryan(2000)の自己決定理論
「人は自分で決めて動くときに最もモチベーションが高まる」
② 他人と比較する
「〇〇ちゃんはもう過去問やってるって」などの比較は、自己肯定感を下げ、逆効果に。親が不安になる気持ちは当然ですが、焦りの感情は子どもに伝染します。
では、親はどう関わればいいのか?効果的な3つのサポート
① 安心できる環境を整える
- 「話しかけられない時間帯」を子どもと決める
- 夜食や飲み物でのさりげない応援
- 静かで落ち着いた学習環境の確保
親ができる「環境支援」は、学習効率の底上げに直結します。
② 目標設定を一緒に考える
現論会では、志望校から逆算した「計画学習」を行いますが、これは親子間でも有効です。
「この大学で何をしたいの?」という対話を通じて、子どもの内側からやる気を引き出すことができます。
③ 日々の小さな努力を認める
「机に向かった」「模試の解き直しをしていた」など、小さな行動に目を向けてください。
成績が出る前でも、行動を認めることで「習慣化」と「自信形成」につながります。
実際にあった「親の関わり方」の成功例
ある保護者様が「毎晩、一言だけポジティブな声かけをする」と決めたところ、生徒の学習時間が月に10時間以上増加し、模試偏差値も大幅にアップしました。
親の言葉が「安心感」になり、コーチングとの相乗効果で、子どもが自ら動くようになった好例です。
親は「支える立場」であることを忘れずに
受験は、親子にとって試練の時期ですが、最も大切なのは「子ども自身が歩む」ことです。
親ができるのは、後ろからそっと背中を押すこと。
焦らず、比べず、信じて待つ――その姿勢こそが、子どもにとって最高のサポートになります。
現論会では「自ら勉強する力」を育てます
現論会では、お子さま自身が決めた目標に向けて、計画的に学習を進めていけるよう、プロのコーチが伴走します。
他人に言われてやる勉強ではなく、「自分で決めたから頑張れる」学習習慣を、一緒に育てていきませんか?
「うちの子に合うサポートってどんなもの?」とお悩みの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
参考文献
- Hopkins, K., et al. (2011). Parental Involvement and Academic Achievement: A Meta-analysis. Review of Educational Research, 81(2), 203–238.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
- 山口裕幸(2007)『子どもをやる気にさせる親の習慣』PHP研究所
- 文部科学省(2019)『保護者の学習支援のあり方に関する調査研究』
