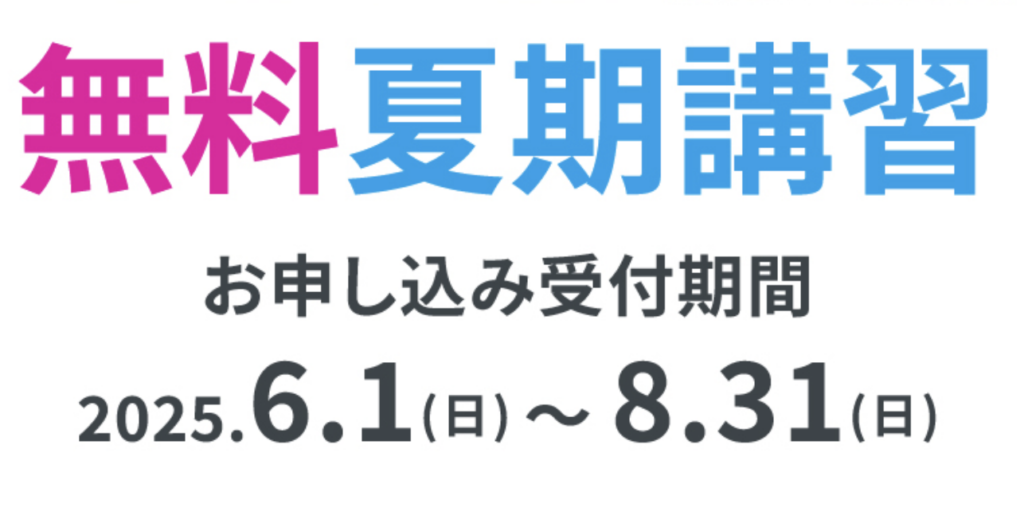高1・高2から始める難関大合格戦略【出遅れ防止】
更新日 : 2025年6月16日
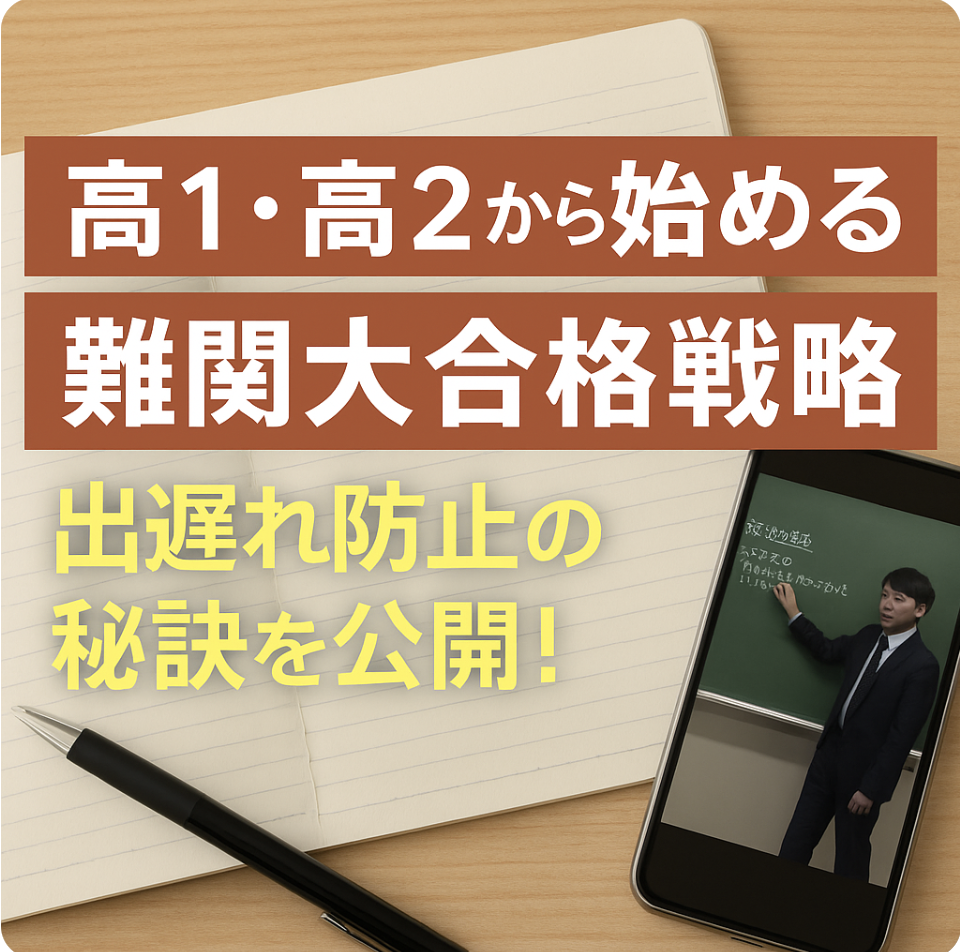
「受験勉強って、高3から始めればいいんでしょ?」――そんなふうに思っていませんか?
確かに本格的な受験モードに入るのは高3ですが、難関大学合格者の多くは、高1・高2からすでに”受験準備”を始めています。
この記事では、早い時期から何を意識すればよいのか、学年別の戦略と参考書学習の具体例を、コーチング型学習塾「現論会熊谷校」の視点からわかりやすく解説します。
なぜ「高1・高2」が勝負の分かれ目なのか?
難関大合格者の8割は「高2までに基礎完成」
難関大合格者を分析すると、東大・京大・早慶・国立大合格者の多くが高2終了時点で基礎科目を一通り終えていることがわかります。
特に英語・数学は積み上げ科目。高3から始めて間に合うのは、基本的に中堅大までと考えるべきです。
高3は「仕上げ」の時期であり「スタート」ではない
高3では、過去問演習や実戦演習、志望校対策に集中するのが理想です。
そのためには、高1〜高2のうちに「基礎の習得」と「勉強習慣の定着」を済ませておくことが必須となります。
高1、高2のうちにやるべき3つのこと
①英単語と文法の基礎を固める
高校英語は「知識がなければ読めない」教科です。
高1では以下のような基礎を確実におさえましょう:
- 英単語帳(例:『システム英単語』Basic〜1章)
- 英文法
②数学I・Aの理解を深める(教材例あり)
高1数学でつまずくと、その後のⅡB・ⅢCに進めなくなります。
おすすめの勉強法は以下の通りです:
- スタディサプリ(高1数学講座):基礎概念の理解に最適。短時間で「わかったつもり」を防げます。
- 入門問題精講(数学I・A):基本~標準問題までを効率的に演習できます。
学校の進度に合わせて、動画で理解→問題集で演習→コーチングで管理の流れを作ると効果的です。
③学習習慣の確立
毎日1.5〜2時間の自学自習を目指すこと。
「塾に通っている=勉強している」ではありません。参考書を使った能動的な勉強がカギです。
高2のうちにやるべき3つのこと
①共通テストレベルの読解力・計算力をつける
英語長文は、共通テストレベルのものから段階的にレベルアップを目指しましょう。
「文の構造を意識して読む」「日本語に訳さずに内容をつかむ」など、読み方の質を高める練習が重要です。
また、数学は適切な参考書で解法パターンを習得し、計算力と正答率を磨きます。
②苦手科目の発見と補強
「高3になったらやる」では遅すぎます。
今のうちに模試を活用して苦手科目を分析し、参考書・映像を活用して修正する力を養いましょう。
③志望校と学部の方向性を固める
「文理選択したけど、将来のイメージが曖昧」なままだと、モチベーションが続きません。
学部研究や大学のオープンキャンパスへの参加を通じて、自分の進みたい道を言語化しましょう。
現論会熊谷校でできるサポート
①生徒一人ひとりの志望・性格に合わせた計画作成
勉強が得意な子も、苦手な子も、それぞれの「今」に合わせて最適な勉強ルートを一緒に設計します。
②毎週の進捗確認・モチベーション維持
「やってるつもり」ではなく、「確実に進んでいる」と実感できるサイクルを構築します。
③高1・高2からの学習習慣づけ
週に一度の面談で習慣化をサポート。学校・部活・趣味との両立も可能です。
よくある質問(FAQ)
Q. 部活が忙しくて時間が取れません。
→スキマ時間を活用した動画学習+参考書学習の組み合わせを提案します。1日30分からでもOKです。
Q. まだ志望校が決まっていません。
→面談を通して興味や性格をヒアリングし、大学・学部の情報提供を行います。
Q. 通塾なしでも参考書で合格できますか?
→できます。ただし「やり抜く力」や「計画修正力」が必要です。現論会は生徒とともにやり切れるよう伴走をします。
締めのメッセージ
高1・高2の時間の使い方が、受験の9割を決める――。
それが現論会でたくさんの生徒を見てきた私たちの結論です。
「そろそろ何か始めなきゃ」と思っているあなた。一歩踏み出せば、受験はもう始まっています。
そして今年も、現論会熊谷校では6月から夏期講習がスタートしています。
「何から始めればいいかわからない」「自分だけで続けられるか不安」
そんな生徒のために、参考書を使った個別の学習計画と、毎週のコーチング面談で徹底サポートします。
特に夏は、まだ差のついていない今こそ「差がつく期間」。
高1・高2のこの夏をどう過ごすかで、受験の景色が大きく変わります。
まずは無料の学習相談からでも構いません。
現論会熊谷校で、あなたにぴったりの“勝てる夏”を一緒にデザインしてみませんか?
🔽 夏期講習・無料相談はこちらから