「どうして勉強をするのだろう?」と悩む子どもに寄り添う親のヒント
更新日 : 2025年7月2日
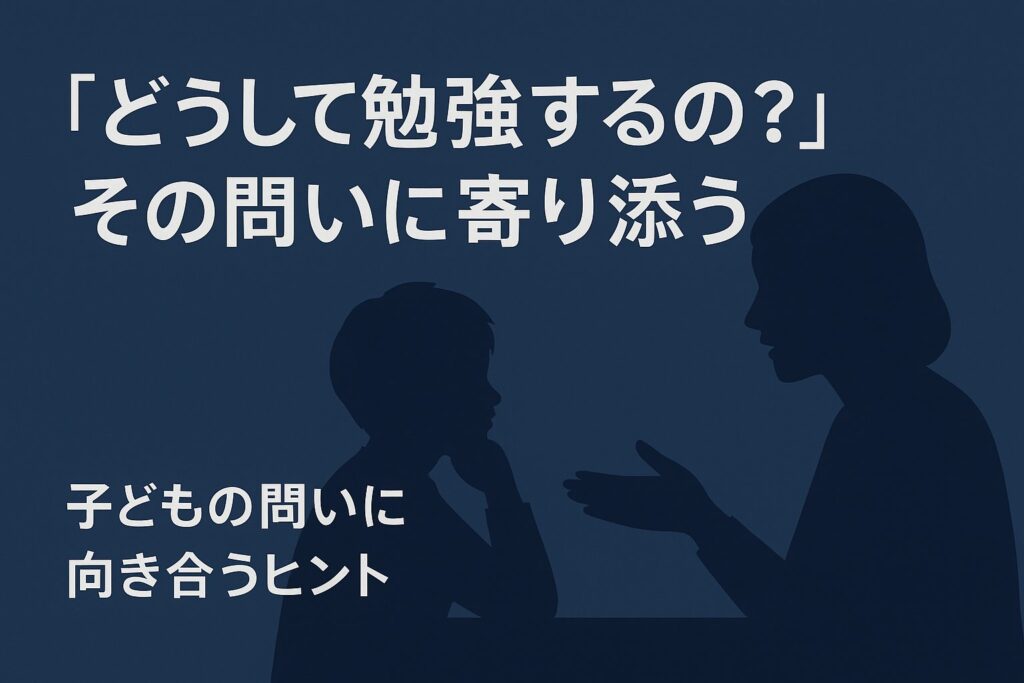
「勉強って何のためにするの?」
お子さんからそう問いかけられて、うまく答えられずに困った経験はありませんか?
この問いは、受験勉強の真っ只中にいる高校生にとっても、保護者にとっても避けて通れないテーマです。
しかし「勉強は将来のため」と一言で片付けてしまうと、子どもはかえって納得できず、やる気を失うこともあります。
今回は、学習塾として多くの生徒をサポートしてきた現論会の視点から
「どうして勉強するのか」を親としてどう伝え、支えるか
についてお伝えします。
子どもが「なぜ勉強するのか」と悩む背景
成績や進路のプレッシャー
高校生になると、定期テストや模試、志望校の選択など「点数で評価される世界」に一気に飛び込みます。
「何のために勉強しているのか分からないのに、結果だけ求められる」
そんな疑問やモヤモヤを抱く子はとても多いのです。
SNSや多様な価値観の影響
今の10代はSNSを通じて、学校の成績以外でも成功する人を目にする機会が多いです。
「勉強だけが人生のすべてじゃない」という正論も簡単に手に入ります。
その一方で、夢や目標がまだ定まらない段階で「何のための勉強か」を見失いやすくなっています。
親として伝えたい「勉強の意味」
勉強は選択肢を広げる道具
「勉強は人生の選択肢を増やすためのもの」という考え方は、非常にシンプルで説得力があります。
子ども自身が将来やりたいことに出会ったときに、その扉を開ける鍵になるのが勉強です。
大人がよく知るように、基礎学力がないと進めないルートもあります。
「未来の選択肢を奪わないために、いま勉強しているんだよ」と伝えてあげてください。
知識や経験は自信の源になる
努力を重ねて知識を増やすことは、自己肯定感を高めます。
「わかる」「できる」という体験は、どんな小さな成功体験でも大切です。
これは子どもの自己効力感を育て、勉強以外の挑戦にも活かされます。
勉強は単に受験のためだけではなく、自分を信じられる土台にもなるのです。
親ができるサポートとは
価値観の押し付けをしない
「勉強しなさい」と繰り返すだけでは、子どもはますます反発してしまいます。
「どうして勉強したくないのか」を聞き出し、気持ちを受け止めることがまず大切です。
一方的に正論を押し付けるのではなく、一緒に考える姿勢を見せましょう。
学習計画を共有してあげる
現論会では参考書をベースにした計画学習を提案していますが、その計画を一緒に見守る親の存在も大きな意味を持ちます。
「進んでるね」「ここは大丈夫?」と声をかけるだけで、子どもの孤立感は大きく減ります。
特に受験期は不安が高まりやすいため、計画を共有し支えるコミュニケーションが効果的です。
現論会のコーチングで「自分で学ぶ意味」に気づく
現論会熊谷校では、参考書を用いたコーチング型の学習支援を行っています。
私たちは「生徒自身が計画を立て、進捗を振り返り、必要に応じて修正する」経験を大切にしています。
このプロセスが「勉強の意味」を自分で見出すきっかけになります。
「なぜ勉強するのか分からない」という悩みは、学び方を変えることで解消できることも多いです。
もしお子さまが同じように悩んでいたら、一度ご相談ください。
まとめ
勉強の意味を問うのは、大人でも難しい問いです。
ですが、その問いに向き合うプロセスこそ、子どもが大人へ成長していく大切な一歩です。
現論会熊谷校では、保護者の皆さまと一緒に、お子さまの「自分で考えられる力」を育てるお手伝いをしています。
ぜひお気軽にご相談ください。
