📘 『岡本のここからつなげる古典文法ドリル』|難関大受験専門塾 現論会
更新日 : 2025年11月7日
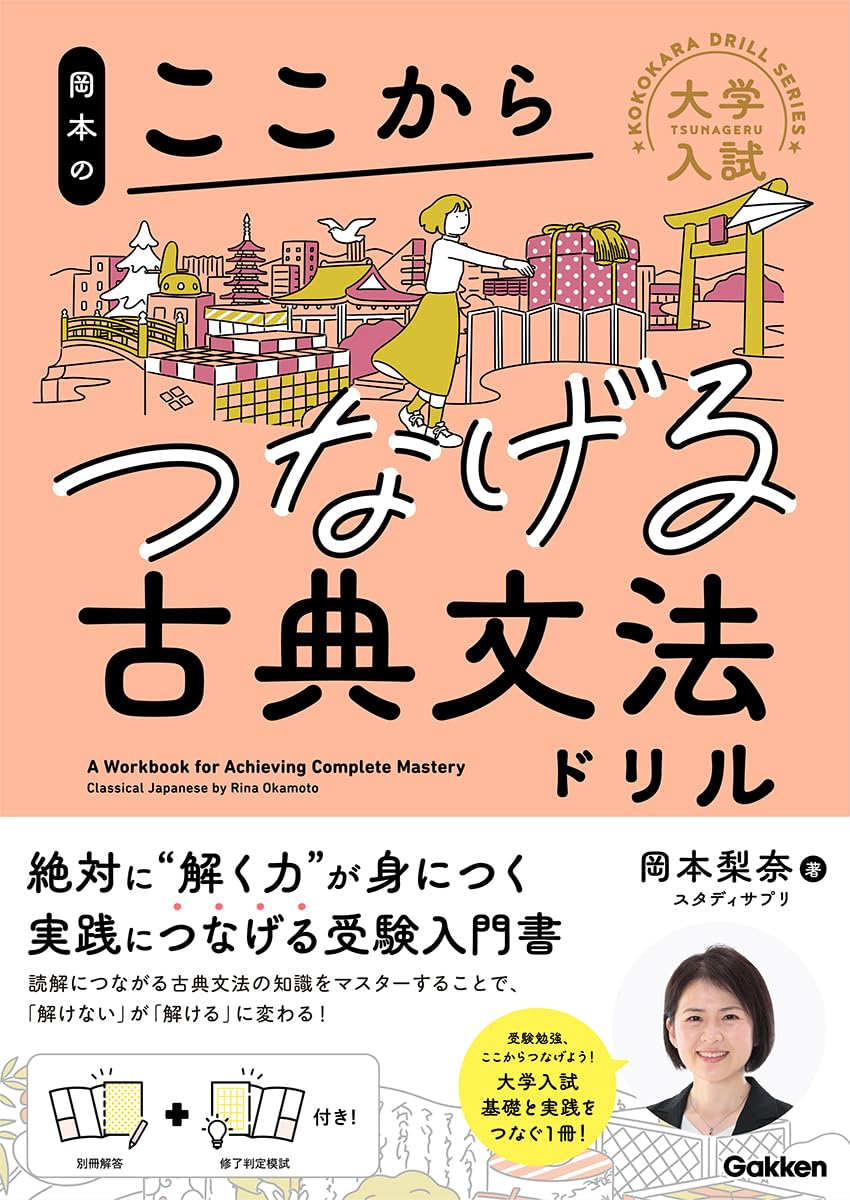
大学受験生の皆さん、学習は順調に進んでおられるでしょうか。
「『岡本のここからはじめる古典文法ドリル』は終わらせた」
「助動詞の活用や意味は、一通り覚えたと思う」
「それなのに、いざ文章題になると、誰が何をしているのかさっぱり分からない…」
多くの受験生が、基礎文法を学んだ「次」のステップでこのような大きな壁にぶつかります。文法問題を解くための知識と、文章を読み解くための力の間には、実は深い溝があるのです。
その「溝」を埋められずに、「古文はセンスだ」「結局、感覚で読むしかない」と諦めかけていませんか?
そのような「基礎は学んだが、読解につなげられない」と悩む受験生に、現論会が「次の一冊」として強く推奨したい参考書があります。
それが、スタディサプリで絶大な人気を誇る岡本梨奈先生による、
『岡本のここからつなげる古典文法ドリル』(学研出版)です。
今回は、なぜこのドリルが「文法知識」と「読解力」の架け橋となるのか、その理由を徹底的に、そして詳しく解説します。
本書が推奨される受験生
この参考書は、文法をゼロから学ぶための本ではありません。基礎を終えた人が、確実に次のステップへ進むための「接続」に特化した参考書です。
- 『ここからはじめる古典文法ドリル』を終えた受験生(※まずは前著で「品詞分解」「助動詞」の基礎を固めることが前提です)
- 助動詞の基礎は理解したが、「敬語」が苦手で後回しにしている方
- 文法はわかるが、「主語把握」など読解になると手が出ない方
- 「文法のための勉強」から「読むための勉強」へ移行したい初学者
- 他の文法書を終えたが、どうも読解に応用できている実感がない方
一つでも当てはまる方には、このドリルこそが読解力向上の突破口を開く一冊となるでしょう。
『つなげるドリル』の優れた点
なぜ、現論会が基礎の次にこのドリルを推薦するのか。それには明確な理由があります。前著が「0から1へ」の参考書だとしたら、本書は「1を10に」するための、非常に重要な役割を担っています。
ポイント①:最難関「敬語」を圧倒的に分かりやすく解説
多くの初学者が挫折する最大の関門が「敬語」です。
前著の『ここからはじめるドリル』では、あえてこの敬語をカットすることで、初学者の負担を減らす設計になっていました。
本書は、その「敬語」の解説からスタートします。
他の多くの参考書では、敬語は「助動詞の一部」や「重要単語」として他の単元と一緒くたに扱われがちです。しかし、本書では敬語を独立した章として手厚く扱っています。
「尊敬・謙譲・丁寧」の使い分けはもちろん、「誰から誰への敬意か」という入試で最も問われるポイントを、岡本先生ならではの分かりやすい解説でインプットできます。ここを乗り越えることが、古文読解の第一歩です。
ポイント②:「主語把握」など、読解に直結する技術を学ぶ
本書の最大のテーマは、その名の通り「つなげる」ことです。
古文が読めない最大の原因は、「主語が分からない」ことにあります。古文は日本語の特性上、主語が頻繁に省略されるため、「あれ、今これ誰が話してるの?」と迷子になりがちです。
このドリルでは、「文法知識を使って主語を把握する方法」を具体的に学びます。
例えば、「尊敬語が使われているから、主語は身分の高い人物だ」といった敬語からの推測や、「接続助詞『て』『で』の前後は主語が変わりにくい」といった文法ルールからの推測など、読解に即役立つ技術が満載です。
文法を「暗記するもの」から「読解の武器」に変える。そのための解説が非常に充実しています。
ポイント③:「修了判定模試」で「読める」レベルかを確認
学習を「やったつもり」で終わらせない工夫も万全です。
本書の最後には「修了判定模試」が付属しており、学んだ知識が本当に定着しているか、客観的にチェックできます。
この模試の秀逸な点は、単なる知識の穴埋め問題だけでなく、「短文解釈」のテストが含まれていることです。
これは、「本書で学んだ文法知識(敬語、主語把握など)を使って、短い一文を正確に訳せるか」を試すテストです。
ここで初めて、自分の知識が「読解に応用できるレベル」に達しているかを判断できます。ここで間違えた箇所こそが、ご自身の弱点です。徹底的に復習し、完璧にすることが求められます。
現論会推奨!『つなげるドリル』効果的な学習法
この優れた参考書を、どう活用すれば最も効率的に成績を上げられるか。現論会がその効果的な活用法をご紹介します。
① 1日1~2テーマを「毎日」継続する
基礎を終えたとはいえ、焦って一気に終わらせるのは推奨しません。
1日1テーマ、多くても2テーマ(30分~45分程度)で十分です。大切なのは、毎日古文に触れて「文法を読解に使う感覚」を養い、鈍らせないことです。薄いドリルなので、毎日続ければ必ず修了できます。
② 必ず「2周」実施し、「説明できる」レベルを目指す
1周目は、解説を読み、問題を解いて内容を理解することが目的です。
2周目は、「なぜその答えになるのか」を自身の言葉で説明できるようにすることを目的とします。
例えば、「なぜこの文の主語はAだと判断できるのか?」「それは、ここにBという尊敬語が使われており、選択肢の中で身分が高いのはAしかいないからだ」といった具合に、解答の根拠を論理的に説明できる状態になって、初めて「読解に応用できる知識」になったと言えます。
③ 修了後は『読む』ための参考書へ接続する
このドリルで文法を「つなげる」感覚を掴んだら、いよいよ本格的な読解演習です。
『1冊読むだけで古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本』など、読解の「読み方」や「解き方」を体系的に学ぶ参考書に進みましょう。
本書で学んだ主語把握の方法や敬語の知識が強力な土台となり、驚くほどスムーズに読解演習に入っていけるはずです。
💡 まとめ|『つなげる』一冊が合否を分ける
大学入試の古文は、「単語」と「文法」の基礎を固めた後、いかに「読解力」に変換できるかで点数が決まります。
多くの受験生は、その「変換」がうまくいかず、「文法は知っているのに読めない」という状態のまま伸び悩んでしまいます。基礎(1冊目)と演習(2冊目)の間には、見えない「溝」があるのです。
『岡本のここからつなげる古典文法ドリル』は、その溝を埋めるために特化した、まさに「1.5冊目」とも言うべき、非常に重要な一冊です。
「文法の勉強は終わったはずなのに…」と立ち止まっている受験生は、ぜひこのドリルを手に取ってみてください。岡本先生の分かりやすい解説が、あなたの知識を「わかる」から「読める」に確実に引き上げてくれるはずです。
🎥 【現論会×岡本梨奈先生】古典文法はまずは”ここから”!『ここから』シリーズについて著者が解説!
志望校合格への最短ルートを確立しませんか?
「この参考書は、いつまでに終わらせればよいのか?」
「自身の志望校では、次に何をやるべきか?」
現論会では、生徒一人ひとりの現状と志望校から逆算した、受験生一人ひとり専用の「年間学習計画」を作成します。
何となく勉強するのではなく、毎日「何を」「どこまで」やれば合格できるかが明確になります。それが現論会のコーチングです。
現論会厚木校では、学習に関するご相談を無料で承っています。フォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。
本校は、保育園 KIDS SMILE LABO(2F)、レストラン 2343 FOOD LABO(3F)が入るビル4階にございます。上質な環境で、学習に集中したい方におすすめです。
📍 厚木市旭町1-7-3 4F(Google Maps)
