大学は研究機関 〜書籍『研究の育て方』から学ぶ、研究の構成要素
更新日 : 2025年4月17日
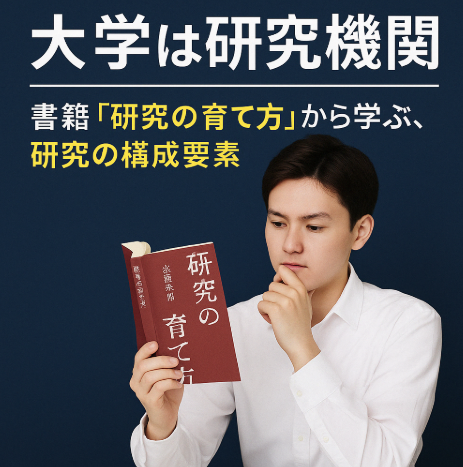
大学とは何をする場所でしょうか?
「勉強するところ」「専門知識を身につけるところ」──それも正解です。しかし本質的には、大学は研究機関です。入学してから初めて気づく人も多いのですが、大学の授業や課題の多くは「研究的な姿勢」を育むために設計されています。
「研究」という言葉を聞くと白衣を着た「科学者」のイメージを持つ方もいるかも知れませんが、現状からどうすれば良い方向へ行くのか?を考え続ける点で見ると、社会人・職人・医療人など、多くの仕事に当てはまる能力だと思います。
今回は、書籍『研究力の育て方』(近藤克則著)から、研究に必要な力を整理しながら、受験生やこれから大学で学ぶ人たちに役立つ考え方をご紹介します。
書籍『研究の育て方』とは?
本書は、研究のゴールとプロセスを「見える化」しながら、必要なスキルを段階的に解説しています。
これから研究者を目指す人だけでなく、論理的に物事を考えたいすべての人に役立つ一冊です。
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/93388

研究力の構成要素(1/2)〜計画と実行力
まずは、研究の初期段階で求められる力です。
- 専門知識: 自分の研究領域を深く理解する
- 読む力: 英語文献を含めた先行研究を読み解く力
- ゴール設定力・構想力・デザイン力: 研究の目的を明確にし、設計できる力
- 仮説設定力: 研究の出発点となる仮説を立てる力
- 計画策定力: 実現可能な研究計画を立てる力
- マネジメント力・段取り力: 締め切りを守り、計画的に進める力
- 発見する力・分析力: 集めたデータから新しい知見を引き出す力
- 統計解析力: 数量的な裏付けを取る基礎的な力
- 書く力: 分析結果を記述し、論理的に説明する力
研究力の構成要素(2/2)〜まとめる力と人間力
次に、研究をまとめ、発信するための力です。
- 要約力: 言いたいことを簡潔にまとめる力
- 考察力・コメント力: 結果の原因や意義を深く考える力
- ストーリーを作る力・プレゼンテーション力: 人にわかりやすく伝える力
- 信じる力・軌道修正力: 仮説や自分自身を信じる力と、必要に応じて軌道修正できる柔軟性
- 努力・根気: コツコツと積み重ねる忍耐力
- 批判的に吟味する力: 先行研究や結果を冷静に検証する姿勢
- 人を組織する力: 仲間と協力しながら研究を進める力
現論会で育む「研究力の土台」
ここまで読んでくださった方はお気づきかもしれません。
実は、こうした「研究力」は、大学受験の勉強の中でも育むことができるのです。
たとえば現論会では、学習日誌を使って日々のデータを蓄積し、自分自身の学習を分析することを習慣化しています。これにより、模試や勉強の記録から自己分析力が養われ、ゴールを設定し、進捗を考察し、必要に応じて計画を軌道修正する力が自然と身につきます。
さらに、現論会のコーチングでは、生徒が自ら考え、アウトプットすることを重視。思考を言語化する力や、自分自身を吟味する批判的な視点も育まれます。
これらは受験勉強だけでなく、大学進学後の研究活動、さらには社会に出たあとも必要とされるスキルです。
まとめ:受験は「研究力」を育てる最高の場
受験勉強は単なる知識の詰め込みではありません。考え方しだいで、「研究力」を鍛える絶好の機会になります。
大学受験という人生の大きな壁を突破するために必要な力は、まさに「研究の構成要素」と重なります。
そして現論会では、それらをバランスよく身につけられる学習環境を提供しています。
宇都宮校では皆さんの抱えている悩み、不安、今後の計画について何でも受け付けております。
ページ右側にある無料相談ボタンから問い合わせしてください!
▶LINEの友達追加でもご相談受け付けてます
