高1・高2の秋、受験を意識する子としない子の違い
更新日 : 2025年10月1日
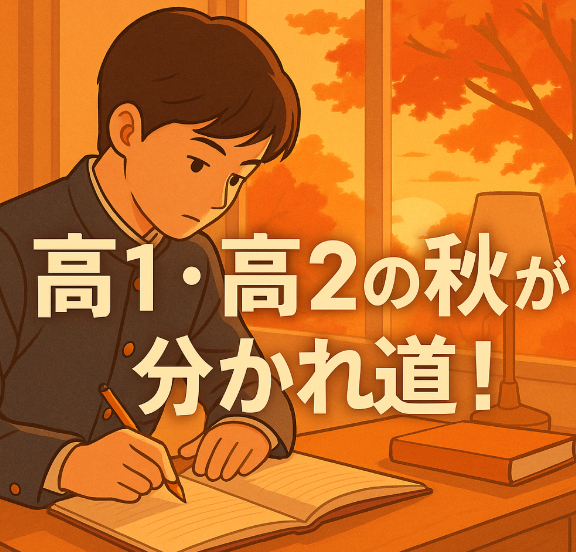
高校1年生・2年生の秋になると、クラスの中で「もう受験を意識して勉強を始める子」と「まだ部活や学校生活が中心の子」とに分かれていきます。保護者としては、
「うちの子は大丈夫なのだろうか?」
「周りに遅れを取っていないか?」
と気になる時期ではないでしょうか。
本記事では、実際の調査データや先輩たちの体験談をもとに、高1・高2で受験を意識している子とそうでない子の学習習慣の違い、早期にスタートするメリット、そして保護者ができるサポートについて解説します。
学習時間に現れる「意識の差」
高1・高2の勉強時間の現状
調査によると、高1では「平日1時間以下しか勉強しない」生徒が6割を超えています。一方で、すでに3時間以上勉強している生徒も2割ほど存在します。
高2になると状況は変化し、3時間以上学習する層が3割に増加。つまり、高2の秋を迎える頃に“受験を意識するかどうか”で学習時間に差が出始めるのです。
難関大合格者に共通する傾向
ある調査では、難関大合格者は高1の時点で平均+72時間、高2で+80時間、合計193時間も不合格者より多く勉強していたことが分かっています。高3になると全員が追い込みをかけますが、高1・高2からの積み重ねが後の合格を左右するのです。
早期に受験を意識するメリット
① 学習計画に余裕が生まれる
高2から受験勉強を始めると、基礎固めを終えた上で高3で過去問演習や応用対策に集中できます。逆に基礎が不十分だと、直前期に焦りながら取り組むことになり、得点力が安定しません。
② 苦手克服・得意強化の時間が取れる
高2のうちに苦手科目を克服しておけば、高3では志望校レベルの問題演習に余裕を持って挑めます。難関大合格者ほど「早くから準備したからこそ高いレベルに挑戦できた」と語っています。
③ 精神的な安定につながる
「もっと早く始めればよかった」という後悔は、合格者の声で最も多いものです。早期に準備しておけば、直前期の不安や焦りを軽減でき、模試や本番でも落ち着いて力を発揮できます。
データで見る「受験勉強の開始時期」
- 難関国公立・早慶合格者の約7割が高2の3月までに受験勉強を開始
- 最難関大合格者では約8割が高2までにスタート
- 難関私大(MARCH・関関同立など)合格者も約6割が高2までに開始
一方、高3から勉強を始めた層は不合格率が高いという調査もあります。つまり、高2までに受験モードに切り替えられるかどうかが、合否を分ける大きなポイントになるのです。
実体験から学ぶ「早期スタートの重要性」
- 先輩Oさん(難関大合格)
「残り1年を先のことと考えるのか、危機感を持って今始めるのかで結果は大きく変わる」 - 先輩Mさん(難関大合格)
「主要科目は直前では伸びにくい。高2のうちから毎日少しずつでもやるべき」 - ある保護者の声
「学習量よりも“習慣化”が重要。部活で忙しくても、毎日少しずつ机に向かう習慣が高3での伸びにつながった」
これらの体験談からも、「早く始めてよかった」ではなく「もっと早く始めればよかった」という後悔が圧倒的に多いことが分かります。
まとめ
高1・高2の秋は、大学受験を意識するかどうかで勉強時間に明確な差が出始める時期です。高2までに受験モードへ切り替えた生徒は、余裕を持った学習計画・基礎固め・精神的安定を得て、最終的な合格率も高くなっています。
保護者の皆さんにとっては、「今がスイッチを入れるタイミング」と考え、お子さんが自主的に学習習慣を築けるように声掛けや環境づくりでサポートすることが大切です。
現論会土浦校では、一人ひとりの状況に合わせて学習計画を立て、日々の習慣づけから受験まで伴走しています。高1・高2の秋だからこそできる一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。
受験受験相談 実施中!
「今の学習法で成績が伸びるか不安…」
「何から手をつければいいか分からない…」
そんな方には、現論会の無料受験相談がおすすめです!
- 自習計画の立て方
- 学習スケジュールの見直し
- 志望校に合わせた戦略アドバイス
これらをすべて無料でご提案いたします。
📩 無料受験相談のお申し込みはこちら
現論会についてもっと知りたい方へ
現論会では、学習法や大学受験に役立つ情報を発信するYouTubeチャンネル「現論会ジャーナル」も運営しています。
雰囲気を知りたい方は、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね◎
🎥 YouTubeチャンネル:現論会ジャーナル
