定期テストの勉強だけで大丈夫?大学受験との違いを解説
更新日 : 2025年10月13日
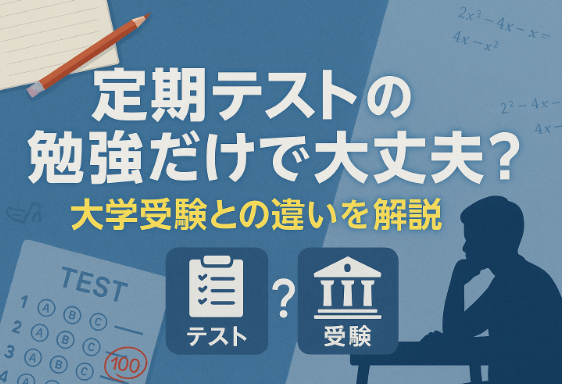
「定期テストでは点が取れるのに、模試では全然通用しない…」
そんな悩みを持つ高校生や保護者の方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、定期テストの勉強=受験勉強ではありません。
どちらも大切ですが、「目的」と「求められる力」がまったく違います。
この記事では、定期テストと大学受験の本質的な違いをわかりやすく整理し、今からできる“受験対応の勉強法”を解説します。
定期テストの勉強と大学受験勉強の違い
| 項目 | 定期テスト | 大学受験 |
|---|---|---|
| 目的 | 学校の授業理解・内申点UP | 全国規模での得点力・思考力の養成 |
| 範囲 | 限られた単元(授業範囲) | 1~3年の全範囲+複合問題 |
| 問われ方 | 「知っているか」「再現できるか」 | 「考えられるか」「初見問題に対応できるか」 |
| 勉強法 | 暗記・丸暗記中心 | 理解→応用→分析→表現まで |
| 必要な力 | 短期記憶・作業力 | 長期的な思考力・分析力・計画力 |
この表からも分かるように、「テスト勉強の延長」では受験に対応できない理由は明確です。
つまり、今のうちから“受験型”の学び方にシフトする必要があります。
なぜ定期テストの勉強だけでは成績が伸びないのか?
① 出題の「想定範囲」が違う
定期テストは「授業でやったところ」から出題されます。
一方で受験問題は、“知らない問題をどう解くか”を試されるもの。
つまり、「覚えるだけ」では太刀打ちできません。
→ 対策法:問題を解くときに「なぜこの解き方になるのか?」を常に考える。
② “短期記憶”で終わってしまう
テスト直前に詰め込んだ知識は、数日で忘れます。
受験で問われるのは「半年後・1年後に使える記憶」。
つまり、反復と定着が不可欠です。
→ 対策法:「翌週・翌月」にもう一度同じ問題を解いてみる。忘却を前提に復習計画を組む。
③ “解ける=理解している”とは限らない
学校のテストでは、授業中に扱った例題とほぼ同じ形式が出ることが多いです。
でも受験では、「形を変えて問われる」「複数の単元を組み合わせる」ことが当たり前。
一度理解したつもりでも、本当に応用できるかは別問題です。
→ 対策法:問題集を“2周目”以降で「別解を考える」「説明できるかチェック」する。
今からできる「受験型勉強」への切り替え3ステップ
① 目的を「テストの点」から「実力の蓄積」へ
「テスト範囲を覚える」ではなく、「この単元を受験で使えるようにする」と意識を変えましょう。
ノートも「見返す用」ではなく「理解を整理する用」に作るのがポイントです。
② 問題集を“復習ベース”で使う
多くの生徒が“解きっぱなし”で終わってしまいます。
間違いノート・復習日リストを作って、1週間後にもう一度解く仕組みを習慣化しましょう。
③ 科目を“横断”して考える癖をつける
特に国語・英語・社会などでは、「読解力」「要約力」「比較する力」が共通しています。
例えば、英語長文で出たテーマを日本史・現代社会でも見直すと、思考が深まります。
保護者の方へ:定期テストの点だけで安心しないために
定期テストの結果が良い=受験でも通用する、とは限りません。
お子さんが「テスト直前だけ頑張るタイプ」になっている場合、勉強習慣のリズムから見直す必要があります。
- 週単位で「家庭学習の時間」を確保する
- テスト後の「復習タイム」を一緒に決める
- “できた問題”より“できなかった問題”に注目する
現論会土浦校では、定期テストと受験勉強を「分けずに繋げる」学習計画を提案しています。
現論会土浦校のサポート
- 参考書ベースの個別学習計画:テスト・受験を一貫して管理
- 週次面談:進捗確認と「なぜできなかったか」の分析
- 自習環境完備:テスト前も集中できるスペースを提供
- メンタルサポート:モチベ低下時の切り替え支援
テスト勉強は「受験勉強の土台」にすることが大切。
現論会土浦校では、学校成績を上げながら受験力を伸ばす学習法を個別にサポートします。
「テストは取れるけど模試はダメ」——
その壁を越えるには、勉強の“目的”を変えること。
今日から「点を取る勉強」ではなく、「力をつける勉強」に切り替えていきましょう。
無料受験相談 実施中!
「今の学習法で成績が伸びるか不安…」
「何から手をつければいいか分からない…」
そんな方には、現論会の無料受験相談がおすすめです!
- 自習計画の立て方
- 学習スケジュールの見直し
- 志望校に合わせた戦略アドバイス
これらをすべて無料でご提案いたします。
📩 無料受験相談のお申し込みはこちら
現論会についてもっと知りたい方へ
現論会では、学習法や大学受験に役立つ情報を発信するYouTubeチャンネル「現論会ジャーナル」も運営しています。
雰囲気を知りたい方は、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね◎
🎥 YouTubeチャンネル:現論会ジャーナル
