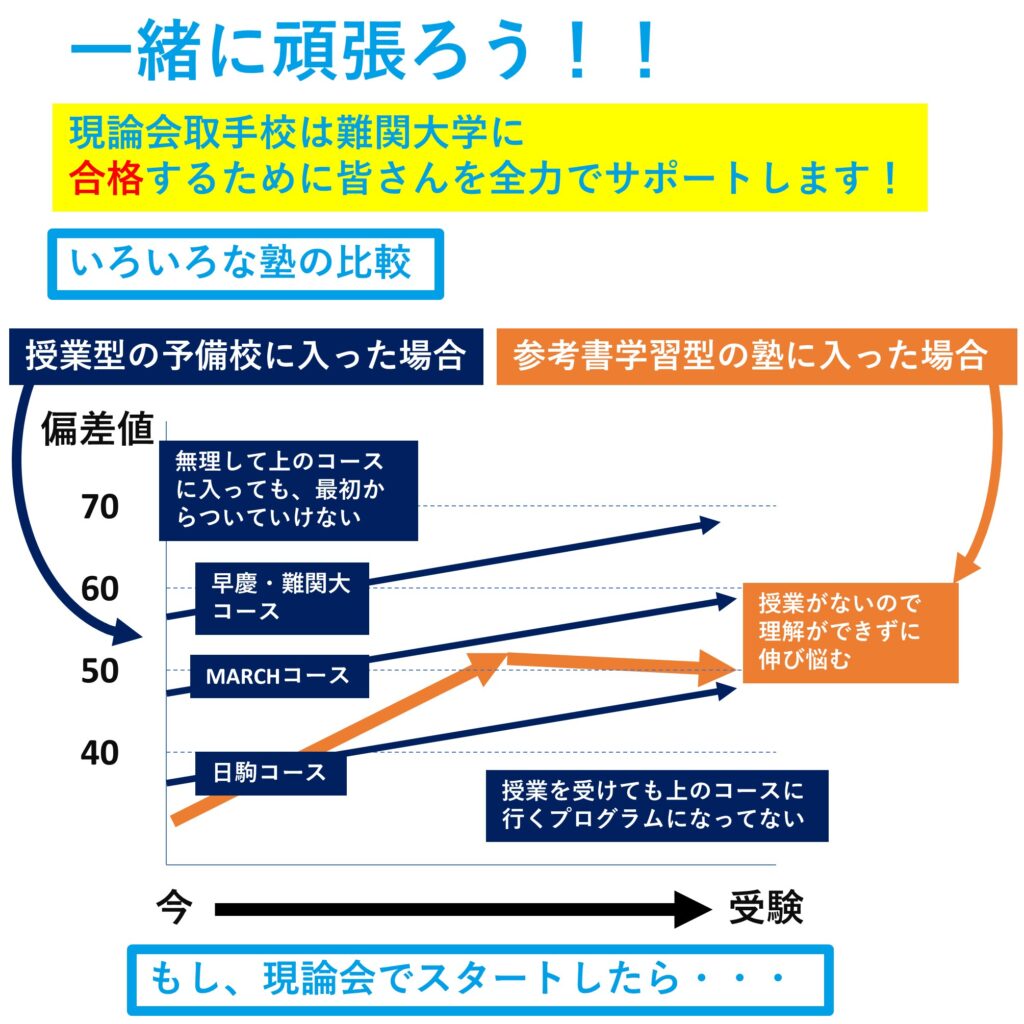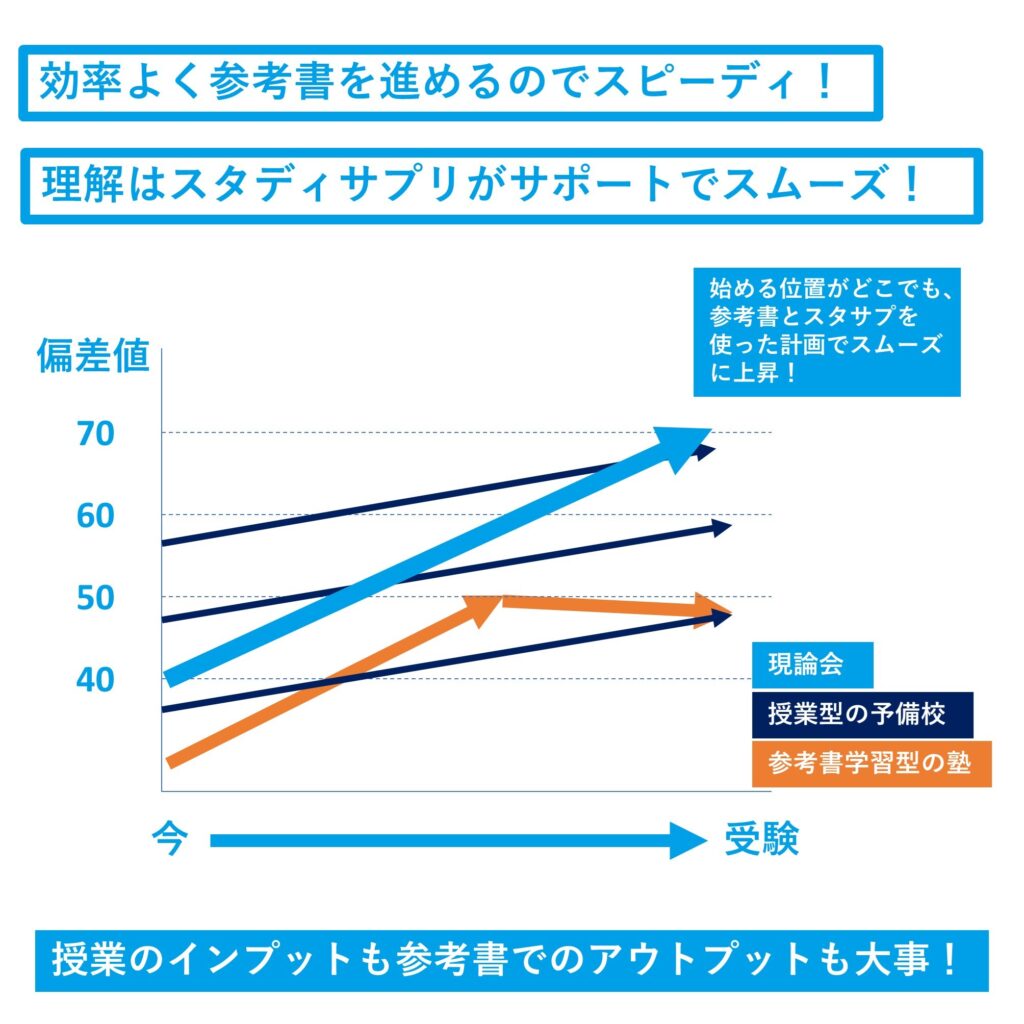【大学受験】この秋、結果に一喜一憂しない受験生の「強いメンタル」とは?|取手・龍ヶ崎・守谷・牛久・我孫子の大学受験予備校【現論会取手校】
更新日 : 2025年10月14日
はじめに:結果に揺さぶられるのが「普通」です。でも、そのままでは終わらない
模試の判定が出るたびに「もうダメかもしれない」と感じる受験生は多いものです。
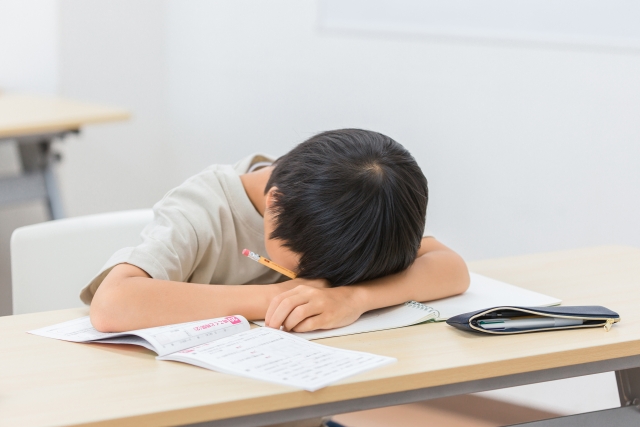
ですが実際に志望校に合格していく受験生ほど、結果の“受け取り方”が違うのです。
取手や龍ヶ崎、守谷、牛久、我孫子といった地域でも、毎年この時期になると模試の判定結果を見て焦る声が多く聞こえてきます。しかし、その焦りの中でどう行動するかが勝負の分かれ目です。
模試の結果は「戦略」の指標
模試の結果は確かに現時点での立ち位置を示すものですが、合否を決めるデータではありません。
たとえば、偏差値50から早慶に合格した生徒の多くは、秋の模試ではまだD判定やE判定を取っています。
それでも彼らが合格できた理由は、模試を「点数で一喜一憂する材料」ではなく、「戦略を修正するデータ」として活用していたから。
現論会取手校でも、模試の分析を「できなかった問題の確認」だけではなく、「次の学習計画の再設計」として扱う指導を行っています。
落ち込む前にやるべき3つの行動
①「できなかった分野」を3つに絞る
全てを復習するのは非効率。まずは「今伸びしろがある3分野」だけに集中しましょう。
例:英語なら「構文」「単語」「文法」など。
②「なぜできなかったか」を言語化する
「わからなかった」ではなく、「何が・どこで・なぜ」つまずいたかを明確にすることで、同じミスを防げます。
たとえば、「時間配分が悪い」「前提知識が抜けていた」など。
③「次の模試で試すこと」を書き出す
次の模試をリハーサルとして設定しましょう。
「解く順番を変える」「先に得点源を取る」など、小さな戦略変更が大きな結果を生みます。
高1・高2生がこの時期に考えるべき「大学受験のリアル」
高校1・2年生のうちは、「受験なんてまだ先」と感じるかもしれません。
しかし、大学受験の差は“勉強量”よりも“意識の差”で生まれます。
たとえば、現論会では高2の秋から本格的に勉強習慣を確立した生徒が、翌年の夏にはMARCH・国公立の過去問を解き始めています。
逆に、「部活が終わったら頑張る」と言っていた生徒が出遅れるケースも多いです。
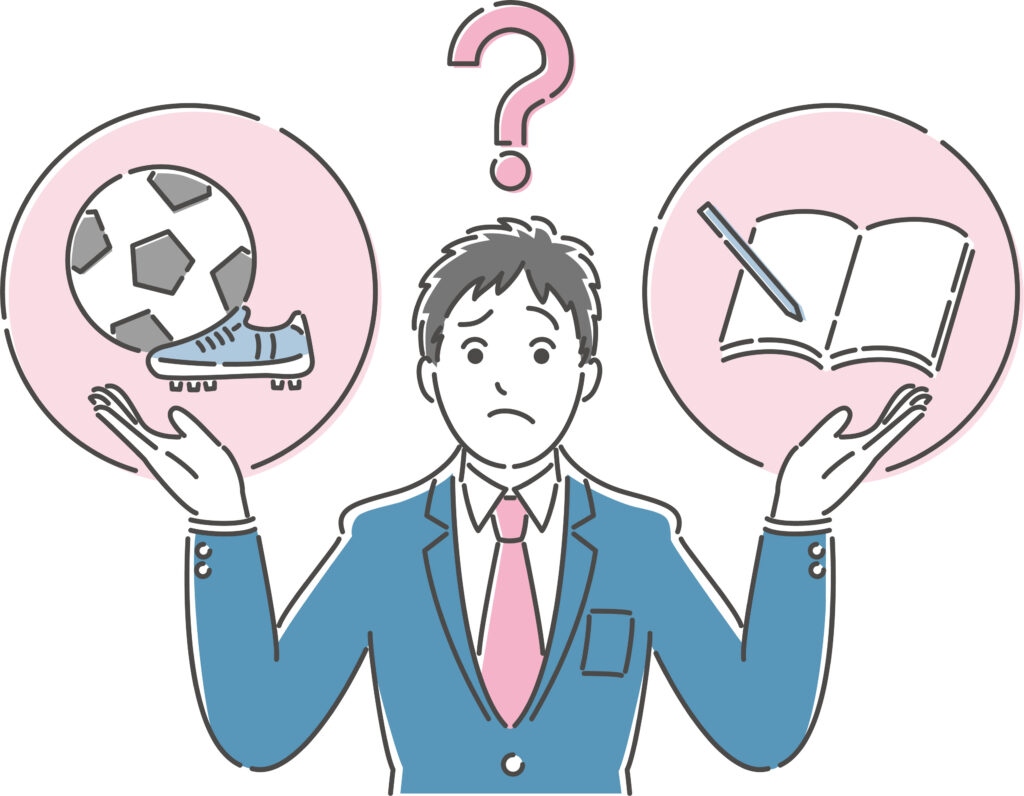
「勉強しなかった人」が動き出した瞬間とは?
「やらなきゃ」と頭で分かっていても動けない――これは多くの生徒が抱える悩みです。
ですが、人が行動を変える瞬間は、“目的”が変わったときです。
現論会取手校でも、勉強に身が入らなかった生徒が「志望校に通う自分の姿を想像して、自分も挑戦したい」と決意してから、毎日自習室に通うようになった例があります。
「誰のために」「何のために」頑張るのかを明確にすると、行動が変わります。
成績を上げたいなら、まず「自分の中のスイッチ」を見つけることから始めましょう。
というか、一緒にスイッチ探しましょう!
このスイッチは誰かと話すと構築されていく場合もあります。
志望校合格者が共通して持っていた「3つのマインド」
①「結果よりもプロセスを信じる」
判定ではなく、「昨日より今日できたか」で自分を評価する。
小さな成功体験の積み重ねが、最終的な合格力になります。
②「弱点から逃げない」
得意科目ばかり勉強しても偏差値は伸びません。
あえて苦手科目に時間を割けるかが、秋以降の伸びを決めます。
③「誰かに支えてもらうことを恐れない」
独学で限界を感じたら、塾や予備校、自習室をうまく利用しましょう。
特に取手駅周辺の自習環境を整えた現論会取手校では、**「一人で抱え込まない受験」**を実現できます。

まとめ:勝負は「結果のあと」に決まる
模試やテストの結果に一喜一憂せず、「次に何をするか」にフォーカスできる人が、最後に笑います。
高1・高2の今からこのマインドを持てれば、受験期に入ったときの伸びは圧倒的に違います。
受験勉強は孤独に見えて、実は**「仲間」や「指導者」との共創の場**です。
もし今、モチベーションや学習環境で悩んでいるなら、現論会取手校の無料相談をご活用ください。