「定期テストを制して大学合格へ!現論会取手校が伝える戦略とスケジュール」
更新日 : 2025年10月6日
はじめに:なぜ定期テストも無視できないか
大学受験において、つい「過去問」「模試」「参考書」ばかりを重視しがちですが、定期テストを疎かにすると、思わぬ落とし穴にハマることがあります。
特に推薦入試での高校内部の評定(通知表・評定平均値)が出願要件となる大学では、定期テストの成績が合否に直結します。
しかし、受験勉強との両立は容易ではありません。
そこで本記事では、
- 定期テストと受験勉強とのバランス
- 推薦入試・一般入試それぞれの対策法
- 学年別・時期別スケジュール例
を「現論会取手校」の視点から具体的に解説します。
これを読めば、「何を・いつ・どこまで手をつければいいか」がクリアになるはずです。
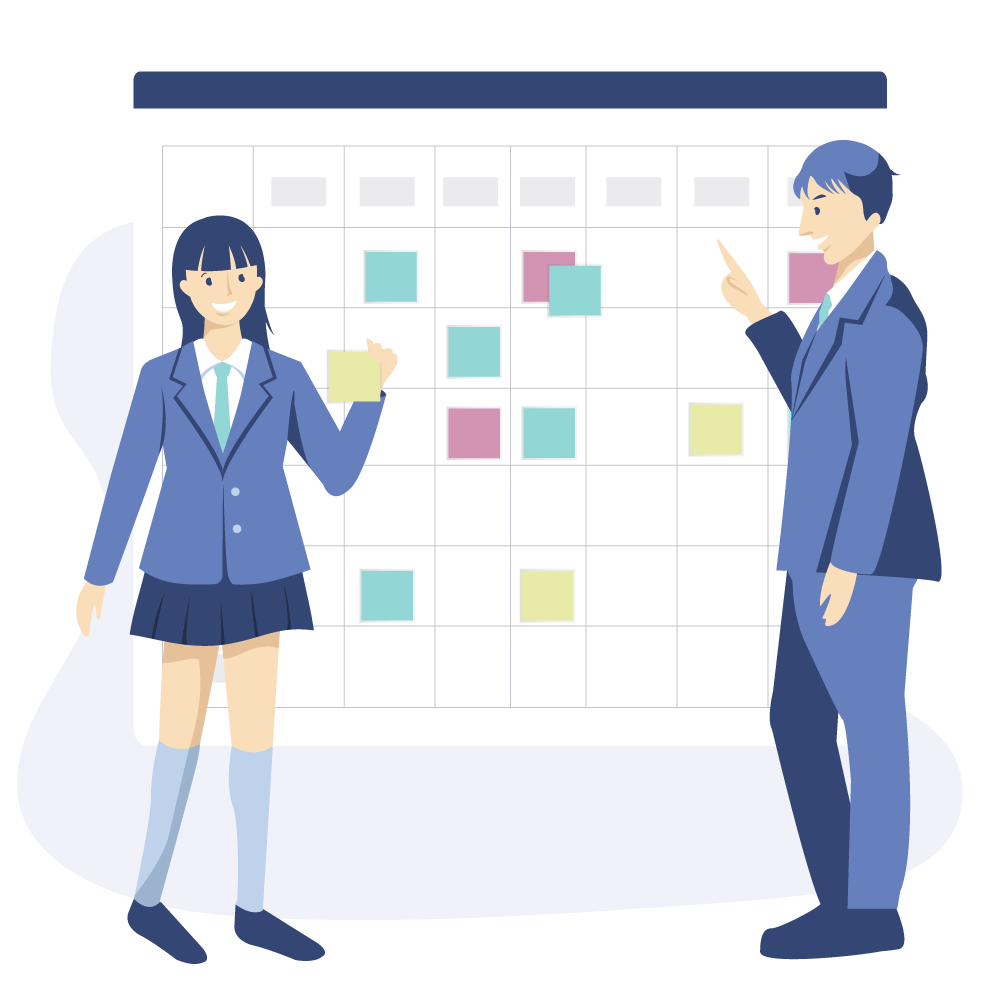
大学受験の仕組みと入試方式の基本
主な入試方式の分類
大学受験には主に以下の方式があります:
- 推薦入試(学校推薦型選抜・公募制推薦)
- 総合型選抜(旧AO入試)
- 一般選抜(大学入学共通テスト+個別試験)
国公立大学では共通テスト+2次試験で合否を判断する方式が基本。私立大学では、共通テスト利用型・独自方式・併用方式など多様です。
推薦入試や総合型選抜では、評定平均値・学業以外の活動・小論文・面接などが評価対象になります。
なぜ「逆算」戦略が鍵か
第一志望校から逆算して、必要な科目・得点ライン・対策スケジュールを設計する方法は、多くの現役難関大学合格者が実践しています。
現論会の指導体制も、志望校から逆算したオーダーメイド年間カリキュラムを重視する方針です。
逆算によって、無駄な勉強を減らし、重要な単元に集中できるようになります。
→合格可能性が一気に上がります。
定期テスト vs 受験勉強:どちらを優先すべきか
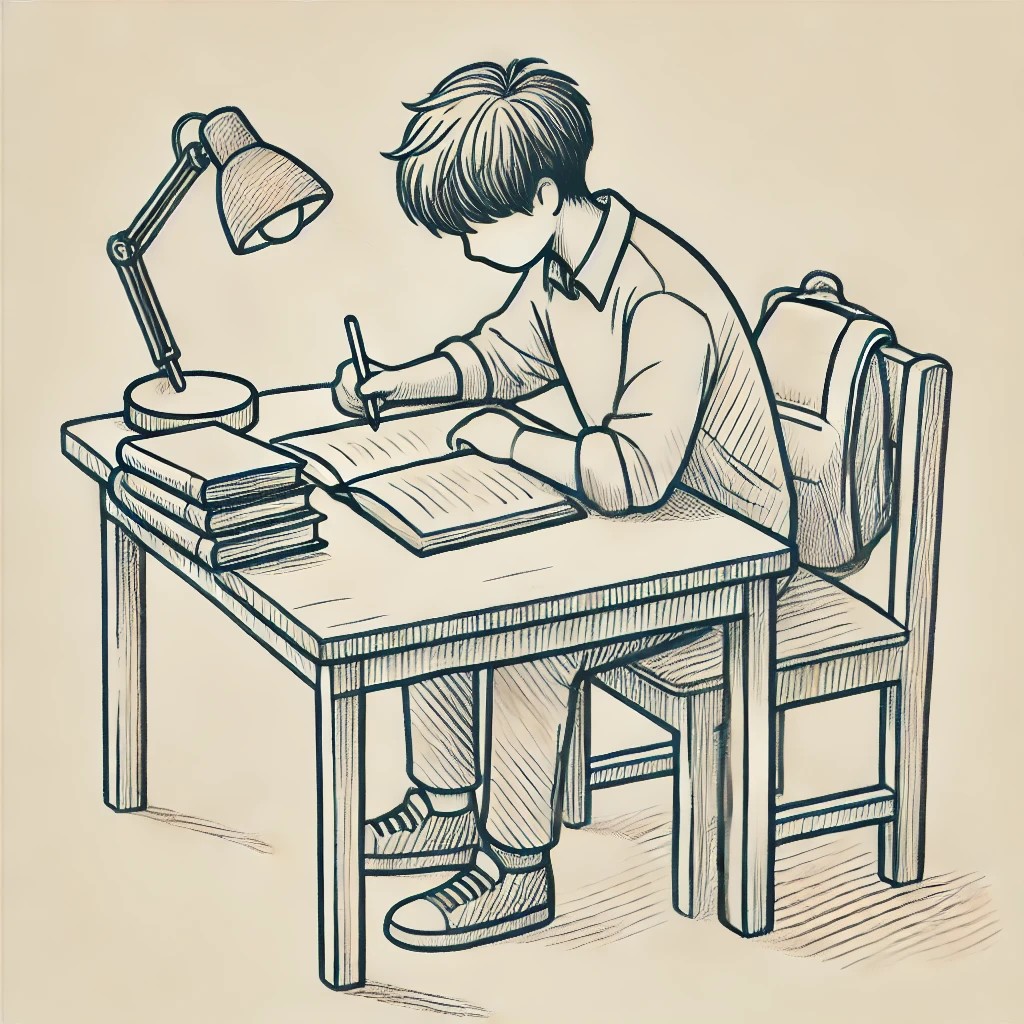
学年によって変わる優先順位
受験生(高3)にとっては、優先すべきは当然受験対策です。受験方式や必要科目・対策によってやることの計画は変わってきます。
一方、高1・高2生は学校の成績(評定)を上げることで推薦の可能性も広げられるチャンスの時期。定期テストでの高得点を積み重ねておくことが、将来の推薦枠を確保する意味でも重要です。
推薦志望者なら定期テスト重視
推薦志望者、特に指定校推薦や公募推薦を目指す場合、評定平均値が出願条件となることが多く、定期テストでの成績をしっかり取る必要があります。
ただし、推薦入試を選んだとしても、「万一落ちたときの一般入試対策」は並行して進めておくべきです。
一般志望者なら“戦略的に捨てる”時期を持つ
一般入試志望者は、受験するであろう大学の入試科目などに応じて、“戦略的に捨てる”判断も必要です。
例えば、受験に出ない定期テストの分野や出題頻度が低い範囲は、定期テストは最低限にするということは珍しくありません。
ただし、完全に捨てる前に「最低限押さえておくべき基礎」は確実に残しておくべきです。
推薦入試・指定校推薦の特徴と対策
推薦入試の種類とスケジュール
推薦入試には、 指定校推薦 と 公募推薦(学校推薦型選抜)があり、募集方式や選抜基準が大学・高校によって異なります。
指定校推薦は校内審査が重要になり、高1~高3の1学期までの評定が基準になることが多いです。
推薦は評定平均値・小論文・面接がメインになります。
つまり、高2終わり〜高3の前半には、出願するかどうか、志望大学・学部・条件(評定基準など)を決めておく必要があります。
小論文・面接対策のポイント
- 小論文:志望動機だけでなく、社会・時事・学問的テーマにも対応できる読解力・論述力が求められる
- 面接・口頭試問:自己PRや併願理由、将来志望などを明確に答えられる練習を繰り返す。ただ問題を解くだけではなく、わかりやすく説明できるように声に出して実際に練習する。
現論会では、生徒個別に志望大学別対策を織り込んだ指導を行っている点が複数校で特徴となっています。
推薦一本に頼らない安全策を
推薦入試は学力試験と違い、大学や面接官(大学教授)の考えに沿っているかを判断されます。学力試験と違い、答えが決まっているものではないので、一般入試よりも合否が読みにくいものになります。
推薦を狙うなら、併願で一般入試を受ける余裕を残す計画を立てておくことが肝要です。推薦不合格の場合、一般入試での逆転を狙う運用ができなければリスクが高まります。
一般入試(共通テスト+二次試験)対策の基本戦略
共通テスト対策のポイント
- 出題範囲は5教科7科目が基本(大学・学部により異なる)
- 基本〜標準レベルの科目を確実に得点源にする
- 模試や過去問で「時間配分・得意分野の比率」を分析
- スピード感が大事
二次試験(個別試験)対策
- 志望学部・大学の過去問を徹底研究
- 論述・記述問題への対応力を高める
- 共通テストとの相性を意識して併願大学の選定
- 難関大学ほど二次の配点割合が大きい傾向
科目選択・併願校戦略
受験科目や併願校の設計は、当然ですが「第1志望の一般選抜を軸に日程を決める」ことがセオリーです。
併願校は、安全・実力相応・チャレンジを混ぜながら、合格確保できるよう戦略を立てましょう。
この際、注意してほしいのが「なぜその大学を受けるか」です。
合格しても行かない、でも受ける。それなら本当に受ける必要があるのか、相談してください。
高1・高2生向け:今からやるべきこと
定期テストで基礎力を固める
高1・高2の段階では、「定期テストで高得点を取る習慣」をつけることが非常に重要です。基礎力が後の受験勉強を支えます。
定期テストの範囲は「学校の教科書+授業ノート」が基本。ここがおさえられていないのに、入試レベルの問題をやりたいというのは厳しい。
模試・基礎演習で実力測定
1〜2年のうちから、模試や基礎演習を活用して自分の弱点・得意単元を把握しておくことが後々有利に働きます。
推薦志望の有無を早めに検討
高2の1~3月で、推薦入試を使うかどうか。視野に入ってくるのかどうかを考えておきましょう。
推薦を狙うなら、部活動・資格・活動実績などを意識的に積み上げておきましょう。
計画習慣を身につける
- 年間・月間・週間のスケジュールを作る
- 日々のタスク(小テスト対策・復習・予習)を細かく設定
- 定期的に振り返り・見直しを行う
このような習慣を高1・高2のうちから始めることで、高3で受験勉強のスケジューリングが非常にうまくいきます。
高3生・受験直前期のスケジュール管理
〜夏休み:基礎固めと弱点補強
- 共通テストレベルの基礎的な演習
- 模試や過去問を使って弱点分野を洗い出す
- 推薦型も意識しているのであれば対策も同時並行で進める
秋以降:過去問演習と入試実践力強化
- 過去問・模試中心の訓練
- 時間制限・実践型演習を重視
- 共通テスト本番想定での模擬試験
2026年度の共通テストは 1月17日・18日(追試:1月24日・25日)、国公立2次試験は2月25日から、後期・中期日程も3月にかけて実施。
試験直前期:最終調整とメンタル管理
- 最後の3〜4週間は過去問の復習と弱点確認
- ケアレスミス対策、時間配分の確認
- 体調管理と睡眠・休息を優先
- 当日の流れ・持ち物確認
合格可能性のリスクマネジメント
- 最終的な併願校・受験日程の最終チェック
- 出願ミス・受験票忘れなどのリスク回避策
- 最後まで諦めない姿勢と戦略的な併願活用
現論会の指導方針・体制
- オーダーメイド型学習計画:志望校から逆算した年間・月間・週間計画を立てる体制。
- 映像授業 + コーチング:スタディサプリなどの映像授業を活用しつつ、現役大学生コーチが学習進捗・勉強戦略を伴走する形。
- 講師全員が難関大学合格者:現役難関大生を起用。
- 完全定額制・追加費用なし
よくある質問/悩みと応答
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 定期テスト前に受験勉強を手抜きしていい? | 志望校合格に必要かどうかで判断しましょう!必要科目であるのであれば定期テストの決められた範囲の教科書レベル(基礎)はしっかり押さえておくべきです。定期テストの内容を“受験に直結する基礎固め”と捉える視点が重要です。 |
| 推薦に落ちたらどうする? | 推薦と一般受験の両方の準備を進めながら、併願校を戦術的に選ぶことが安心への鍵です。 |
| 模試の判定が悪かったらどうすれば? | 判定は”計画の修正材料”として捉え、弱点補強+勉強計画再設計を行うべきです。模試の判定で一喜一憂しない。 |
| 高2から塾に通うのは遅い? | 遅くありません。ただし、自習習慣・計画立案力を早期に身につけておくことが大切です。 |
| 勉強が進まないときは? | 小さな目標に区切って、「1日1テーマクリア」など達成感を得ながら進める工夫が効果的です。コーチと相談して軌道修正しましょう。 |
まとめと次の一歩:現論会取手校の無料相談案内
まとめ
- 定期テストと受験勉強は、優先順位を使い分ける戦略が必要
- 推薦入試は定期成績・小論文・面接対策が肝心
- 一般入試は共通テスト+二次試験の対策を逆算して進めよう
- 高1・高2は基礎固め+定期テスト高得点習慣を重視
- 取手校では、映像授業+コーチング型指導で、あなたの合格戦略をサポート
もし「自分の現状で何をすればいいか迷っている」「おすすめの学習プランを個別に聞きたい」という方がいれば、現論会取手校では無料受験相談を実施しています。実際の成績や志望校を元にしたオリジナルプランを一緒に作成できますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、現論会全体の合格実績も豊富で、東京大学・京都大学・医学部・国公立・私立難関大学など多くの合格者を出しています。
本記事が、あなたの受験・定期テスト対策のヒントになれば幸いです。次は「あなた自身の学習スケジュールを立ててみる」ステップに進んでみましょう。
