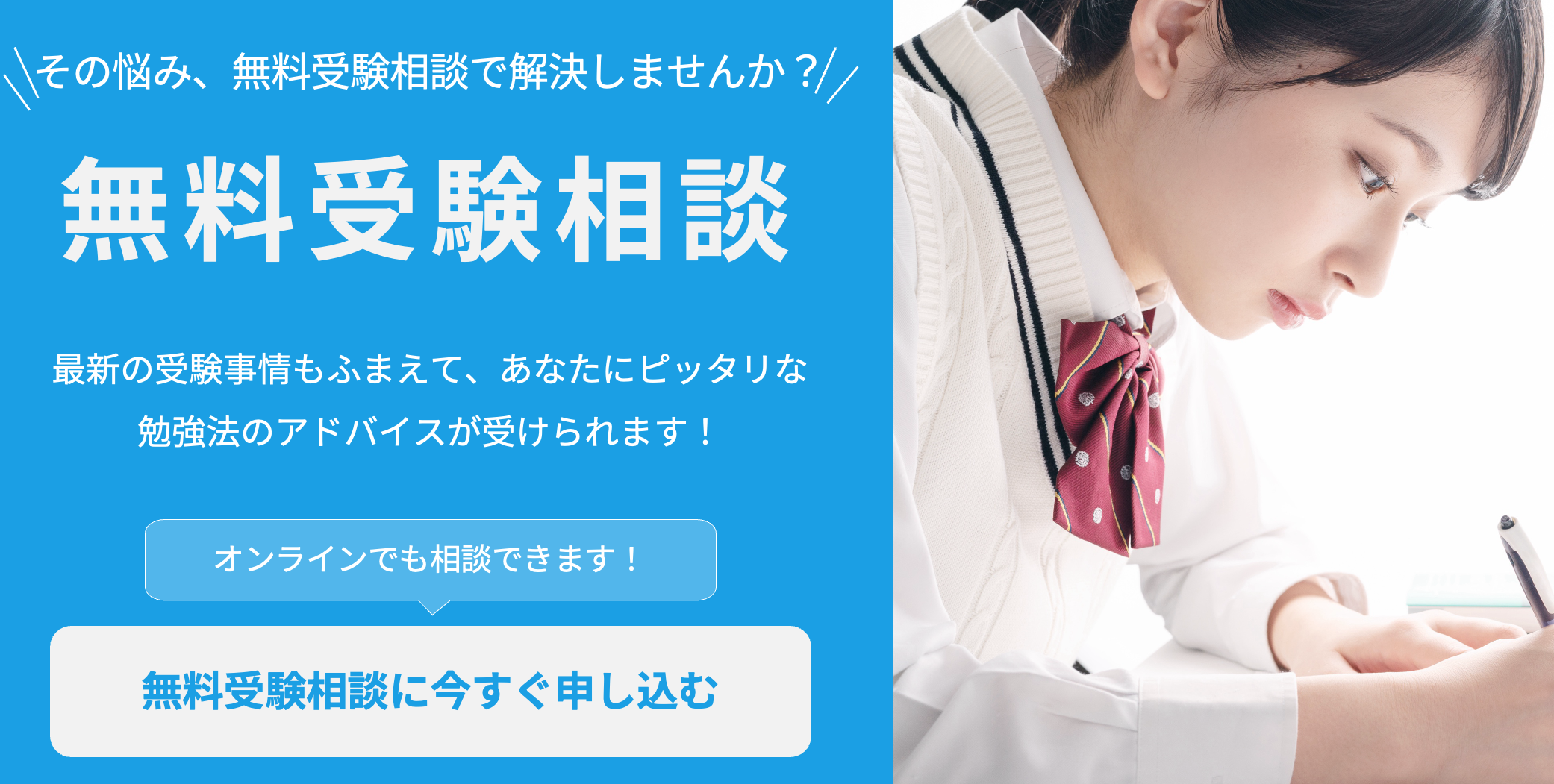衝撃の3割】過去問演習で心が折れた君へ。その「絶望」を「合格」に変える、正しい乗り越え方
更新日 : 2025年11月7日
なぜ最初の過去問は「絶望」を連れてくるのか
なぜ、あんなに勉強したはずなのに、第一志望の過去問は解けないのでしょうか。それは君の努力が足りなかったからでも、才能がなかったからでもありません。理由は、極めてシンプルです。
1. 最初の過去問は「点数が取れないのが当たり前」
まず受け入れるべき事実は、**「初めて解く第一志望の過去問で、高得点が取れる受験生は、ほぼいない」**ということです。
君が目指している第一志望校は、君にとっての「到達点」です。そのレベルの大学が課す試験は、君がこれまで受けてきた模試や、解いてきた参考書の問題とは、難易度も形式も全く異なります。
初めて解く過去問とは、
- どんな設問が来るか(形式)がわからない
- どれくらいの分量か(ボリューム)がわからない
- どう時間を使えばいいか(時間配分)がわからない という、全くのノーガード状態で戦うことを意味します。
プロボクサーだって、初めて対戦する相手の映像も見ずにリングに上がれば、苦戦するのは当たり前です。 この状況で点数が取れないのは、君の実力不足というよりも、「準備不足」であり「情報不足」なのです。 まず、この「点数が取れないのが当たり前」という事実を、冷静に受け止めることから全ては始まります。
2. 「参考書学習」と「過去問演習」の致命的なギャップ
絶望のもう一つの大きな理由は、「これまでやってきた勉強」と「過去問演習」の間に存在する、大きなギャップです。
これまでの君の勉強は、「単語帳を1冊完璧にする」「文法の参考書を仕上げる」「数学のチャートを1周する」といった、「インプット学習」や「単元ごとの問題演習」が中心だったはずです。それは、基礎体力を作る上で絶対に欠かせない、正しいプロセスでした。
しかし、過去問(入試本番)は、
- 制限時間というプレッシャーの中で、
- 全範囲からランダムに出題され、
- 複数の単元知識を組み合わせる複合問題を、
- 正しくアウトプットし、点数に結びつける
という、全く異なる能力を要求してきます。
「英単語は覚えた」はずなのに、長文の中で出会うと意味が出てこない。 「数学の解法は理解した」はずなのに、少しひねられるとどの解法を使えばいいかわからない。 「時間さえあれば解けた」のに、時間が足りなくて大問1つ丸ごと落とす。
これこそが、「知っている」と「(時間内に)解ける」の間に横たわる、深く暗い谷なのです。 最初の過去問演習は、この谷の深さを、受験生に容赦なく突きつける場なのです。
3. 絶望して「立ち止まる」のが最悪のシナリオ
問題は、点数が低いこと自体ではありません。 最大の問題は、その「低い点数」という結果にショックを受け、絶望し、過去問から目をそらし、立ち止まってしまうことです。
「まだ自分には早かったんだ」 「もっと基礎が完璧になってからやろう」 「こんな点数、誰にも見せられない」
そう言って赤本をそっと閉じ、再び「やり慣れた」参考書学習に逃げ帰ってしまう。 これが、最も不合格に近づく行動パターンです。
その点数が低い過去問こそが、合格に必要な「課題」が詰まった宝の山であるにもかかわらず、それを見ようとしないのですから。
では、どうすればいいのか。 次の章で、その絶望を「力」に変えるための「マインドセット」について詳しく見ていきましょう。
絶望を「力」に変える、合格者のマインドセット
ボコボコにされた。3割しか取れなかった。 この現実を前に、合格する受験生は、どのような「思考」をするのでしょうか。
1. マインドセット転換:「今の点数」は0点でもいい
まず、脳みそに叩き込むべき大原則があります。 それは、**「今の点数は、関係ない」**ということです。
「は? 関係なくないだろ」と思うかもしれません。 いいえ、本当に関係ないのです。
君の目的は、「今、この瞬間に過去問で高得点を取ること」ですか? 違いますよね。
君の真の目的は、「受験本番の日(来年の1月や2月)に、合格最低点を1点でも超えること」、ただそれだけのはずです。
であるならば、今の時期の過去問演習は「点数を取るための本番」ではなく、「本番で点数を取るための課題を発見する作業」にすぎません。
野球選手が、試合で打つために、練習で自分の弱点(例:内角高めの速球が打てない)をあぶり出すのと同じです。練習で打てなかったからといって「もう野球やめます」とはなりませんよね?「よし、内角高めの打ち込みをしよう」となるはずです。
今の過去問演習は、その「課題発見」の作業です。 だから、今の点数は何点でもいい。極論、0点でも構わないのです。 大事なのは、「なぜ0点だったのか」「どこで点を落としたのか」という、次に繋がる「材料」を手に入れることなのです。
2. 「伸びしろ」にこそ目を向ける
点数が3割だったということは、裏を返せば、君には「7割分」もの明確な「伸びしろ」があるということです。 それは「絶望」ではありません。「宝の山」です。
「何を勉強すれば点数が伸びるのか」がわからず闇雲に参考書をこなしていた時期は終わり、今、君の目の前には「これをやれば合格に近づける」という具体的な課題(=倒すべき敵の姿)が、ハッキリと示されたのです。
「うわ、マジか。こんなにできないのか」 「やばい、これが第一志望のレベルか」 「……ってことは、これを全部できるようにしたら、自分はめちゃくちゃ成長できるじゃないか!」
このように、視点を「できなかったこと」から「これからできるようになること」へ、ポジティブに切り替えることが重要です。
3. 過去問演習は「テスト」ではなく「学習サイクル」の一部である
「過去問演習」という言葉の響きが、君を苦しめているのかもしれません。 「演習」や「テスト」と聞くと、私たちはどうしても「良い点を取らなければならない」という強迫観念に駆られます。
ここで、捉え方を根本から変えましょう。 過去問演習は、「点数を測るテスト」ではなく、以下に示す「学習サイクル」のスタート地点に過ぎません。
- 解く(現状把握):制限時間を計って、今の実力をぶつける。
- 分析(課題発見):なぜ間違えたのか?原因(知識不足、時間不足、解法違いなど)を徹底的に洗い出す。
- 復習(課題解決):洗い出した原因を潰すため、今までの参考書に戻って完璧に仕上げる。
- 再挑戦(成果確認):別の年度や、次の過去問で、復習の成果を試す。
多くの受験生は、1の「解く」だけで一喜一憂し、絶望して止まってしまいます。 しかし、本当に大事なのは、その後の2「分析」と3「復習」です。 このサイクル全体を回すことこそが、「過去問演習という勉強」なのです。
1年目の点数など、気に病む必要はありません。 「さて、分析と復習の材料が手に入ったぞ」と、冷静に次のステップに進む準備をしましょう。
具体的な「乗り越え方」 – 課題を点数に変える「学習サイクル」
マインドセットが整ったところで、いよいよ具体的な「行動」に移ります。 ボコボコにされたその状態から、どうやって合格点を掴み取るのか。 合格に必要な「学習サイクル」を詳述します。
ステップ1:解く(=現状把握)
まずは、恐れずに「解く」ことです。 点数が取れないからといって、解くことをやめてはいけません。
理想的なペースとしては、**「週末に1年分解く」**など、自分でルールを決めて定期的に行うことです。 平日は学校や基礎学習があるため、まとまった時間が取れる土日などを利用して、本番さながらに時間を計って1年分(できれば合格最低点が出ている年度)を解き切ります。
ここでのポイントは、「解けない」とわかっていても、絶対に途中でやめないこと。 時間配分のミス、解けない問題に固執してしまう感覚、焦り。そういった「本番で起こりうること」を全て体験し、記録することこそが、このステップの目的なのです。
ステップ2:分析(=課題発見)
解き終わったら、採点です。3割でも、2割でも構いません。 点数を見て落ち込むのは5分だけ。すぐに「なぜこの点数になったのか」の分析に移ります。
この「分析」の精度が、今後の伸びを全て決めると言っても過言ではありません。 間違えた問題(あるいは、たまたま合っていた問題)を一問一問、丁寧に仕分けしていきます。
- A. 知識不足
- 英単語、熟語、文法を知らなかった。
- 日本史の用語、世界史の年代を覚えていなかった。
- 数学の公式、化学の反応式をど忘れした。
- B. 解法・アプローチミス
- 英文解釈の構造が取れなかった。
- 現代文の本文には書いてあったのに、読み落とした。
- 数学の問題文の意味を取り違え、違う解法で突っ走った。
- C. 時間不足・焦り
- 時間が足りず、大問を丸ごと落とした。
- 焦って簡単な計算ミス、ケアレスミスをした。
- 解けるはずの問題なのに、難しく考えすぎて時間を浪費した。
- D. 全く手が出ない(レベル不一致)
- 解説を読んでも、何をやっているのか理解できない。
この分析作業を、全教科、全問題で行います。 「なんとなくできなかった」を「自分は、○○大学の英語で、第2問の文法問題が知識不足で、第3問の長文が時間不足で解けなかった」というレベルまで、具体的に言語化することが重要です。
ステップ3:復習(=課題解決)
分析が終わったら、いよいよ「復習」です。 ステップ2で明確になった「自分の弱点」を、徹底的に潰していきます。
ここで、絶対にやってはいけないのが、「新しい、難しい参考書」に手を出すことです。
君がやるべきは、今まで使い込んできた「基礎の参考書」に戻ることです。
- **A(知識不足)**が原因なら、使ってきた単語帳、文法書、一問一答の、該当箇所を完璧に覚え直す。
- **B(解法ミス)**が原因なら、『基礎英文解釈の技術100』や『数学 基礎問題精講』(※一例です)など、解法を学んだ参考書に戻り、「なぜその解法を使うのか」を説明できるレベルまでやり込む。
- **C.(時間不足)**が原因なら、長文の音読や速読の練習、計算練習を復習メニューに加える。
- **D.(レベル不一致)**が原因なら、それはまだ基礎が固まっていない証拠です。その問題は一旦「捨て問」として保留し、AやBの復習に全力を注ぎます。
この「復習」の期間を、例えば平日の1週間と決めます。 週末の「現状把握」で見つかった弱点を、月曜から金曜(または次の土曜まで)の「復習」で潰し切るのです。
ステップ4:再挑戦(=成果確認)
そして、1週間の「復習」を終えたら、次の週末が来ます。 ここで、**再び過去問(別の年度)に「再挑戦」**します。
「復習」の成果は出ているでしょうか。 先週は時間不足だったが、今週は最後まで解き切れたかもしれない。 先週はボロボロだった文法問題が、今週は半分取れたかもしれない。
もちろん、そんなに甘くはありません。 「先週は3割、今週も3割5分」……そんなことはザラにあります。 しかし、落ち込む必要はありません。 「復習」が足りなかったか、あるいは「分析」が間違っていただけです。
「よし、今週の敵(過去問)は、こういう攻撃(出題傾向)が得意だったな。先週の復習じゃまだ足りなかった。よし、今週からの復習メニューはこれにしよう」
このサイクルを、ただひたすらに回し続けるのです。 「過去問を解く」→「分析する」→「復習する」→「過去問を解く」→「分析する」→「復習する」……。 この「課題発見と解決のサイクル」を、入試本番まで、愚直に回し続けるのです。
気づいた時には、絶望の「3割」だった点数は、5割、6割、そして合格最低点へと、着実に近づいているはずです。
独りよがりの「復習」に陥らないために
最後に、この「学習サイクル」を回す上で、非常に重要な注意点を2つお伝えします。
1. 情熱と冷静な戦略のバランス
「絶対に合格してやる」という情熱は、受験終盤において最強の武器です。 その執念が、君を机に向かわせます。
しかし、その情熱が「間違った方向」に向かっていては、意味がありません。 「敵(過去問)は剣で攻撃してきているのに、自分はひたすら魔法の修行ばかりしている」ような状態では、永遠に勝てません。
情熱は持ちつつも、戦略は「冷静に」立てる必要があります。 「今、自分に足りないのは『単語力』なのか、『解釈力』なのか、それとも『時間配分』の戦略なのか」 これを冷静に分析する視点が不可欠です。
2. 「客観的な視点(=指導者)」を必ず入れよ
そこで重要になるのが、「客観的な視点」です。 受験生は、必死になればなるほど、自分の状況を客観的に見ることが難しくなります。
「自分はこれが足りないんだ!」と、一つの弱点に固執して突っ走ってしまう。 本当の弱点は別にあるのに、それに気づけない。 これは、多くの受験生が陥りがちな「独りよがりな勉強」です。
可能であれば、「塾や予備校、学校の先生」など、指導経験のある人を頼ることが非常に有効です。
指導者(特に合格実績のある先生)は、君が今ハマっている「沼」が、他の受験生も通ってきた「よくあるパターン」であることを知っています。
「あ、君は今、その沼にハマってるんだね。そこは、こうやって復習すれば抜け出せるよ」 「君は『文法』が原因だと思ってるけど、データを見ると本当の原因は『長文を読むスピード』だよ」
こうした客観的なアドバイスは、君が「間違った復習」に費やすはずだった、貴重な数週間、あるいは1ヶ月という時間を節約してくれます。 独りよがりにならず、信頼できる指導者に自分の分析結果(採点済みの過去問)を見せ、積極的にアドバイスを求めましょう。
その絶望は、合格への第一歩
第一志望の過去問で、3割しか取れなかった君へ。
その絶望は、君が本気で第一志望を目指し、高い壁に挑んでいる「証拠」です。 そして、それは全ての合格者が、かつて通ってきた「通過儀礼」でもあります。
恐れる必要はありません。 今日味わった絶望を、決して忘れないでください。 その悔しさを、明日からの「復習」のエネルギーに変えてください。
「解く」→「分析」→「復習」→「再挑戦」
このサイクルを、情熱を持って、しかし冷静な戦略(客観性)を失わずに、入試本番のその日まで、ただひたすらに回し続ける。
それが、今日「3割」だった君が、来年の春、合格最低点を「1点」上回るための、最も確実で、最も正しい「乗り越え方」です。
その絶望は、終わりではありません。 合格に向けた、本当の戦いの「スタートライン」なのです。
無料受験相談も実施中
現論会の受験相談はいつでも無料で、受け付けておりますので、お電話やHPの「無料受験相談」から気軽にお問い合わせください!
現論会は、東大・京大・医学部・早慶上理・GMARCHなどの難関大学合格者である凄腕の専属コーチが、独自の学習コーチングで生徒の大学受験勉強を全力でサポートする学習塾です。難関大学受験を乗り越えたコーチたちが、個々の生徒に応じてオーダーメイドで1日単位で学習計画を作成いたします!南浦和で大学受験に対応した塾をお探しの際は是非、南浦和駅から徒歩2分の埼玉県さいたま市にある現論会南浦和校をご利用ください。