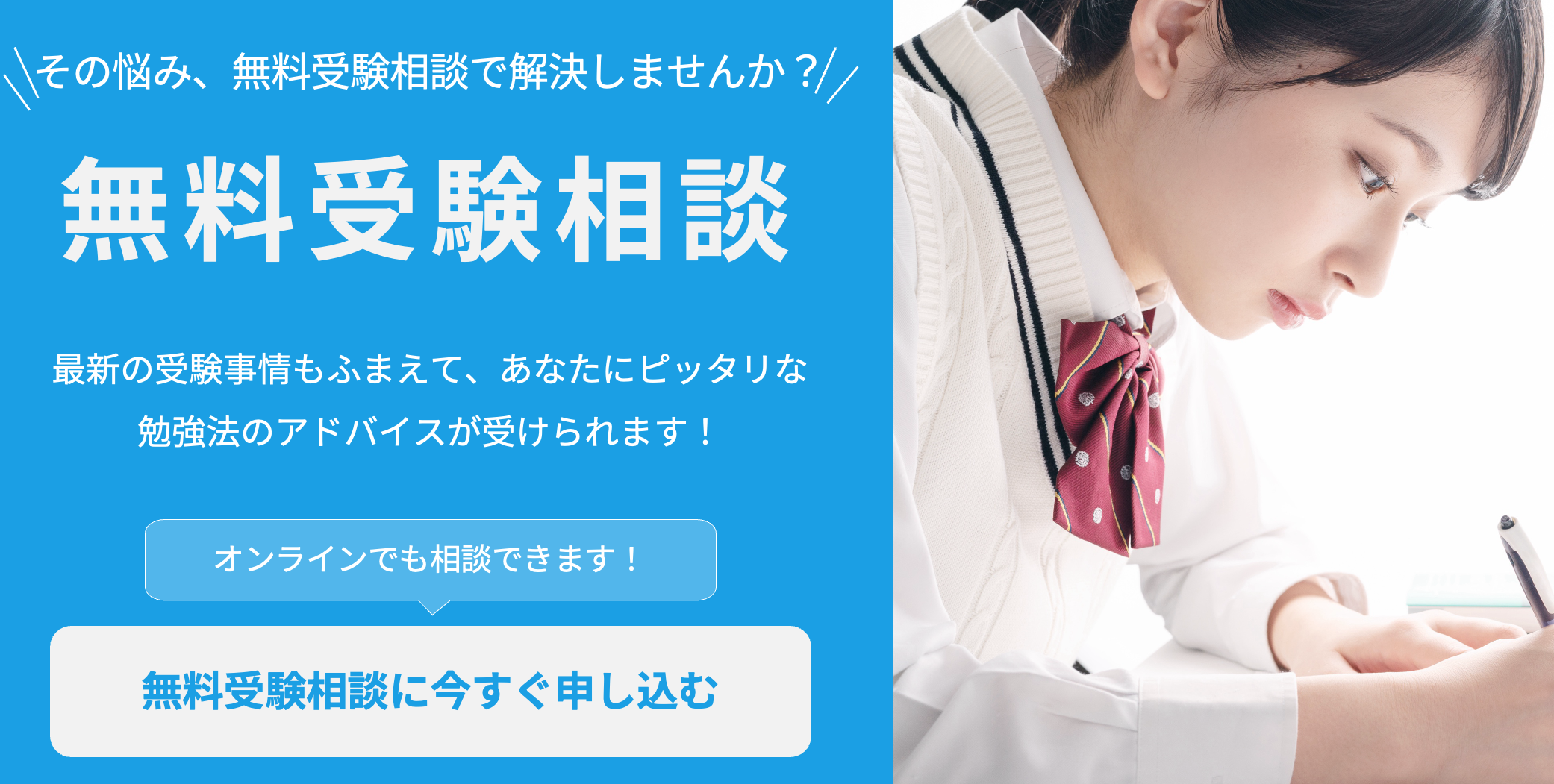模試対策 完全攻略 7つのステップ|現論会南浦和校
更新日 : 2025年10月2日
ここから、模試の点数と偏差値を確実に上げるための具体的な7つのステップを解説します。
ステップ1:模試2週間前までの「戦略的準備」
模試の点数は、当日ではなく、その前の準備段階で半分が決まると言っても過言ではありません。
1-1. 試験範囲の正確な把握と優先順位付け
ほとんどの模試には「出題範囲」が明記されています。まずはこれを正確に把握しましょう。
- 【直前対策の黄金律】 既習範囲のうち、「少し復習すれば確実に解けるようになりそうな分野」を最優先で復習します。苦手すぎてどうにもならない分野に固執するより、コスパの良い分野で確実に点数を積み重ねる戦略が有効です。
- 未習範囲への対応: もしまだ学校で習っていない範囲が含まれていても気に病む必要はありません。未習範囲は「本番ではない」と割り切り、まずは既習範囲での満点を目指す意識を持ちましょう。
1-2. 模試形式に慣れる(時間配分のシミュレーション)
模試は、通常の定期試験とは異なり、時間との戦いです。
- 過去問の活用: 同じ予備校が実施した過去の模試があれば、時間厳守で解いてみましょう。この際、**「どの問題にどれくらいの時間をかけるか」**という時間配分の計画を立てておくことが重要です。例えば、英語の長文読解に何分、文法問題に何分、といった具合に具体的な目安を設定します。
- 当日持ち物チェック: 受験票、鉛筆(シャーペン)、消しゴム、時計、会場までの地図、軽食・飲み物など、忘れ物がないか入念にチェックリストを作成し、前日に準備しておきましょう。
1-3. 生活リズムの最適化
模試は朝早くから始まります。試験日の1週間前から、試験開始時刻に合わせて脳が活性化するように、起床時間や就寝時間を調整しましょう。当日の朝食の内容も、試験中に胃もたれなどを起こさないよう、シミュレーションしておくと万全です。
ステップ2:模試前日・当日の「メンタル&フィジカル戦略」
最高のパフォーマンスを発揮するための最終調整です。
2-1. 前日は「新しいことをしない」勇気を持つ
前日は、一夜漬けで新しい知識を詰め込むのは厳禁です。かえって脳が疲弊し、当日集中力を欠く原因となります。
- 【確認作業のみ】 前日に行うのは、これまで取り組んできた「まとめノート」や「暗記リスト」の確認作業に留めましょう。新しい問題に手を出す必要はありません。リラックスして早めに休むことが、何よりも点数アップに繋がります。
2-2. 試験開始直後の「5分間戦略」
試験開始直後の5分間は、焦りを抑え、冷静になるための大切な時間です。
- 問題用紙全体の確認: まず全ページをめくり、問題構成、大問数、配点(わかる範囲で)をざっと把握します。
- 時間配分の最終調整: 確認した問題構成を元に、どの問題にどれだけ時間を割くかの「作戦」を頭の中で再確認します。この作戦に沿って解答を進めることで、試験時間全体を見通すことができます。
2-3. 「解く順番」の最適化
解きやすい問題から確実に点数を取るのが鉄則です。
- 【鉄則】 難易度の高い問題や、時間がかかりそうな長文・記述問題を後回しにする。
- 【マークシートの注意点】 解答順序がバラバラになっても、マークミスをしないよう、大問が終わるごとにマークを塗りつぶす時間を設けるなど、工夫が必要です。焦ってまとめてマークしようとすると、必ずミスが起こります。
ステップ3:模試後すぐに行う「自己採点と感情のコントロール」
模試で最も重要なフェーズがここから始まります。模試が終わった瞬間から、勝負は始まっています。
3-1. 模試会場を出る前に「自己採点」を済ませる
疲れていると思いますが、記憶が鮮明なうちに自己採点をしましょう。
- 【重要性】 自分の解答の根拠がまだ頭に残っているため、なぜその答えを選んだのかを後で分析する際に非常に役立ちます。時間が経つと、その時の思考過程を忘れてしまいます。
- 解答用紙に印をつける: 迷った問題、自信のない問題には必ず印をつけておきましょう。復習時の効率が格段に向上します。
3-2. 点数に「一喜一憂しない」メンタルの確立
自己採点で点数が予想より低かったとしても、絶対に落ち込まないでください。模試は点数を取るためのものではなく、**「次に点数を取るための材料」**です。
- 点数 < 失点理由:重要なのは点数そのものではなく、「なぜその点数になったのか」という失点理由の分析です。結果がどうであれ、「自分の弱点がわかったからラッキーだ」と前向きに捉えましょう。
3-3. 失点原因を「3つのタイプ」に分類する
復習の効率を上げるため、間違えた問題の失点原因を必ず以下の3つに分類してください。
- 知識不足: 単語、公式、年号などの暗記すべき事項を知らなかった。(→暗記・インプットで解決)
- 解法・理解不足: 問題の解き方を知らなかった、あるいは応用が利かなかった。(→問題集での演習・アウトプットで解決)
- ケアレスミス: 計算間違い、問題文の読み間違い、マークミス、時間配分の失敗など。(→見直し・環境整備で解決)
この分類によって、次に行うべき対策が明確になり、闇雲な学習を避けることができます。
ステップ4:成績表から「弱点分野」を炙り出す徹底分析法
後日返却される成績表は、あなたが今一番取り組むべき課題を教えてくれる「宝の地図」です。
4-1. 成績表の「志望校判定」は参考程度に
「A判定だから安心」「E判定だから絶望」と極端に考えるのはやめましょう。特に初期の模試の判定は、あくまで現時点の学力と志望校との距離を示す「参考値」です。大切なのは、以下の客観的データです。
4-2. 徹底的に見るべき「客観的データ」
- 設問別正答率: 間違えた問題の正答率をチェックします。
- 正答率が高い(60%以上)問題での失点: これは「大多数の受験生が解けている問題」です。最優先で復習し、二度と間違えないようにすることが、偏差値アップの最短ルートです。ここで失点している限り、偏差値が大きく上がることはありません。
- 正答率が低い(20%以下)問題: 現時点では、難問すぎて多くの受験生が解けていません。志望校のレベルにもよりますが、無理に時間をかけず、後回しにしましょう。
- 平均点との比較: 科目ごとの平均点、偏差値を確認し、どの科目が自分の足を引っ張っているのか、あるいは得意科目として更に伸ばすべきかを見極めます。
- 分野別・単元別正答率: どの分野(例:数学の「図形と方程式」、英語の「文法・語法」)が苦手なのかを具体的に特定します。このデータこそが、今後の学習計画の「核」となります。
4-3. 弱点分野を「可視化」する
成績表のデータに基づき、自分の学習計画表やノートに、苦手分野を色分けして記録しましょう。苦手な分野にマーカーを引き、目に見える形でリストアップすることで、「次はここを潰す」という意識付けがしやすくなります。
ステップ5:弱点を「克服」する具体的な復習ノート作成術
分析で特定した弱点を、次に受ける模試までに確実に克服するための復習方法です。
5-1. 「模試復習ノート」を必ず作成する
模試の解答用紙や問題集に直接書き込むのではなく、専用の「模試復習ノート」を作成しましょう。このノートが、入試直前の最強の武器になります。
- 【構成要素】
- 問題の概要: 模試名、科目、大問番号、問題番号を明記。
- 失点原因: ステップ3で分類した「知識不足」「解法不足」「ケアレスミス」のいずれかを必ず記入。
- 正しい解法プロセス: 正解を導くための思考の順序、公式、解答手順を、自分の言葉でわかりやすく記述。ただ模範解答を書き写すだけでは意味がありません。
- 「次に活かすこと」: 今後類似問題が出たときに間違えないための具体的な反省点やチェックリスト(例:単位の確認を怠らない、長文読解の段落ごとの要点をメモするなど)。
5-2. ケアレスミスの「可視化と対策」
ケアレスミスは「ミス」ではなく「実力」の一部です。特にケアレスミスで失点した問題は、原因を具体的に特定し、再発防止策を打ち立てることが重要です。
- 例: 「計算用紙に書いた数字を解答用紙に写し間違えた」→「解答用紙に転記する前に、必ず指差し確認をする」
- 例: 「問題文の『誤っているものを選べ』を『正しいものを選べ』と勘違いした」→「問題文の重要指示語には必ず赤ペンで丸をつける」
5-3. 復習は「解き直し」から「定着」へ
復習は一度やって終わりではありません。
- 当日: 自己採点と失点原因の分類
- 翌週: 復習ノートを作成し、解き直し
- 2週間後: 復習ノートを見ずに、間違えた問題の類題やそっくりな問題集の問題を解いてみる(定着度の確認)
この**「時間の経過を置いて再度確認する」**工程が、記憶を長期的に定着させる鍵となります。
ステップ6:模試結果を元にした「学習計画の再構築」
模試の結果は、あなたの学習ロードマップを修正するための最高のインプットデータです。
6-1. 「弱点克服」と「得意伸長」のバランスを取る
模試で露呈した弱点ばかりに時間を割くのは非効率です。
- 【戦略的バランス】
- 時間配分: 弱点克服に6割、得意科目の維持・伸長に4割を目安に時間配分を見直しましょう。得意科目を放置すると、いつの間にか苦手科目になってしまうことがあります。
- 基礎の徹底: 特に正答率の高い問題(=基礎的な知識)を落としている場合、一時的に応用問題の演習をストップし、徹底的に基礎のテキストに戻ってやり直す勇気を持ちましょう。基礎が固まれば、応用力は後から自然についてきます。
6-2. 志望校の「出題傾向」と模試結果を照合する
志望校の過去問を分析し、**「模試で間違えた分野」と「志望校の頻出分野」**が重なっているかを確認します。
- 重複分野: 重複している分野(例:志望校で微分積分が頻出だが、模試でその分野の点数を落とした)は、最優先で対策を強化します。
- 非重複分野: 模試で間違えたが、志望校ではほとんど出題されない分野であれば、対策の優先順位を下げても問題ありません。すべての分野を完璧にする必要はありません。合格に必要な得点源に焦点を絞りましょう。
6-3. 次の模試までの「短期目標」を設定する
次の模試をただ受けるのではなく、具体的な「短期目標」を設定して臨みましょう。
- 目標例:
- 「今回の模試で失点した数学の『確率』分野で、次回は必ず満点を取る。」
- 「英語の長文読解の解答時間を5分短縮する。」
- 「ケアレスミスによる失点をゼロにする。」
具体的な目標を持つことで、日々の学習に緊張感と目的意識が生まれ、より集中して取り組むことができるようになります。
ステップ7:模試の種類別「受験の心構え」
最後に、模試の種類ごとの対策のポイントを整理しておきましょう。
7-1. 予備校別模試(河合塾、駿台、東進など)
- 特徴: 多くの受験生が受験するため、自分の相対的な位置を測るのに最も適しています。判定の信頼度も高いです。
- 活用法: 判定結果だけでなく、母集団の中での自分の順位を重視しましょう。特に上位層での順位の変動は、ライバルとの差を測る重要な指標になります。現時点での自分の立ち位置を客観視するツールとして活用します。
7-2. 記述式模試 vs マーク式模試
- マーク式(共通テスト形式など): **「スピード」と「正確な知識」**が問われます。対策は、反射的に正解を選べるほどの基礎知識の徹底と、マークミス対策に重点を置くこと。
- 記述式(二次・私大形式など): **「論理的な思考プロセス」と「表現力」**が問われます。対策は、解答に至るまでの思考過程を答案に示せるように、復習ノートで「なぜそうなるのか」を言語化する練習に重点を置くこと。部分点を狙うための答案作成能力も重要です。
7-3. 志望校別オープン模試・実戦模試
- 特徴: 志望校の出題傾向に合わせて作られており、本番シミュレーションとして最も有用です。
- 活用法: 採点が厳しく、結果が悪く出ることが多いですが、気にせず「本番の予行演習」として受け止めます。時間配分、当日会場までの移動、休憩時間の過ごし方など、すべてのシミュレーションを行いましょう。この模試での失敗こそが、本番の成功に繋がります。
無料受験相談も実施中
現論会の受験相談はいつでも無料で、受け付けておりますので、お電話やHPの「無料受験相談」から気軽にお問い合わせください!
現論会は、東大・京大・医学部・早慶上理・GMARCHなどの難関大学合格者である凄腕の専属コーチが、独自の学習コーチングで生徒の大学受験勉強を全力でサポートする学習塾です。難関大学受験を乗り越えたコーチたちが、個々の生徒に応じてオーダーメイドで1日単位で学習計画を作成いたします!南浦和で大学受験に対応した塾をお探しの際は是非、南浦和駅から徒歩2分の埼玉県さいたま市にある現論会南浦和校をご利用ください。