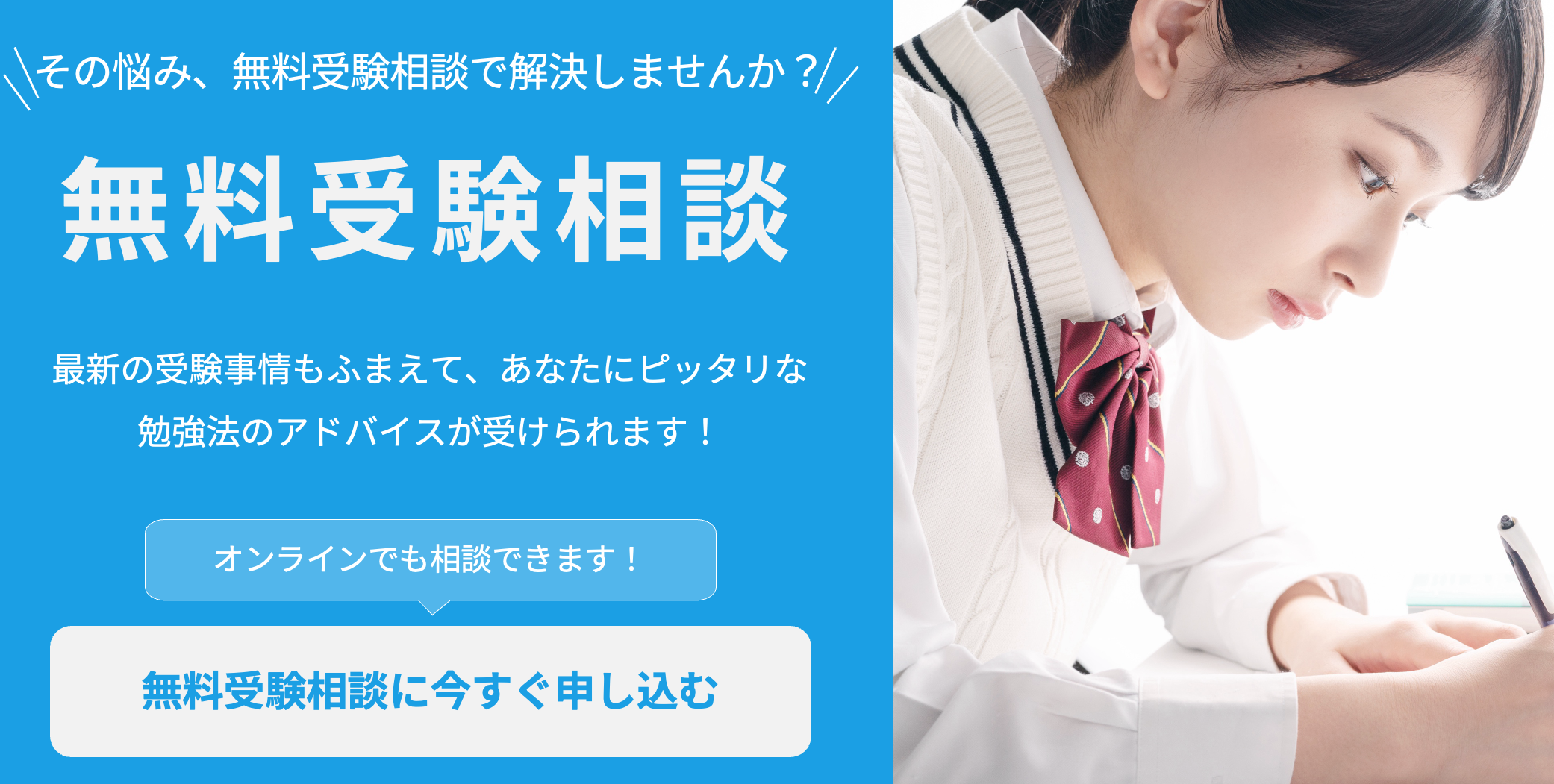マーク模試で絶対失敗しない!「大事故防止」攻略法|現論会南浦和校
更新日 : 2025年10月16日
僕自身の受験経験、特にADHD気質でケアレスミスが多かったという反省を踏まえてたどり着いた結論。それは、**「記述模試よりも、マーク模試のほうが大事故のリスクが高い」**ということです。
なぜなら、マークシートという均一な回答形式は、一度ズレると連鎖的にミスを生み、最後まで気づきにくいという恐ろしい特性を持っているからです。
Part 1:試験開始前の「命を救う」徹底チェック(★重要度MAX
チャイムが鳴り、試験開始の合図があった瞬間から、あなたは戦いの準備を整えなければなりません。この数分間のアクションが、本番の点数に直結します。
① 問題用紙は必ず最後まで確認する
「配点を把握して時間配分を決める」——これは誰もが言うことですが、それ以上に重要なのは**「解くべき問題が合っているか」**の確認です。
- チェックポイント: 数学I・A/II・B、社会科目のように選択問題が多い科目は特に危険です。チャイムが鳴ったら、問題冊子の表紙と、実際に解き始める大問の頭を確認し、自分が受験する科目に間違いがないかを、まず一呼吸置いて確認してください。毎年必ず「違う問題を解いてしまった」という受験生が出ます。
- 大問・マーク総数の把握: その後、すぐに全ページをめくり、大問の数やマークの総数(行数)を把握します。毎年同じ形式だと思っていても、出題構成が急に変わる可能性はゼロではありません。正確な情報に基づいて、その日の戦術を組み立てましょう。
② マークシートの「座標」を確かめる
ケアレスミスの王様、「マークのズレ」を防ぐための基本的な、しかし最も重要な対策です。
- 「0」と「1」の位置に注意: 共通テスト形式では、回答の選択肢が「0, 1, 2, 3…」と始まる場合と、「1, 2, 3, 4…」と始まる場合があります。マークシートの行の一番左の選択肢が「0」なのか「1」なのかを、一瞬で良いので確認するクセをつけてください。特に普段、英検や私大など、さまざまなマーク試験を受けている人は要注意です。
Part 2:解いている途中の「思考を止めない」テクニック
問題の難易度に集中しながらも、ミスなく効率的に進めるための具体的な技術です。
③ 答えは「問題用紙に清書してから」マークせよ
僕が最も大切にしていたルールの一つが、**「二つの異なる作業を同時に行わない」**ことです。
- 原則: 計算(思考)とマーク(記入)は、脳内で全く別の作業です。計算結果を導き出しながら、それをマークシートの適切な位置に転記するという**「二重作業」**は、ミスを引き起こす温床となります。
- 実践方法:
- 問題用紙の余白に、計算の最終的な答えを分かりやすいように大きく書き出す。
- その答え(例:34)を「見て」、マークシートに転記する(例:分子の「4」、分母の「3」をマーク)。
- 特に数学の分数は要注意!日本語では「分母分の分子」と言いますが、マークシートでは「分子」が先で「分母」が後になるケースが多いです。この日本語の順番とマークの順番のズレを、問題用紙に書き出した清書された数字を介することで解消します。
④ 「核信度」によるトリアージ(仕分け)を徹底する
試験中に時間が余るか、足りなくなるかは最後まで分かりません。どちらに転んでも最大限の点数を獲得するために、常に問題の「状態」を記録します。これは、時間がないときに「何を優先して見直すか」を決める**トリアージ(優先順位付け)**です。
- 確信が持てる問題(安全): 「これは絶対に合っている」と断言できる問題は、解答番号に大きな**「◎」や「丸」**をつけて、今後一切見直さないという決断をします。
- 迷った問題(要対応): 2択で迷った、計算ミスが不安など、あと少しで見直せる問題は**「△」**。時間があれば最初にここから潰しに行きます。
- 全く分からない問題(低優先): 知識がなく手が止まった、明らかに難易度が高い問題は**「?」**。最後に時間が余ったら鉛筆転がし(アテカン)や、短時間での知識検索に挑みます。
このトリアージを行うことで、「時間が余ったのに、どこを見直せばいいか分からない」という最悪の事態を防げます。
⑤ 「〇」と「×」のルールを統一する
社会科や理科、英語など、選択肢の正誤判定が求められる科目で、最も危険なケアレスミスを防ぐ方法です。
- ルール: 問題文が「適切なものを選べ」であっても、「不適切なものを選べ」であっても、**選択肢の文章の内容が「正しい」ものには必ず「〇」をつけ、「間違い」の文章には必ず「×」**をつけます。
- 効果:
- この作業で選択肢を仕分けした後、「〇」がついた選択肢、または**「×」がついた選択肢**が一つだけ残るはずです。
- 最後に残った一つ(例えば「×」のついたもの)が設問の要求(例:「不適切なもの」)と合っているかを照らし合わせ、その番号をマークします。
この方法を徹底すれば、問題文の「不適切」という一言を見落としたとしても、選択肢の「×」印がそれを思い出させてくれるため、大事故を回避できます。
Part 3:時間管理と自己暗示の「メンタル」戦略
ミスを防ぎ、最高のパフォーマンスを発揮するためには、道具や精神的な側面からのアプローチも必要です。
⑥ 使う道具へのこだわりと工夫
- 鉛筆を使う:シャープペンシルではなく、鉛筆を使いましょう。芯が太いため、一度に塗れる面積が大きく、マークにかかる時間を確実に短縮できます。
- 芯の硬さと削り方:普段使いより濃いBや2Bの芯を選び、先端を少し丸く削っておくのがおすすめです。尖らせすぎると折れるリスクや塗る回数が増えます。
- 予備の準備:念のため、鉛筆は最低5本、できれば10本程度(折れたとき、芯が減ったときに交換するため)持っていくのが理想です。
⑦ 判断コストを下げて、思考リソースを温存する
模試や本番では、極限の集中力が要求されます。余計な判断で脳のリソースを消費してはいけません。
- アテカン(勘)の戦略: 迷った問題で「Aにしようか、Bにしようか…」と時間を浪費するくらいなら、**最初から「迷ったら必ずCを選ぶ」**など、自分のルールを決めておきましょう。
- これにより、その場で判断するコスト(リソース)を節約できます。節約した5秒で、他の簡単な問題を1問解く時間が生まれるかもしれません。アテカンは**「当たること」よりも「判断コストを下げ、時間を稼ぐこと」**に真の価値があります。
- 「人事を尽くして天命を待つ」という自信: 僕が受験生時代、特に意識していたのは、**「不安要素を潰し、自信を持つこと」**です。
- マークシートの説明書きを熟読する、道具を完璧に揃える、トリアージを完璧にする。これらは一見無駄な作業に見えても、**「自分はやるべきことを全てやった。だからマークミスはないはずだ」**という揺るぎない自信となり、本番で冷静さを保つ土台になります。
終わりに:マーク模試は「学力測定」と「慣れ」の場
今回の模試は、あなたの学力を測る場であると同時に、これらの「大事故防止テクニック」を練習する絶好の機会です。
- 大事故のリスクがある
- 確信度の仕分けが求められる
- 時間との戦いが厳しい
これがマーク試験の特性です。
普段の演習ではできない「本番形式でのトリアージ」や「道具の使い方の練習」を、この週末の模試で実践してみてください。今日紹介したテクニックを一つでも徹底できれば、あなたのマーク模試の点数は確実に安定するでしょう。
学力は日々の努力で培われます。そして、その学力を最大限に発揮するためには、これらの攻略法が不可欠です。
最高のパフォーマンスを発揮できるよう、心から応援しています。
無料受験相談も実施中
現論会の受験相談はいつでも無料で、受け付けておりますので、お電話やHPの「無料受験相談」から気軽にお問い合わせください!
現論会は、東大・京大・医学部・早慶上理・GMARCHなどの難関大学合格者である凄腕の専属コーチが、独自の学習コーチングで生徒の大学受験勉強を全力でサポートする学習塾です。難関大学受験を乗り越えたコーチたちが、個々の生徒に応じてオーダーメイドで1日単位で学習計画を作成いたします!南浦和で大学受験に対応した塾をお探しの際は是非、南浦和駅から徒歩2分の埼玉県さいたま市にある現論会南浦和校をご利用ください。